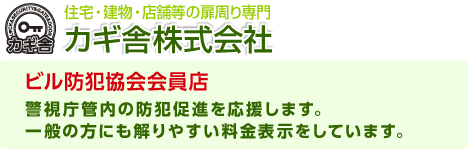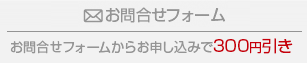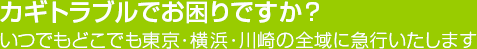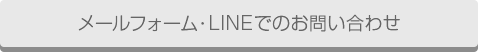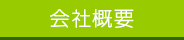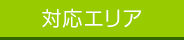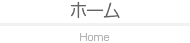引き戸に後付けできる鍵の種類と設置方法
建物のバリアフリー化や空間の間仕切りになる引き戸は、さまざまな場所で採用されています。しかし、鍵を取り付けていない場合は、小さな子どもやペットが自分で扉を開けてしまうといったリスクに注意しなければなりません。扉付近での思わぬ事故や怪我を防ぐ方法のひとつとして、引き戸への鍵の後付けの需要があります。この記事では、引き戸に後付けできる鍵の種類や選び方、取り付け手順をご紹介します。
◎引き戸の種類と特徴
引き戸とは、真横に動かして開閉する仕組みの戸であり、日本においては古くから襖や障子のように建具として使われてきました。引き戸は、日本家屋の玄関扉として用いられる場合が多く、洋風の住宅でも屋内の間仕切りや洗面所の扉として部分的に使われます。引き戸は、その構造から扉の前に人がいる状態で開閉してもぶつかりません。狭い廊下でも使え玄関スペースを広くとれ、内側で寄りかかるように人が倒れても開閉できるため、事故の際に助けやすい構造になっています。扉を開く際に後ろに下がる必要がなく、レバーハンドル錠のようにドアノブを下げる必要がありません。そのため、車いすやベビーカーでも利用しやすく、買い物で手が塞がっていても楽に開閉が可能です。ドアストッパーなしでも開閉の具合を調整できるため、換気を容易に行える点もメリットです。引き戸は、開閉の仕方によって「片引き戸」「引き込み戸」「引き違い戸」「引き分け戸」の4種類に分かれます。室内で最も一般的な片引き戸は、壁の奥または手前に沿って、戸が左右へ移動して開く仕組みの引き戸で、複数枚の戸が連動するタイプも存在します。引き込み箇所が外部に露出しているため、人や荷物を巻き込まないように注意が必要です。雨戸に代表される引き込み戸は、戸を壁のなかに滑り込ませる分、すっきりとした見た目で壁を自由に使える点がメリットです。ただし、戸の収納部分である戸袋の掃除に手間がかかり、引き戸自体に立体物をつけられません。襖や押入れ、玄関で一般的な引き違い戸は、右または左から2つの戸が近づくように開閉する引き戸です。天井と床への複数の溝と大きな開口部が必要ですが、壁への引き込みスペースがいらない点がメリットです。2つの戸が離れていくようにして開く引き分け戸は、両開き戸ともいい、間仕切りなどに使われます。両側に引き込み部分が必要なため、左右の壁が使えない点に注意が必要です。引き戸の開閉の仕組みは、レール式と上吊り式の2つに分かれています。押入れや襖にも採用されているレール式の引き戸は、床のレール上でスライドさせて開閉する仕組みです。レール部分にホコリがたまると動きが悪くなるため、長期間使用するには、定期的なメンテナンスが大切です。壁の上や天井にあるレールから戸を吊り下げる上吊り式の引き戸は、レールがない分掃除が容易で、車椅子が通りやすくなっています。

◎引き戸の鍵を狙った犯罪手口
引き戸は、横方向のシンプルな動きで開閉する分、誰でも容易に操作が可能です。しかし操作が容易な反面、小さな子どもが誤って風呂場に近づいたり、猫が仕事部屋に何度も入ってしまったりといった問題が生じます。盗難対策やプライバシーの観点から、シェアハウスにおいても引き戸への鍵の設置は重要です。ガラス部分が多い、密着性が低いという特徴を持つ引き戸は、屋外からの侵入犯に狙われやすくなっています。玄関などの引き戸の多くには、採光や意匠面から表面にガラスが使われているため、ガラス破りによる不正侵入に注意が必要です。ガラス破りとは、ドライバーなどでガラスを割り隙間から手を入れ、扉の鍵を操作する手口です。引き戸の鍵の多くには、室内側のつまみに防犯機能が施されており、ストッパーをつまみながら上げなければロック解除されない製品などが存在します。ガラス破り対策には、専用鍵で操作しなければ内側のつまみが空回りする鍵の後付け、外から操作しにくい高い位置への鍵追加、防犯ガラスや防犯フィルムの施工などの対策があげられます。引き戸は、バールなどで戸と壁の隙間を広げて侵入する、こじ開けの被害にも遭いやすい構造です。引き戸には滑らかにスライドさせるために、戸と戸の間にチリと呼ばれる隙間があるため、開き戸に比べ戸と壁の密着度が高くありません。しかし、引き戸は横に開く構造上、開き戸のようにガードプレートを使った対策が難しいため、鍵の後付けといった対策が重要です。引き戸についた鍵穴を直接破壊する侵入手口もあります。対策としては暗証番号の電子錠を設置や、物理攻撃への抵抗時間を示す耐鍵穴壊し性能の高い鍵の採用が有効です。現在の鍵にプラスして引き戸に鍵を後付けすれば、警察庁も推奨するワンドア・ツーロックを実現でき、ピッキング犯への威嚇にもなります。ワンドア・ツーロック以外のこじ開けやピッキング対策には、センサーライトやアラームを周辺に設置する方法があります。

◎引き戸に後付けできる鍵の種類
戸の構造が開き戸と大きく異なる引き戸には、錠に独自の特徴が存在します。前後ではなく左右に動く引き戸では、四角のカンヌキではなく、鎌のような形の金具が上に引っかかることで施錠されます。一般的に引き戸で使われる錠の室外側には鍵穴があり、室内側にはスライド式などのつまみがあります。引戸の錠の場合、錠ケース本体と鍵穴部分が一体になっている場合が多いため、鍵穴の防犯性能を上げたい場合には錠前ごと交換するか、補助錠を追加して対応してください。また、戸のどの位置に取り付けるかによって鍵の種類が異なるのが、引き戸の錠の特徴です。引戸に後付けできる鍵は、「召し合わせ錠」「戸先錠(とさきじょう)」「簡易錠」の3種類です。障子や襖、サッシなどの引違い戸を閉じた際の重なり部分を召し合わせと呼ぶことから、戸を閉めた際の重なりにある鍵を「召し合わせ錠」といいます。手前の戸と奥の戸のそれぞれに錠前を設置するのが特徴で、引き違い戸に後付けできることから引き違い戸錠とも呼ばれています。召し合わせ錠は、挿入した鍵と同じ向きにカンヌキが飛び出し、手前の戸と奥の戸を連結することで、施錠する仕組みです。戸の隙間(チリ)が大きくなる、戸の位置が下がるなどすると、奥と手前の錠の位置がずれ、うまく施解錠できません。ずれの原因にあげられるのは、経年劣化による扉下の戸車の擦り減り、戸車自体の破損、レールのネジ緩みによる溝の歪みなどです。ずれ対策として、召し合わせ錠には錠の中心に小さな穴があいており、穴に細長い針金のような補助具を通して錠の位置をそろえられます。召し合わせ錠には、万能引き戸錠、プッシュ栓錠、内締まり錠の3つの形式が存在します。万能引き戸錠は万能型ともいわれ、近代では一般的な召し合わせ錠です。外から鍵を操作するか屋内からつまみを動かすと、鎌のボルトが飛び出し、錠前同士がつながって戸が動かなくなる仕組みです。プッシュ栓錠が外からのみ、内締まり錠が内側からのみ施錠できるタイプであり、古い引き戸で見られる錠です。戸先錠(とさきじょう)は、玄関や室内の引き戸の、取っ手付近に後付けできる鍵です。開き戸と同じように、カンヌキは鍵挿入と垂直方向に飛び出し、枠のストライクに引っ掛かることで固定されます。室内側のつまみの形状は、上下スライド式、上下に動かすレバー式、開き戸のように回転するサムターン式の3つです。戸先錠を設置の仕方でわけると、戸のなかに錠ケースを彫り込む彫り込み式か、引き戸の室内側表面に固定する面付け式の2タイプがあります。後付けが容易な面付け式はネジで固定するため、扉に彫り込むほどの厚みがない場合にも設置できる長所を持ちます。面付け式では、鎌が飛び出て戸枠側の受け部に引っかかると施錠されますが、外から錠本体が見えないため、こじ開けがしにくい構造です。戸先錠の錠ケースは、細長い筒のような形のチューブラ鎌錠か、箱型のケース鎌錠に分かれます。チューブラ鎌錠は、四角ではなく細長いチューブ形なので引き戸内に埋め込む面積が少ないため、小さな切り欠き穴で後付けが可能です。簡易錠は、ネジや粘着テープで設置する鍵を指し、引き戸の取っ手とその向かい側の壁をネジで固定したり、引き戸表面にテープで設置したりして設置します。つまみをスライドしたり金具を引っ掛けたりするとストッパーがかかる仕組みで、ロックのみ、あるいは施錠も可能な製品があります。ただし、簡易錠は取り付ける側からしか操作ができないため、片側からのみの施錠になる点に注意してください。賃貸物件でも粘着テープの簡易錠であれば、戸に傷をつけずにすみますが、召し合わせ錠や戸先錠に比べると取れやすいため、一般的にメインではなく補助錠の用途で使われます。
◎引き戸に後付けする鍵の選び方
引き戸に後付けする鍵は、用途や場所にあわせて選択することが大切です。防犯を強化したい場合には、シリンダー(鍵穴)のタイプも確認しておきましょう。シリンダーのタイプは、ギザギザした形状と、クレーターのような凸凹した穴がついたものの2種類に分けられます。ギザギザした形状の鍵はディスクシリンダーやピンシリンダーと呼びます。古い内部構造の製品は防犯性があまり高くありませんが、古い住宅では使われているケースがあります。凸凹の穴のあるタイプはディンプルキーと呼ばれ、ピッキング対策として推奨される製品です。引き戸に後付けする鍵を選ぶ際は、ピッキングへの抵抗時間を示す耐ピッキング性能の高い製品や、紛失しても簡単に複製ができない登録制のディンプルキーを選ぶとよいでしょう。引き戸に鍵を後付けする際は、室内での出入りを防ぐ目的であればロックのみの製品、施錠も必要な際には戸先錠というように目的を明らかにすることが大切です。留守時などの防犯であれば外からも施錠できる製品、プライベートの確保が目的であれば引き戸の内側からも施錠できる製品を選びましょう。大がかかりな配線工事が不要な乾電池式の電子錠を採用すると、手軽にオートロック機能などを使用でき利便性が向上します。暗証番号などのキーレスタイプの電子錠では、子鍵を持ち歩く必要がありません。また、電気を使わない機械式は、水濡れや停電時でも安心して使用できるメリットがあります。

◎引き戸に鍵を後付けする手順
召し合わせ錠や戸先錠といった本格的な鍵を引き戸に設置するには、穴あけ加工が必要です。穴あけを伴う取り付けには専門的な知識や技術が必要なため、無理をせず作業に慣れたプロの業者に任せると安心です。引き戸に鍵を後付けする際の作業は大きく分けて、採寸、切り欠き穴の加工、取り付けの流れで進められます。召し合わせ錠は、室外側の錠ケース台座である外部化粧座と、室内側の錠ケース台座である内部化粧座を設置する厚みやスペースが戸にあるかをチェックします。必要なサイズが計測できたら、2枚の戸を閉じた際に重なる部分にそれぞれ切り欠き穴を作り、製品をはめ込んでいきます。召し合わせ錠は、室内用と室外用の錠前がセットになって梱包されているケースが多いですが、ビスを外すと化粧座と錠ケースに分解可能です。まずは、屋内方向から錠ケースを室外側の引き戸にはめ込みます。戸の厚みと錠ケースの分厚さが一致しない際は、錠ケースと引き戸の間にスペーサーを入れて厚みを調整可能です。次に、角芯を錠ケースの角穴に入れるようにしながら化粧座を外からはめ、屋内から錠ケースの上下をビスで固定します。外から室内側の引き戸に錠ケースをはめ、反対側から化粧座をはめてビスで固定しますが、この際に化粧座は少しだけ動く程度に仮止めしておくのがポイントです。最後に、互い違いになっている引き戸を閉めて、2つの化粧座の位置がぴったりと重なるようにします。位置が重なったのを確認できたら、屋内側から付属のセットピンを内部化粧座にある穴に入れ、外部化粧座の穴までしっかり通し、そのまま仮止めしていた内部化粧座のビスを完全に固定します。戸先錠を引き戸に後付けする際も、召し合わせ錠同様にまずは正確に採寸します。戸先錠で測る項目は、鍵穴の中心から扉の端まで、錠ケースのフロントカバーや化粧座の縦横、引き戸自体の厚みです。戸に十分な厚みやスペースがとれそうであれば、引き戸に切り欠き穴を彫り込みます。戸の側面の穴から錠ケース本体を挿入し、戸の外側に外部化粧座、内側には内部化粧座を設置し、ビスで固定します。錠ケースと向かい合う位置のドア枠にも、錠ケースから飛び出た鎌が適切に引っかかるように切り欠き穴を作ります。召し合わせ錠、戸先錠ともに、作業後にスムーズに引き戸が動くか確認し、問題がなければ工事完了となります。
◎まとめ
引き戸への鍵の後付けは、子どもやペットへの対策としてはもちろん、防犯性や利便性の向上につながります。カギ舎では、鍵の専門知識を持ったスタッフがご要望を丁寧にお伺いします。見積もりは無料で承っていますので、引き戸への鍵の後付けを検討の際は、お気軽に当社へお問い合わせください。