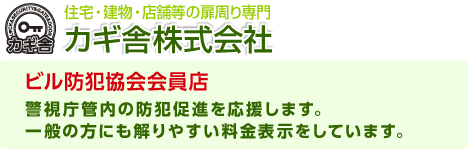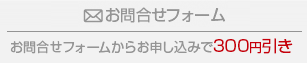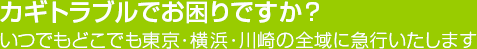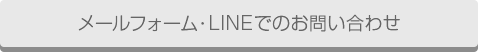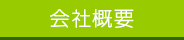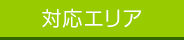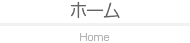木製ドアのトラブルと修理時に見直すこと
木製ドアは温かみのある風合いが特徴的ですが、長期間に渡り使い続けていると、ドアが開きにくいなどさまざまな不具合が生じて修理が必要になることがあります。この記事では、木製ドアの種類や材質、耐用年数や修理が必要になるトラブル、修理の際に見直すと良いことなどご紹介します。
◎木製ドアの種類
室内に設置できる木製ドアの種類としては、化粧シート仕上げや突き板仕上げ、無垢材などがあげられます。木製ドアに使用されている化粧シートとは、樹脂フィルムや紙製のシートに木目柄を印刷したもののことを言います。芯材を軸に合板を組み合わせ木目の化粧シートを張り付けたのが化粧シート仕上げと呼ばれる木製ドアです。最近では技術の向上により、まるで本物の木材のような木目の表面加工を施されている化粧シート仕上げの木製ドアも増えており、キッチンやリビングなどの室内ドアのほかにも、フローリングや階段、手すり部分にも採用されています。化粧シート仕上げの木製ドアはデザインが豊富で傷がつきにくくなっています。表面は防水加工が施されているため、汚れや水滴が拭き取りやすく、手入れが簡単で耐水性や抗菌性仕様の製品があることもメリットです。木製ドアの突き板仕上げとは、突き板をシナ材やナラ材の合板やMDF、つまり中質繊維板などの基材に張り塗装して仕上げた木製ドアのことを言います。天然木化粧合板とも呼ばれる突き板は、杉やヒノキ、ウォールナットなどの木材を薄くスライスした板です。突き板は反りに強いため、室内ドアだけではなくキッチンの扉や家具の表面化粧材としても採用されています。浮き造り加工と呼ばれる、表面の木目の固い部分だけを浮き出すように残す細工を施した製品もあり、木目の美しさや温かみをいっそう強く感じることができます。無垢材の木製ドアとは、丸太から切り出した自然の木をそのまま使用しています。無垢材は丸太からの切り抜き方次第で木目が変わるため、同じ木目の無垢材はほかには存在せず、木が持つ本来の魅力を存分に感じることができます。無垢材は時間の経過とともに色味やツヤが深みを増しながら変化するのもその特徴のひとつです。自然木を材料としている無垢材には湿度をコントロールする性質が備わっています。湿度が高い夏場には湿気を吸い、湿度が低い冬には放湿して室内の湿度を一定に保つため、無垢材の木製ドアを室内に設置すれば一年中気持ちよく快適に過ごせます。無垢材は空気を多く含んでおりその空気が断熱材と同様の役割を果たすため、冷気が伝わりにくく部屋が冷えるのを防ぐ効果が期待できます。また、もともと木に含まれている精油が残っているため、ダニやカビなどの繁殖抑制にもつながります。

◎木製ドアの材質
木製ドアに使われている材質もさまざまな種類があります。木製ドアによく使用される国産材としては杉やヒノキ、ヒバなどがあげられます。全国で植林されている杉は日本の気候に適している植物なので、私達にとって最も身近な木材であると言えるでしょう。杉はまっすぐで柔らかく加工がしやすいため、昔から木製ドアだけでなく天井板や家具などの建材として幅広く利用されてきました。木材のなかでも比較的安価で入手しやすく独特の清々しい香りを放ち、抗菌や防腐効果があるのも杉の大きな特徴です。特に奈良県吉野の林から採れる吉野杉は良質の木材として日本三大美林のひとつに数えられ広く知られています。ヒノキは日本で1番軽い材質と言われていることから、室内ドアやタンスなどの家具に使用されています。自然な色味でフローリングとの相性もよく、木製ドアは時間が経過するとともに色合いが変化し白っぽい色味から味のあるアメ色になっていきます。ヒノキは熱伝導率が低いため断熱効果や湿度を調整する効果も期待できます。材質が柔らかく香りのよい木材としても知られていますが、これはヒノキチオールという成分が含まれているためです。ヒノキの持つ独特の芳香は気持ちをリラックスさせる効果もあり、芳香剤やアロマオイルなど商品化もされています。香りだけではなく抗菌効果もあるため抗ウィルス作用も期待でき、強度と耐久性もありながら加工が容易でもあることから、奈良県にある世界最古の木造建築物である法隆寺にも採用されています。針葉樹であるヒバは別名アスナロと呼ばれています。杉やヒノキと同様に住宅の建材として使用されることが多いヒバには、香り成分ヒノキチオールがヒノキよりも多く含まれています。香りが良いだけではなくヒバには抗菌や防虫効果、防腐効果や消臭・脱臭効果もあるため匂いのこもりやすいトイレやキッチンなどの木製ドアにも適しています。日本では、青森県の青森ヒバや石川県の能登ヒバが特に有名です。輸入材として木製ドアに使用されている木材には、オーク材やウォールナット材、パイン材などがあります。オークはブナ科の広葉樹の一種であり日本では一般的にナラの木材のことをオーク材と呼んでいます。木製ドアのほかにもアンティーク家具などに使用されるオーク材は、直線的で平行な木目の柾目(まさめ)や力強い山型の曲線模様の板目(いため)などが特徴的です。まれに虎斑(とらふ)と呼ばれる虎の模様のような美しい木目が現れることがあり、耐久性や耐水性が高く加工しやすくなっています。とても堅く重量があり傷がつきにくいのが特徴で、椅子やテーブルなどにも最適な材質です。木製ドアに採用されているオーク材にはポリフェノールの一種であるタンニンという成分が含まれているため防虫効果もあります。くるみ科の植物であるウォールナットは木肌が美しくツヤがあるのが特徴で衝撃に強く丈夫なため、ライフル銃の銃身を支える重要な部分である銃床にも使われています一般的に木製ドアや家具などに使用されるウォールナットとはブラックウォールナットのことを指していい、世界三大銘木のひとつに数えられています。パイン材は日本でもよく知られている針葉樹である松の木から切り出された木材です。50種類以上もある松のなかでもイエローパイン、ホワイトパイン、ポンデロッサパインなどが家具や木製ドアに使用されています。白色から薄黄色の色味と節が多いのが特徴的なパイン材には油分が多く含まれているため、年月が経つにつれて茶色がかったアメ色へと色味が変わり独特な味わいを楽しめます。木肌が柔らかく加工がしやすい上温かみのある肌触りがあり、パイン材にはリラックス効果をもたらすフィトンチッドと呼ばれる成分が含まれています。そのため木製ドアに使用すれば木の香りにより癒し効果が得られ、加えて消臭や脱臭、抗菌や防虫効果も期待できます。輸入材のなかでもパイン材は流通量が多いため比較的価格が安価で、木製ドアの修理や交換の際に採用すればコストが抑えられるメリットがあります。
◎木製ドアの特性
アルミ製やスチール製のドアは1度傷がつくと修理が困難なことが多いため、新しい木製ドアに交換しなければならない場合があります。しかし木製ドアであれば、大きな傷がついたり穴が空いても修理が可能なことが多く、交換にかかるコストを抑えることができます。木材は熱伝導率が低いため、外の気温に左右されにくい環境を作るのに適しています。木を材料として作られた木製ドアは高い断熱性を持っているため、部屋の扉として利用すれば夏には外気の侵入を防ぎ冬には外気の侵入をしっかり防いでくれ、室内を快適で過ごしやすい環境に保ってくれます。熱伝導率が低いことは火を通しにくい防火性にもつながります。木材には空気が多く含まれており、もともと空気は熱を伝えにくい成分であるため木材の温度は上昇しにくくなっています。そのため万が一火災が発生して炎に包まれても、木製ドアは熱くなるまで時間がかかるため延焼を防いでくれる場合があります。このように木製ドアはメリットが多いのですが、耐用年数があり寿命が訪れる前でも修理が必要になるケースがあります。
◎木製ドアの耐用年数
木製ドアの耐用年数ですが、木製ドア本体は約20年、木製ドア枠は約10~15年、 木製ドアのドアノブなどの金具は約5~10年となっており、それ以上経過すると修理や交換が必要になることがあります。木製ドアを少しでも長く使いたい場合には日頃からのメンテナンスが大切です。耐用年数を過ぎても無理をして使い続けると、耐久性や気密性が低下してしまい本来の目的を果たせなくなってしまうため、不具合を感じたら早めに修理や交換を行うようにしましょう。木製ドア本体の修理のほかにも、前後に扉を開く開き戸を壁と固定するために使用される蝶番やドアの開閉速度をコントロールするドアクローザー、ドアが勝手に開かないように固定する役割を担うラッチなどの部品などの修理が必要になることがあります。特に前後に開く引き戸をスムーズに動かすために下部に設置されている戸車は、木製ドアの重さを支えているためより早く劣化してしまい修理が必要になる傾向にあります。このように木製ドアが耐用年数に至らなくてもさまざまなトラブルに見舞われ修理を行わなければならないことがあります。

◎木製ドアによく見られるトラブル
日々使い続けている木製ドアは、徐々に開け閉めがスムーズにできなくなり、修理が必要になることがあります。ドアが閉まらない原因としては、蝶番のネジの緩みや変形、ドアノブの故障やラッチの滑りが悪くなること、木製ドアの腐食やドア枠が歪むことなどが挙げられます。開き戸タイプの木製ドアを開閉する際の軸となる蝶番は、ドアの縦枠にネジにより取り付けられていますが、木製ドアを開閉するたびに長い年月をかけて徐々に緩んだり劣化により変形することがあります。そうすると木製ドアを閉めようとした際に強い力を入れないと閉まらなくなったり開けづらくなるため蝶番を修理しなければなりません。木製ドアは、ドアノブやドアレバーを操作することでラッチがドア枠にあるストライクに入り、ドアが閉まる仕組みとなっています。ドアノブの故障によりラッチが動かなくなりトイレに閉じ込められたというトラブルも実際に起こっているため、ドアノブを回した際に異音がしたり緩んでいて回しにくいなどの不具合を感じたらできるだけ迅速に扉業者に修理を依頼するようにしましょう。経年劣化した木製のドアは気づかないうちに湿気などにより端から腐食していくため、修理しなければならない状態に陥っている場合があります。 ドア枠が歪んでいたり、地震の影響により建物自体が歪み木製ドアが開かない場合には、扉業者に修理を依頼しましょう。化粧シート仕上げや突き板仕上げのドアの多くはフラッシュ構造で作られているため、衝撃により木製ドアに穴が開いてしまい修理しなければならないことがあります。フラッシュ構造とは木材で枠を組み、両側に化粧板などを貼って仕上げたドアのことを言います。フラッシュ構造を採用したフラッシュドアは大量生産できるためコストを低く抑えることができるのがメリットですが、板と板との間に空洞があることにより衝撃が加わると穴が空く恐れがあり扉業者による修理が必要となります。毎日何度も開閉を繰り返す室内の木製ドアは、修理を伴うトラブルをできるだけ避けるためにも、日常生活の中で定期的に掃除するなどメンテナンスを行うことが修理や交換を防ぐことにもつながります。
◎木製ドアのメンテナンス
木製ドアの掃除をする際には表面のホコリを払い乾いた布で汚れを拭き取ってください。ドアノブやレバーハンドルの手垢などの汚れが気になる場合は、水で薄めた中性洗剤に布を浸し固く絞ってから拭き取り、その後水拭きしましょう。木製ドアの引き戸のレールにゴミやホコリが溜まると、ドアの下部にある戸車が動かなくなり引き戸が開閉しづらくなるため、レールの溝に溜まったゴミはほうきでこまめ掃き出したり掃除機で吸い取るようにしてください。どんなに普段から気をつけてメンテナンスをしていても経年劣化に伴い修理が必要になるケースが増えてきます。故障したまま調子の悪い木製ドアを使い続けていると突然ドアが外れてケガをしたり、無理にドアを閉めようとして指を挟むなどの事故につながることもあるため、そうなる前に扉業者に修理を依頼するようにしましょう。木製ドアの修理を扉業者に依頼する際に、見直すと良いことがいくつかあります。

◎木製ドアを修理する際に見直すこと
木製ドアの修理を行う場合、これまで開き戸だった扉を引き戸に替えバリアフリー化するのもひとつの方法です。バリアフリーとは、介護を受ける側だけではなく、介護をする側にも配慮された設計のことを言います。開き戸より間口の広い引き戸にすれば開口部が広く取れるため、ご高齢の方や車椅子を使用している方、サポートする方の移動もスムーズに行えます。引き戸を軽い木製ドアにすれば力の弱い小さなお子さんでも開けやすくなり使い心地がよくなります。リビングとほかの部屋を隔てていた木製の引き戸の枚数を増やし2枚引き違い戸から3枚引違い戸に変え、さらに2つの部屋の間にあった段差をなくせば間口が広くなりバリアフリー化を実現できるだけでなく部屋全体も広く明るい印象になります。木製ドアの経年劣化を放置して修理を行わないと断熱性が低下します。そうなると室内でも温度差が生まれ、脳梗塞などを引き起こすヒートショックの引き金になる可能性が少なからずあります。ヒートショックとは急激な気温の変化に伴い血圧が上下し心臓や血管などの疾患が起こることを言います。木製ドアの修理をきっかけとして室内ドアを新しいドアに交換すれば、部屋の断熱性がアップし外との温度差が大きくなる時期にも室内で快適に過ごせるようになります。ご高齢の方ほどヒートショックを発症するリスクが高いと言われているため、木製ドアの修理の際には、バリアフリー化に加えて断熱性の向上も検討しましょう。
◎まとめ
木製ドアは、適切なメンテナンスを行えば長く使い続けることができるほか、修理をきっかけとしてライフスタイルに合わせてバリアフリー化することも可能です。カギの専門業者であるカギ舎では、木製ドアの修理の依頼はもちろん、カギに関する修理や交換などあらゆる相談に年中無休24時間対応しています。木製ドアの修理やカギに関することでお困りの方はカギ舎へご連絡ください。