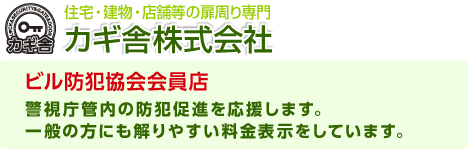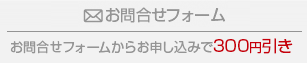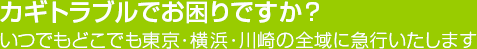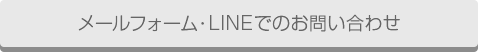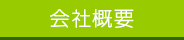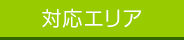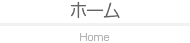窃盗被害に遭わないために!鍵・扉の防犯対策豆知識
日頃、何気なく開け閉めしている玄関の鍵や扉ですが、住宅の窃盗被害のうち半数以上は、空き巣によって玄関から侵入されています。自然災害や事故の場合と同様に、犯罪被害に遭うリスクを減らすには知識と備えが必要です。この記事では、住宅の侵入窃盗の傾向や犯人側の心理、効果的な防犯対策の方法や鍵のメンテナンスなどについてご紹介します。
◎住宅の侵入窃盗犯罪の傾向
警察庁が発表したデータによると、2021年東京都では侵入窃盗が2,254件発生しており、1日あたり約6件に相当します。うち907件は住宅で発生しており、1日あたり2.5件に相当します。出入り口からの侵入は56.4%、表出入口からの侵入は52.4%を占めています。被害原因は「無施錠」「「錠破り」「錠あけ」「鍵の複製」「合鍵を入手」など、鍵や錠に関係するものが圧倒的に多い傾向があります。住宅窃盗被害の多い時期は、行楽シーズンで留守にしがちな春や秋、年末年始などがあげられます。時期に関係ないところでは、引っ越しをして1~2か月後、バタバタしていたのが落ち着いて緊張が緩む時期も狙われやすい傾向にあります。侵入に関しては、5分で鍵を開けられなかったら7割が諦めるというデータがあります。簡単に鍵や扉が開けられず時間がかかることで犯罪の抑止につながります。そのため、5分という時間は鍵や錠、扉やガラスなどを防犯建物部品認定(CP認定)する性能試験で、耐久時間の基準になっています。泥棒は犯行前に下見をするケースが多いとされています。通りは人目が少ないかどうか、逃げやすいか、ターゲットの家や周囲の家は留守にしがちか、どんなタイプの鍵や扉かなどを見ています。いつ空き巣に見られているかわからないため、鍵をポストや植木鉢の下など玄関の周辺に隠している場合は十分に注意しましょう。また植栽で玄関扉の見通しが悪くならないよう、手入れしておきましょう。侵入窃盗を諦める理由のうち3割以上が、「近隣の人に声をかけられた」というデータがあります。(参考:(財)都市防犯研究センター)そのため、隣近所との連携が防犯対策になります。人感センサーと連動してフラッシュする玄関灯やカメラなどの防犯設備などが有効です。長期間不在にする時は、新聞や郵便物を止めるなどして留守を悟られない配慮も必要になります。鍵や錠、扉を破る方法については、手口がほぼ明らかにされています。被害に遭わないためにも、鍵や錠、扉の知識を得て、具体的な防犯対策を知っておくことが大切です。

◎鍵の防犯対策豆知識
シリンダー錠は、玄関ドアの鍵として多くの家で使われています。ディスクシリンダーは、鍵を差すと内部のタンブラーが動いて鍵を回すことができる構造です。ピッキング犯罪にはきわめて弱いため鍵交換を検討しましょう。ロータリーディスクシリンダーはディスクシリンダーを改良した鍵です。鍵を差し込むと複数枚あるタンブラーが回転して、すべてが正しい位置に揃ったとき、ロッキングバーが解除され鍵を回すことができます。以前と比較してピッキングに強い構造になっています。ピンシリンダーは、鍵を差し込むとギザギザした鍵山がシリンダー内のピンを押し上げて解錠する構造です。ピッキングと呼ばれる、鍵穴に特殊な工具を入れて解錠する犯罪手口に弱く、バンピングと呼ばれる犯罪手口にも弱いので、鍵交換が推奨されます。ディンプルシリンダーは鍵の表面に円や長穴状のくぼみが掘られています。ピンが1列しかないピンシリンダーに対し、複数列にして複雑化することでピッキングに強い特徴があります。しかし単純な配列のディンプルシリンダーは、ピッキングやバンピング被害に遭う可能性があります。また鍵に刻印された番号で複製ができる点にも注意しましょう。最近では、メーカーが鍵番号を管理し、本人確認書類とパスワードを明示しないと鍵を複製できないタイプも出ています。レバータンブラー錠やウォード錠などは昔から使われている簡易的な鍵で、防犯効果が弱いため鍵交換やCP認定された補助錠の設置が必須です。プッシュプル錠はハンドルの押し引きでラッチの操作ができるので、力の弱いご高齢の方や子どもでも扉の開閉がスムーズにできます。サムターンの複数付いたタイプが防犯上有効です。インテグラル錠、チューブラ錠は室内で鍵の必要な所に使われています。ほかにも鍵に埋め込まれた磁石がシリンダー内の磁気を帯びたパーツを動かして解錠するマグネットタンブラーシリンダー錠や、波型のうねりが鍵の表面に刻まれ、鍵山がないウェーブキーシリンダー錠があり、いずれもピッキングに強い特徴があります。ピッキングに弱い鍵の場合は、ピッキングアラームを設置するのも1つの方法です。工具を操作するときに発生する鍵穴への振動を検知すると、大音量の警報音が鳴る仕組みとなっています。サムターン回しは、ドアスコープや郵便受けを壊す、扉にドリルで穴を開ける、扉と枠の隙間を利用するなどして特殊な金属棒を扉の内側に入れ、サムターンに引掛けて回して解錠する手口です。対策として、サムターンにカバーを付けたり、スイッチ付きや本体を押し込んで回す2アクション方式、使う時だけ取り付ける脱着式や、サムターン回しが片側だけを引っ張るのに対し両方向から力を加えないと回らない偏荷重式、卵型で引っ掛かりをなくすなどの方法があります。樹脂製のサムターンカバーはDIYでも容易に取付けできますが、加熱によって溶かされてしまう可能性があります。カム送りはシリンダーを扉から浮かせて隙間から工具を入れ、デッドロックを動かして解錠する手口です。国内メーカー4社、15品番がこの方法で解錠できると警察庁から公表されていることから、該当製品を使っている場合は交換をしましょう。ラッチ付近のプレートの刻印でメーカーと品番を確認することができます。バンピングは、特定のメーカー、品番に合ったバンピングキーを使って解錠する手口です。ピンシリンダーや単純な配列のディンプルシリンダーが対象になります。インプレッションは、加工前のブランクキーを鍵穴に差して揺動させ、ついた傷の状態から鍵山を推測してヤスリ等で削り、合鍵を作る手口です。技術と経験が必要ですが、インターネット上で手法が公開されており、必要な工具や部材も入手できるため、鍵をCP認定する際の試験項目にあげられています。ドリリングは、ドリルやホールソーで錠を破壊する手口です。シリンダー構成部品に焼き入れ処理材や超硬部材を用いたり、CP認定を受けた補助錠を扉に取付けて対策します。デッドボルトをドアの隙間からノコギリで切断する手口に対しても、デッドボルトを焼き入れ処理材にすることが対策になります。シリンダーを扉からもぎ取る手口には、CP認定された補助錠の扉への取付けが効果的です。ほかには、シリンダープラグの引き抜きや捻りもあり、こうした大きな外力による手口は扉にも振動が相当伝わるので、振動検知タイプの防犯センサーの取付けも有効です。全般的にワンドアツーロックは非常に効果のある対策手法で、国土交通省の「防犯設計指針」でも、補助錠の取り付けは推奨されています。CP認定錠は、最近の侵入手口に応じた厳しい防犯性能試験をクリアした錠で、防犯対策部材を選ぶ際の基準となります。また自治体によっては、CP認定錠の取付けや交換、ガラスへの防犯フィルムの貼付けなど、住まいの防犯対策費用の一部を補助してくれる制度があります。

◎扉の防犯対策豆知識
玄関扉には、主に開き戸と引き戸が使われています。開き戸には、片開きドア、片開き扉に開閉可能な子扉を組み合わせた親子ドア、袖に固定式の窓がある片袖ドア、両側の袖に固定窓がある両袖ドア、左右2枚の扉が開く両開きドアといった種類があります。室外から向かって左に開き戸の丁番の軸があると左勝手、右なら右勝手と呼びます。室内側に開き戸が開くと内開き、室外側だと外開きです。引き戸では、片側だけの片引き戸、両側扉が開いて収納される両引き戸、扉を開けた時に壁に収納されて見た目がスッキリする引き込み戸、片側扉を反対側に重なるようにスライドすることで開閉する引き違い戸などがあります。扉の材質は木製と金属製が多いですが、金属製でもアルミ、スチール、ステンレスなどが多く使われています。なかでもアルミは軽量で耐久性も高く、一般的によく使われています。扉に対する侵入手口はいくつかあげられます。まずこじ開けは、開き戸の扉と枠の間にバールを入れて枠を変形させ、錠のデッドロックを露出させて解錠する手口です。警視庁の公表している実際の犯行動画によれば、作業時間は数分とされています。対策としては、バールが入らないようにガードプレートや煙返しを取り付ける、デッドロックの形状を鎌付きにして容易に外れないようにします。デッドロックが扉の室内側に取付けられる面付け錠であれば、こじ開けの心配は不要です。引き戸では、2枚の扉が重なる部分の召し合わせ錠や、枠側の戸先錠などが使われていますが、扉同士の隙間からの解錠レバー操作、こじ破りなどの危険があります。ディンプルキーの採用や、隙間にプロテクトガードを設ける、フックを鎌付きにして外力によるこじ破りを防ぐことが大切です。MIWAやアルファといったメーカーからは、防犯性能の高い引き戸錠が販売されています。扉の部分的にガラスを使い、採光やデザイン上のアクセントにしている玄関扉や、まれですが全体がガラス製の玄関扉があります。ガラスの部分がある扉では、ガラスを割ったところから手や工具でサムターンを回して解錠する犯行手口があります。こじ破りは、ガラスと枠の間をマイナスドライバーなどの工具でこじるように力を加え、ひびを入れてから静かに割っていく手口です。打ち破りはハンマーなどの工具でガラスを叩き割る手段になります。焼き破りはバーナーでガラスを熱してから水で急冷するなど熱衝撃を加えて割る手口で、短時間で静かに割ることができ、道具もホームセンターなどで入手できるため、近年増加しています。対策としては防犯ガラスの使用があげられます。防犯ガラスは、2枚の板ガラスの間に強度の高い中間膜やポリカーボネート板などを挟んだ構造で、外力で容易に割れず、耐熱強化ガラスを使って焼き破りを防ぐことができます。犯人も防犯ガラスであると分かれば侵入を避ける傾向があり、犯罪抑止にもつながります。既存のガラスに強度や耐熱性の高い防犯フィルムを貼る方法も有効です。施工は、防犯フィルム施工技能者の認定を受けた工事業者に依頼しましょう。日本ウインドウ・フィルム工業会では、有資格者が貼付したCP認定防犯フィルムに、防犯建物部品の証であるCPマークを貼付することと規定しています。網入り板ガラスは、一見防犯性能が高そうに見えますが、金属線が入っていることからフロート板ガラスより割れやすく、割れたガラスが脱落しないので破壊音も小さく、逆に狙われやすいケースもあります。

◎鍵や錠のメンテナンス
家族の安全や財産を守るためには、普段から鍵や錠のメンテナンスは欠かせません。鍵や錠は手入れせずに長期間使っていると、ある日突然鍵が差さらない、引っ掛かりがある、回らないなどの不具合が起きることがあります。鍵山やディンプル、ウェーブキーの溝などが摩耗、変形していないか、ときどき目で見て確認しましょう。マグネットキーは、鍵側に埋め込まれた磁石が脱落すると解錠できなくなるので注意しましょう。鍵山に付着した汚れやゴミは乾いた布で拭き取り、ディンプルキーは歯ブラシなどでくぼみの汚れを掻き出します。鍵の動きが悪いからといって、鍵穴に油を差したりシリコンスプレーを吹き付けると、ゴミやホコリと共に内部で固着し、故障の原因になりますので注意が必要です。滑りを良くするには、鍵専用の粉末状で速乾性の潤滑剤をスプレーするか、鉛筆の芯で鍵の凹凸をなぞり、黒鉛を付着させてから鍵を出し入れします。MIWA、KABA、GOALなどの鍵メーカーは純正の潤滑スプレーを販売しているので、適合する場合は純正品を使用するのが安心です。使用にあたっては、故障につながる禁止事項もあるので、取扱説明書をよく確認しましょう。錠の耐用年数は日本ロック工業会(JLMA)によって定められていて、電気を使わない一般錠は約10年です。玄関の鍵や錠は防犯上最も重要な場所で構造も精密なので、不具合が改善しない時は安易に自分で分解したりせず、鍵の専門業者に相談しましょう。
◎まとめ
近年では、インターネット上でさまざまな情報を入手し工具や部材も購入できることから、鍵や扉のDIYをする人が増えています。しかし鍵や錠、扉の防犯対策レベルは犯罪手口の巧妙化に準じて上がっていることを忘れてはいけません。
鍵や扉についてトラブルや心配なことがあれば、知識や経験が豊富で最新の防犯事情にも通じたカギ舎へご相談ください。