カギ舎株式会社
■本社
〒151-0063
東京都渋谷区富ヶ谷1-30-10
TEL:03-6454-1241
〒151-0063
東京都渋谷区富ヶ谷1-30-10
TEL:03-6454-1241
■事業所
杉並区和田1-25-3
杉並区和田1-31-3
中野ブロードウェイ422-2
杉並区和田1-25-3
杉並区和田1-31-3
中野ブロードウェイ422-2
東京商工会議所
杉並警察ビル防犯協会所属
杉並警察ビル防犯協会所属

【東京都】
中野区 新宿区 足立区 荒川区 杉並区 板橋区 江戸川区 大田区 葛飾区 江東区 品川区 渋谷区 世田谷区 台東区 中央区 千代田区 墨田区 豊島区 練馬区 文京区 港区 目黒区 北区 西東京市 三鷹市 調布市 武蔵野市 全域
【埼玉県】
和光市、新座市、朝霞市、戸田市、蕨市、川口市
【神奈川県】
横浜市 川崎市 全域
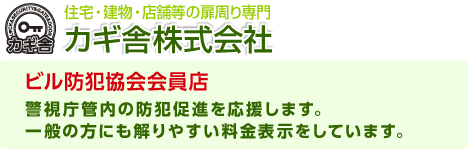
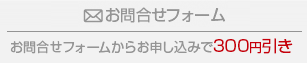

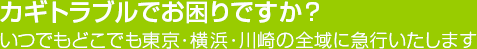

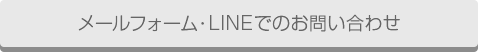
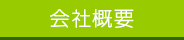
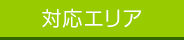
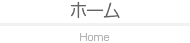




最後に生体認証とは、本人を特定することで解錠が行える仕組みです。バイオメトリクス認証とも呼ばれ、セキュリティ面で高く信頼されています。顔認証や指紋認証、音声認証のほかにも静脈認証や虹彩認証まで、さまざまな生体認証が可能となりました。身体ひとつでドアの開閉がスムーズに行える先進的な方法です。顔認証は、顔を「鍵」として解錠を行うタイプです。顔認証の電気錠を導入する際は、システム上に顔のデータを登録します。ユーザー登録数は少人数のタイプのものから10万人もの顔を登録できるタイプまで幅広く、オフィスなどで多く採用されています。指紋認証は、事前に指紋をシステム上に登録し、所有者を認識することで、解錠を行います。人によって異なる指紋は、何億通りもあるといわれており、他人の指紋で認証されてしまうといったケースはほとんどありません。音声認証はその名の通り、声を使用した解錠方法です。声の模様といわれている声紋を鍵として用いたセキュリティシステムです。短いフレーズ、長いフレーズなどあらかじめ登録した一定の長さの言葉を発して認証を行います。声が枯れてしまったときや、まわりの音に邪魔されて認証ができないというデメリットもあります。静脈認証は、手の甲や手のひらの皮膚の下にある静脈で本人かどうかを認証します。周囲の環境や、持ち物に影響されにくいので、登録者本人以外が解錠することは極めて困難です。最後に虹彩認証とは、目のなかにあるドーナツ状の模様のことを指します。虹彩の模様は、指紋以上に複雑といわれており、100%といってよいほど偽造は困難です。また、虹彩は生涯変わらないともいわれています。そのため、1度登録すれば再登録が不要な点も大きなメリットです。