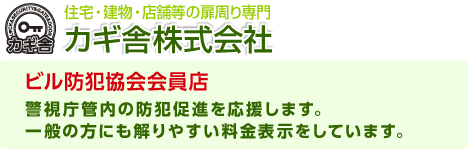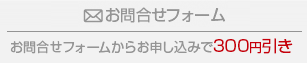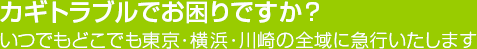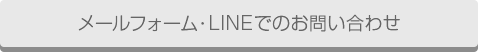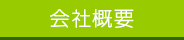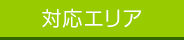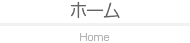自動ドアの構造と鍵の種類
マンションのエントランスやコンビニエンスストアなどの店舗の出入口、ビルやホテル、公共機関など多くの場所で見かける自動ドアは、日常生活のなかで身近な存在となっています。この記事では、自動ドアの種類や構造、自動ドアのカギの種類や電気錠の構造などについて詳しくご紹介します。
◎自動ドアのタイプ
電気の動力により自動で扉の開閉を行うドアのことを自動ドアと言います。人や物などが近づいた際にそれをセンサーが自動で検知し、扉を開いた後再び自動的に閉じる構造となっています。そのため荷物で両手がふさがっている場合や車椅子などで通行する際にもスムーズに通行することができ、特に多くの人が出入りする場所ではなくてはならない存在と言えます。自動ドアは扉が自動で閉まり扉の閉め忘れを防ぐため、エアコンを使用している際には省エネルギー対策にもつながります。同時に、外からの風雨やチリ、ホコリの侵入を防ぎ、室内環境を快適に保つために役立ちます。近年は駅などにある多機能トイレなどでは、車椅子の方が使用しやすいように自動ドアの設置が進んでいます。そんな便利な構造となっている自動ドアには、引き戸タイプや回転ドアタイプなどの種類があります。引き戸タイプは、ショッピングモールなどの商業施設でもよく見かける横にスライドするタイプの自動ドアです。引き戸は、1枚の扉のみが作動する片引き戸タイプと、2枚の扉を左右に動かす両引き戸タイプに大きく分けられます。両引き戸タイプの自動ドアであれば、多くの人が1度に出入りする際や車椅子の方が通る際にも余裕を持って通行できます。構造上一般的に開口幅が100㎝ほどであれば片引き戸タイプを、200㎝ぐらいあれば両引き戸タイプの自動ドアを設置できます。引き戸タイプの自動ドアのメリットとしては、扉が横方向にスライドするため、扉の前後にスペースが必要ないことがあげられます。開き戸の場合は扉を開けた際に人や物にぶつかる可能性がありますが、引き戸タイプであればその心配がありません。回転ドアタイプの自動ドアは、扉が円形になっており自動ドアを3方向に区切る構造となっています。自動ドアが回転する動きに合わせて建物内へ入ることができる自動ドアです。回転ドアタイプの自動ドアのメリットは、人が出入りしつつも外気を取り入れず、建物の内部と外部を遮断しながら通行可能なことがあげられます。そのような構造により、室内の温度をあまり変化させることなく出入りが可能です。医療機関の手術室や食品工場の冷凍倉庫、遮音の必要な防音室など特に高い機密性や遮音性が必要な場合には、特殊な自動ドアが利用されることがあります。自動ドアにはさまざまな種類がありますが、同じような構造で成り立っています。

◎自動ドアの構造と各部位の名称
自動ドアの構造部分は、大きくドアエンジンとコントローラー、モーター、ガイドプーリーと呼ばれる戸車、タイミングベルトに分かれています。自動ドアのエンジンは、自動ドアが開閉する際に作動する動力装置です。自動ドアのエンジンはドア上部の無目(むめ)と呼ばれる部分に収納されており、重い扉をスムーズに開けるだけではなく、何かが自動ドアに挟まりそうになった際に迅速に止める役割を果たしています。たとえセンサーが検知していなくても、モーターに負荷がかかるとコントローラーが扉の動きを止めます。このように現在使用されている自動ドアは、安全面に十分に配慮した構造となっています。自動ドアの頭脳とも言えるコントローラーは、自動ドアを動かすために必要なセンサーやモーターとつながっています。センサーからの信号により、コントローラーはモーターにドアを開くように指示を出します。実は自動ドアのコントローラーは扉の移動距離を記憶しており、安全を確保するために扉が開閉する際にモーターの速度を調整しています。硬い樹脂で作られているガイドプーリーの上部はベルトに接続されており、上から扉が吊り下げられている構造となっています。 自動ドアのタイミングベルトはモーターの回転を扉に伝える働きを担っており、ゴムや金属線、樹脂などで構成されており簡単には切れない造りとなっています。ガイドレールは自動ドアの下部にある溝であり、自動ドアがレールから外れないように樹脂製の振れ止めが付いています。自動ドアは、地震や火災などいざというときのためにブレークアウト構造となっています。ブレークアウト構造は、有事の際に建物の外へ避難する際に、手動で自動ドアを開けられる構造となっています。そのため迅速で安全に外へ避難することが可能です。自動ドアは自動的に開く構造となっているため、センサーにもさまざまな種類があります。
◎自動ドアのセンサーの種類
自動ドアのセンサーには、主に起動センサーと補助センサー、保護センサーの3種類があります。自動ドアを開閉するためのセンサーが起動センサーで、自動ドアを通る人や物が閉じる扉に挟まれないよう安全に配慮する役割を担っています。また閉じる自動ドアに人や物が接触したり衝突しないように、ドアの作動する範囲を監視する構造となっているのが保護センサーです。それぞれのセンサーには、光電方式や光線式反射式、超音波方式が採用されています。自動ドアの光電方式は、ドアの両脇に設置した投光器と受光器の間に通った光線を人や物が遮っている間は開いた扉が閉じない構造となっています。光線式反射式方式は、日本の自動ドアでもっとも普及しているセンサーです。近赤外線を自動ドアのセンサーから放出して反射率の変化を検知することにより、光が反射した物を確認して開く構造となっています。超音波センサーは、自動ドアの頭上の無目に設置したセンサーが扉の開いた部分に超音波を放射して人を感知するとドアを閉じないようにする構造となっています。自動ドアのタッチスイッチは、扉に付いているボタンを押した場合にのみ扉が開く構造となっています。タッチスイッチ内には、電波送信部分やボタンが押されたことを検知する装置、乾電池の3つが収納されており、ボタンを押すことにより電波を送受信して自動ドアが開く仕組みです。乾電池で作動しているため、定期的にタッチスイッチの電池交換を行う必要があります。触れるタッチスイッチは、軽く触れるだけで自動ドアが開く構造となっています。触れるのみドアが開くため、力の弱い小さい子どもやご高齢の方でも開けやすく便利な自動ドアです。ただし実際に触れて自動ドアを作動させているのではなく、触れる部分の横から赤外線が通っており、その赤外線に触れることで起動センサーが検知し扉が開く構造となっています。自動ドアにも通常のドアと同様にカギが付いており、さまざまな種類があります。

◎自動ドアの鍵の種類
自動ドアのカギは扉の下部に付いています。一般的な金属製のカギとしては、棒錠であるレバータンブラー錠やシリンダー錠、ディンプルキーがあります。レバータンブラー錠は、自動ドアの他にも南京錠やデスクの引き出しのカギとして使用されています。カギ穴が特徴的な形で、カギ自体は細長い棒状になっています。カギをカギ穴に鍵を挿し込んで回転させ、内部の障害物を移動させることにより施錠や解錠を行います。自動ドアのカギのなかでも特にレバータンブラー錠は非常にシンプルな構造であるため、防犯性は低いとされています。古くから使用されている自動ドアにはレバータンブラー錠が使用されているものがありますが、防犯性に不安があるため早めの交換をおすすめします。シリンダー錠は円筒形のカギ穴に鍵を差し込み施錠や解錠を行います。シリンダー錠には、ピンシリンダー錠やディスクシリンダー錠があります。ピンシリンダー錠はカギの内部に複数のピンがあり、カギを回すことでピンを押し上げて解錠する構造となっています。ディスクシリンダー錠はシリンダー内部にディスク上のタンブラーが複数並んだ構造となっており、カギ穴にカギを挿し込み回すと内部の障害物が移動し解錠可能なカギです。自動ドアのカギであるピンシリンダー錠やディスクシリンダー錠のカギにはギザギザがついていますが、ディンプルキーは先端が丸く、カギの表面に大きさの異なる丸いくぼみが複数あります。カギをカギ穴に差して回した際に、シリンダー内の複数のピンの形状と鍵の形状が一致することにより解錠する構造となっています。カギ内部の構造が複雑になっているため、金属製のカギのなかでは比較的防犯性の高いカギであると言われています。自動ドアのカギには、ドアの内側と外側の両方にシリンダーがついた構造となっているもの、外側にシリンダー錠が付いており自動ドアの内側には手で回すと解錠できるサムターンが付いたものなどがあります。自動ドアのカギの中でもピンシリンダー錠やディスクシリンダー錠は、その構造から空き巣のよく使う不正開錠の手口であるピッキングに弱いとされています。自動ドアのピッキングとは、カギ穴に特殊な工具を差し込み不正開錠する方法です。プロの空き巣であれば数分でカギを開けることが可能であると言われているため、防犯面で心配な場合はセキュリティ性の高い電気錠などに替えた方が良いでしょう。自動ドアの内側がサムターンである場合、外側から見ると内側がサムターンなのかどうかがすぐにわかることがあり、その場合ガラス破りの被害に遭う危険性があります。ガラス破りとは、文字通り自動ドアのガラスを破壊して侵入する方法です。店舗などの自動ドアは夜間で誰もいない間に、シリンダーの周囲のガラスを割ったり切るなどした後、そこから工具を挿し入れてサムターンを回し室内へ不正に侵入される可能性が考えられます。自動ドアのレバータンブラー錠やシリンダー錠などの安全性について不安がある場合、自動ドアの内側にサムターンが付いている場合には、よりセキュリティ性の高い構造である電気錠に交換するのもひとつの方法です。
◎自動ドアの電気錠の特徴
電気錠とは、その名前の通り電気を送ることによりカギの解錠や施錠を行います。電気錠であればカギ穴がないため、空き巣によるピッキングの被害を未然に防ぐことが可能です。自動ドアの電気錠の構造は電気錠本体、操作部分、制御部分の3つから成り立っています。電気錠本体は通常のシリンダー錠と同様に自動ドアの扉に取り付けられます。自動ドアの電気錠の操作部分には、あらかじめ決めておいた暗証番号をテンキーに入力してカギを解錠する暗証番号錠タイプや、ICカードをリーダーにかざして自動ドアのカギを解錠するカード錠タイプなどがあります。自動ドアの場合、金属製のカギを失くしたり盗まれると悪用されて不正に建物内に侵入される可能性があります。しかしカードキータイプであれば、万が一紛失してもカードを無効化することができます。カードは再発行することが可能であるため、セキュリティ性を高めるとともに利便性を維持できます。自動ドアの暗証番号錠タイプはそもそもカギを持ち歩く必要がないため、紛失するリスクを避けられます。カードキータイプと暗証番号錠タイプを組み合わせ両方の操作を行い、自動ドアを解錠するようにすればより防犯性が高まりより安心です。自動ドアの電気錠の制御部分は、自動ドアの電気錠本体と操作部分を正しく作動させるための心臓部のような役割を果たしています。自動ドアの施錠の管理のほかにも、電源の供給なども行っていることもその特徴としてあげられます。自動ドアに金属製のカギの代わりに電気錠を設置する場合は、業者による工事が必要となります。電気錠の工事は電気工事士の資格を持つ作業員が行う必要があります。カギを扱う業者によっては電気工事士が在籍している場合もあるため、電気工事と電気錠の取り付けを一貫して行えます。

◎まとめ
自動ドアの構造について知っておくことで、自動ドアやカギに何らかのトラブルが起きた場合の対処に役立ちます。東京に本社を置くカギの専門業者であるカギ舎では、自動ドアの構造やカギについて詳しく、電気錠の設置作業時に必要な電気工事士の資格を持つ作業員が在籍しています。自動ドアのカギなどについてお困りの場合は、365日24時間自動ドアのカギの相談や依頼に対応しているカギ舎におまかせください。