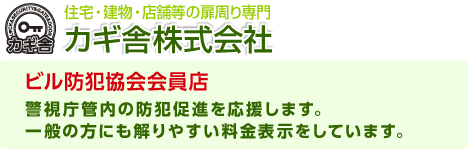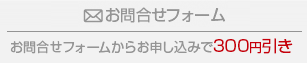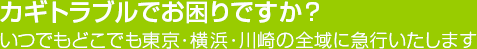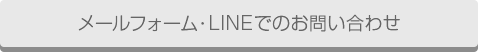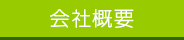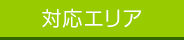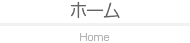電気錠における制御装置の役割
電気錠とは、電気を動力として自動で鍵の施錠や解錠ができる鍵のことを指します。集合住宅のオートロック、ホテルやオフィスなど多くの場所に設置されていますが、その利便性やセキュリティの高さから、一戸建て住宅でも広く普及するようになっています。電気錠のシステムは「電気錠本体」「操作器」「制御装置」の3つで構成されています。この記事では、電気錠の制御装置について詳しくご紹介します。
◎電気錠における3つの構成
ドアの鍵を閉めるという動作は、デッドボルトと呼ばれる四角形の部品がドアから飛び出してドア枠のくぼみに入り、ドアとドア枠を固定し開かないようにする仕組みによって行われます。デッドボルトを引っ込めるとドア枠との固定が解除され鍵が開く仕組みです。通常の鍵は、鍵をさして回したりサムターンと呼ばれるつまみを回したりすることによって、この動作を行いますが、電気の力を使ってこの動作を行うのが電気錠となっています。
○電気錠本体
電気錠と言われるもの自体は、ドアに取り付ける錠前本体のことで、ドアの開閉や鍵の施解錠をする大元部分のことを指しています。ドアに内蔵させる電気錠が多いですが、ドア枠の方に付ける仕様の電気錠もあり、門扉のような引き戸に付けたり工場で使用するような大きな扉や自動ドアに付けたりと、ほとんどの扉に設置することが可能です。鍵穴がついている電気錠は、鍵のみで使用できる通常の錠前とほとんど見分けがつかないですが、ドアノブや鍵穴がない電気錠もあり、用途に合わせて選ぶことができます。
○操作器
操作器とは、電気錠の操作を行う機器のことで、遠隔から鍵の施解錠をするスイッチや入室する人を認証する装置などを指しています。部屋の外側に付ける操作器は、許可された人だけが電気錠を解錠し部屋に入ることができるようにするための装置です。電気錠の認証方法には、テンキーで暗証番号を入力する、カードリーダーにカードをかざすといった方法だけでなく、指紋や瞳の虹彩、静脈などを使った生体認証、スマートフォンのBluetooth機能やWi-Fiを使って通信を行う方法などもあります。部屋の内側に付ける操作器は、来客時に室内から電気錠の解錠を行うことができるスイッチや退室時に認証せずに電気錠の解錠ができるボタンなど、遠隔で電気錠の施解錠を操作するための装置です。インターホンと連動させて、呼び出しや通話ができるようにしたりカメラで来客確認を行えるようにしたりすることもできます。
○制御装置
制御装置は、電気錠本体や操作器が動作できるよう電源供給を行ったり、動作の制御を行ったりするための装置です。制御装置は電気錠システムの心臓部とも言えるもので、施解錠の管理やユーザーの管理も行います。使用する制御装置の種類によって、電気錠に連動することができるシステムや加えられる機能が変わります。使用する場所によっては、電気錠や操作器を複数台設置する場合もありますが、1つの制御装置を使用して一括で管理することが可能です。電気錠を動かすためのシステムは、電気錠本体と操作器、制御装置という基本的な構造に加えて、無線LANを使ってスマートフォンやパソコンから電気錠を遠隔操作するためのネットワーク制御リレーや指定した時間や曜日に電気錠の施解錠を行うためのプログラムタイマー、非常用バッテリーなど、電気錠を使用する際の用途に応じて、必要な機器を組み込むこともできます。

◎制御装置の種類と機能
電気錠の本体と、それを動かすための操作器をつなぐ役割を果たしているのが制御装置です。制御装置は、電気錠システムを使用するユーザーの情報を管理し、動作の制御を行っています。テンキーやカードリーダーなどの認証装置から送られてきた情報は、制御装置によって登録してある情報と照合され、合致しれば電気錠の施解錠が行われます。制御装置の仕様は機能の違いによってさまざまで、制御装置単体の場合は、白やグレーの箱のような形をしている制御装置が多いですが、操作器と制御装置が一体型になっていて1台で両方の機能を果たす制御装置もあります。一体型でない制御装置でも、電気錠の操作ができるボタンがある制御装置やドアの状況や異常が分かるように表示が出たりランプが点灯するようになっていたりする制御装置も多くあります。制御装置には、電気錠と他の機器を連動させるという大きな役割もありますが、連動することができる機器はさまざまです。インターホンシステムや火災報知器、自動ドア、エレベーター、シャッター、また勤怠管理システムなどさまざまな機器をシステムに組み込み、制御装置によって動作を制御することが可能です。設置する電気錠の台数や他にどんな機器を連動させるかによって、使用する制御装置の種類が変わります。シンプルな構造で、電気錠1台と室内外の操作器といった電気錠システムであれば、1回線用の制御装置を使用することができます。電気錠を玄関と門に設置しインターホンを連動させる、大きな建物で複数のドアに電気錠を設置する、火災報知器と連動させるといった複雑な電気錠システムになる場合は、必要な回線に合わせて2回線用制御装置から16回線用制御装置など、多回線で使用できる制御装置を使用します。国内ロックメーカーのほとんどの電気錠に対応している制御装置や、生体認証システムに対応できる制御装置など、制御装置によって対応できる機器に違いがあるため、制御装置を選ぶ際は、連動させたい電気錠や他のシステムに対応しているかどうか確認する必要があります。制御装置には、電気錠システムの制御や管理、他の機器との連動とった基本的な機能以外に、制御装置に備えられる他の機能もあり、制御装置の種類によって機能に違いがあります。
○使用状況や異常の表示
多くの制御装置には、電気錠システムに異常が発生した時に警報ランプやブザーで知らせたり、通信不良や解錠不良などの警報を表示したりする機能があります。また電気錠が設置してあるドアの開閉状況や鍵の施解錠の状況が制御装置に表示されるようになっていることも多く、複数の電気錠を設置している場合は、それぞれの状況が制御装置から確認できます。
○モード設定
施解錠の設定を変更できる制御装置もあります。ドアを閉めると常に自動で電気錠が施錠される設定やドアの開閉に関係なく施錠と解錠を交互に行う設定、手動で解錠した場合は自動施錠しない設定など、制御装置によってさまざまな設定が可能です。
○タイマー設定
タイマー設定を行える制御装置は、時間によって施解錠の設定を変えられます。週間タイマーや24時間タイマーが内蔵された制御装置などもあります。
○非常時のための機能
非常時に、制御装置から全ての電気錠を一斉解錠することも可能です。また、パニックオープンやパニッククローズという、非常時に全ての電気錠を解錠したり施錠したりする設定ができる制御装置もあり、電気錠を付ける場所の用途によって選ぶことができます。
○インターロック機能
電気錠のインターロック制御ができる制御装置があります。インターロックとは、一定の条件が整わないと機器が動作できないようにすることで、例えば2箇所で設置した電気錠で、片方が施錠されないともう片方は動作できないようにするといった使用ができます。インターロック制御ができる制御装置は、厳重な入退室管理を行う場合に有効です。
○停電時のための機能
制御装置には、停電した場合に必要な機能もあります。停電補償機能がある制御装置やバッテリー内蔵型の制御装置であれば、停電後でも一定の時間は通常通りの操作が可能です。また制御装置にバッテリーを別で取り付けておくことで、停電した場合に備えることもできます。マンションのエントランス、ビルや工場などの事業所では停電補償機能付きの制御装置を選ぶと安心です。
○採風システム
窓に電気錠を設置する場合、採風システムを取り入れるなら、風通しができるように少し窓が開いた状態でロックすることができます。専用の制御装置と組み合わせて使用します。
○エコタイプ
エコタイプの制御装置であれば、待機時の消費電力を減らすことも可能です。

◎電気錠のメリット・デメリット
電気錠を導入することでさまざまなメリットがあげられます。まず物理的な鍵を使わないので、錠前へのサムターン回しやピッキングによる空き巣狙いなど、犯罪対策に有効です。ホテルのオートロックのように、外出時に扉が閉まると自動的に施錠されることから、外出後に施錠し忘れることを防げます。また、電気錠は入退室管理システムと連動が可能です。カードリーダーなどを併設することで、オフィスで働く人たちの出勤、遅刻、早退を含めた労働時間を正確に管理できるようになります。製品によりますが体温が高い人が入室できないようにする体温測定機能装置や、入室履歴から混雑度を表示させる機能もあります。また、タイマーで電気錠の施解錠を自動的に行えるため、防犯性と利便性に優れています。一方、電気錠はデメリットもいくつかあります。電気錠は電気を使って解錠を行うため、電気がなによりも重要となってきます。そのため、災害時における停電などで電気錠が作動しなくなる恐れがありますが、停電時に予備の電源が作動するものや、非常用のシリンダーが使える電気錠もあります。災害などの非常事態に備える場合はバックアップ機能があるものを選ぶと安心です。また、電気錠は一般的なシリンダー錠と比べると、本体と操作部分、制御部分、配線ケーブルや通電金具の取り付けに加え、設置工事費が必要になるので導入コストがかかってきます。取り付け場所などによっても費用が変わってくるため、導入の際は必要な機能や予算を考えておくことが大切です。
◎電気錠の導入事例
実際に電気錠はどのような形で導入されているのでしょうか。家庭からオフィスまで具体的な導入事例をご紹介します。
◯家庭の玄関ドアに電気錠
家庭に電気錠を導入すると、鍵を持ち歩く必要がない暮らしが実現します。玄関ドアのリーダーに暗証番号で施解錠できるテンキーを導入すると、鍵やリモコンキーなど持ち歩く必要がなくなります。モニター付きのインターホンと連動させると訪問者の顔を確認して解錠できます。また、スマートフォンの専用アプリを活用すれば外出先から電気錠の解錠も可能になります。
◯オフィスには入退室管理との連動を
オフィスでは入退室システムを導入することによって、パソコンを使って複数の扉を一括して集中管理できます。カードリーダーを夜間通用口に設置すると、夜間の出入りを制限できます。事務室や電算室、資料室などの電気錠をカードで解錠した履歴が残るため、情報の流失などの未然防止につながります。全扉ごとのカードデータの登録や抹消は、管理室に置かれたパソコンで操作でき、全扉の状態を画面に表示できます。
◯病院の共有トイレに電気錠を導入
病院内の共用トイレに電気錠を設置すると専用トイレのように使えます。病室の壁を隔てて共用トイレの両方の入り口に電気錠と開閉ボタンを取り付けることで、片方が使用中であればもう片方は操作できない仕組みで、病院スペースの有効活用につながります。加えて火災の時は、火災報知器の信号を受信して一斉に解錠することで避難と救助が可能です。
◯商業施設のセキュリティ管理に電気錠
商業施設はテナントが複数入居し、従業員、スタッフ、納入業者、来店者など多数の出入りがある場所ですが、電気錠と集中操作盤の導入で施解錠を集中管理できます。ビルの通用口や事務室など入室を制限したい扉に設置した電気錠により、重要エリアの出入りを管理します。ビル通用口付近に設置した警備用の集中操作盤の一カ所で、全ての鍵を管理できます。警備員による常駐警備との組み合わせで強固なセキュリティが実現します。

◎まとめ
電気錠は利便性が高くセキュリティ面でも安心できる鍵です。電気錠システムの取り付けや交換は、「カギ舎」までお気軽にご相談ください。ご要望を丁寧にヒアリングし、用途に合った電気錠や制御装置をご提案いたします。カギ舎では、業界最安値と熟練した技術で最高のサービスをご提供しています。見積り以上ご請求することはなく、アフターフォローも万全ですので安心してご依頼いただけます。年中無休で24時間受け付けしておりますので、ぜひ1度ご相談ください。