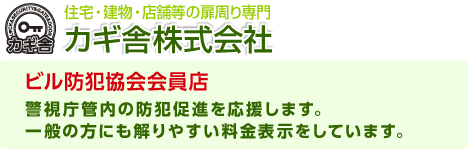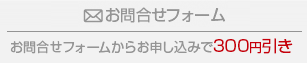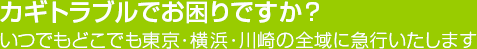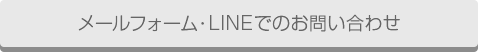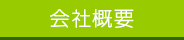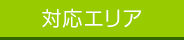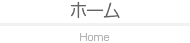パナソニックインターホンのドアの解錠トラブル


インターホンは、来訪者と対面することなく姿を確認したり会話したりすることができるため、今や住宅や施設にとってなくてはならない重要な設備のひとつです。インターホンは大変便利ですが、ときにトラブルを生じることもあります。集合住宅ではオートロックの解錠、戸建て住宅でもドアの解錠機能を兼ねそろえたインターホンがあります。ドアの解錠を兼ねそろえたインターホンが故障した場合、非常に不便なだけでなく、防犯性能も落ちる恐れがあるので速やかに対処する必要があります。この記事では、インターホンによるドアの解錠のトラブルを中心にご紹介します。
◎オートロック機能を備えた集合住宅のインターホン
ある程度戸数の多い集合住宅ではセキュリティを高めるために、各住戸の玄関だけでなくエントランスにオートロック付きのドアを設けているところが増えています。エントランスと各住戸で2段階のドアの解錠が必要になるので、防犯性を高めることができます。オートロック機能のある集合住宅は、必ずエントランスにインターホンがついています。エントランスのドアの解錠方法には暗証番号、集合キー、カードキー、指紋認証などがありますが、来訪者はエントランスのインターホンから居住者にドアの解錠を依頼する必要があります。来訪者は、エントランスのインターホンに居住者の部屋番号を入力することで、各住戸の居住者にコンタクトをとります。居住者は直接対面せずとも通話やカメラなどで来訪者を確認することができるので安心です。エントランスのドアの解錠は、各住戸のインターホンの室内子機にある解錠ボタンを押すだけで行うことができます。エントランスに出向かずとも各住戸から遠隔で簡単にドアの解錠を行うことができるので大変便利です。もしインターホンからエントランスのドアの解錠ができなくなった場合は、その都度エントランスに出向いてドアを解錠しなければならなくなり大変不便となるでしょう。またオートロック機能付きの集合住宅でインターホンからドアの解錠操作ができない問題が発生した場合、ほかの住戸でも同様の解錠トラブルが生じる可能性もあります。交換が必要な故障の場合は全住戸一斉にインターホンを交換しなければならなくなることがあります。この場合は、入居者全員に関わる問題となるため、集合住宅のインターホンについては特に慎重かつ迅速な対応が求められます。
◎戸建て住宅用インターホンによるドアの解錠
戸建て住宅用のインターホンでもドアの解錠が行える製品があります。戸建て住宅用のインターホンには各社さまざまな製品がありますが、パナソニックでドアの解錠が行えるインターホンは、家じゅう「どこでもドアホン」とスマホで「外でもドアホン」になります。この2機種は玄関ドアの電気錠と連携させることが可能です。家じゅう「どこでもドアホン」は、テレビモニター付きのインターホンです。ワイヤレスモニター付きの子機がついており、自宅内であればどこからでも来訪者の対応を行うことができます。家じゅう「どこでもドアホン」では、インターホンの親機やワイヤレス子機にドアの解錠を操作するための解錠ボタンがついているので、来訪者の応対と同時に速やかにドアの解錠を行うことが可能です。スマホで「外でもドアホン」も家じゅう「どこでもドアホン」と同様に、インターホン親機やワイヤレス子機を通してドアの解錠が行えるほか、スマホと連携させることでアプリを通してドアを解錠することができます。外出先など家から離れた場所にいても、一定条件を満たすとスマホから遠隔操作ドアを解錠することができるので、家族がスマホを忘れて解錠できないときも安心です。スマホで「外でもドアホン」、家じゅう「どこでもドアホン」をインターホンからドアの解錠を行えるようにする場合には、VL-JY1(JEM-Aアダプタ)が必要です。まず、インターホンのモニター親機を3線式ケーブルでVL-JY1(JEM-Aアダプタ)とつなげます。そしてJEM-Aアダプタのコネクタ付きケーブルを電子錠操作器のHA端子に接続します。施工は、電気工事士の資格をもった作業員が行う必要があります。インターホンからドアの解錠が行えるようになれば、玄関に出向かずとも遠隔でドアを解錠し、来訪者を招き入れることができるようになるので利便性が高くなります。

◎インターホンでドアを解錠できないトラブルとその原因
インターホンは常時通電している電気製品であるため、故障や不具合の発生は避けて通ることができないと言われています。インターホンには寿命があり、家庭用インターホンでおよそ10年、集合住宅やオートロックと連動しているインターホンでおよそ15年とされています。経年劣化によるトラブルの発生はやむを得ないため、耐用年数を超えている場合は交換を視野に検討すべきでしょう。インターホンのトラブルは、電源の確保や各種設定の調整など故障でなければ自分で解決できる問題もありますが、インターホンのいずれかの部位が故障している場合は、自力で修理することは難しいです。また配線に関するトラブルは、感電の危険性があるため電気工事士の資格を有したものでなければ修理を行うことはできません。インターホンは精密機械であるため、知識のないまま扱うとさらなる故障を引き起こす可能性もあります。解錠トラブルなど不具合を生じた際にはむやみに触らず、専門業者に点検や修理を依頼しましょう。インターホンのトラブルのなかでも、インターホンでドアを解錠ができないトラブルは生活や防犯面で大きな影響がでます。ドアの解錠ができない場合、配線に問題を生じている可能性があります。まずはインターホンの親機とVL-JY1を接続している3線式ケーブルが端子から外れていたり、それぞれの配線が断線していないか調べる必要があります。次に制御端子、モニター端子、コモン端子のそれぞれに正しく線がつなげられているか確認しましょう。そして、インターホンのモニター親機の機器設定が電気錠に設定されているかチェックします。電気錠操作器側からは、VL-JY1のコネクタ付きケーブルがHA端子に正しく挿入できているか確認をしてください。これらを確かめた上でインターホンが解錠できない場合は、故障の可能性が高いと言えるでしょう。配線の問題の場合は、端子から外れている目視でトラブルを発見できる場合もあります。慣れている人なら直せることもありますが、見た目に問題がわからない場合は、より被害を拡大しないように無理をせず専門業者に修理を依頼してください。インターホンにはドアを解錠できないトラブルのほかにも、さまざまなトラブルが発生します。まずはインターホンの呼び出し音に関するトラブルです。呼び出し音が鳴らない、勝手に鳴る、鳴ったり鳴らなかったりする、鳴りっぱなしなどの不具合を生じることがあります。インターホンが鳴らない場合、まずはじめに確認しなければならないのは電源です。インターホンの電源プラグが抜けているまたは電池が切れていることによるトラブルは意外と多く報告されています。次にインターホンの使用年数を確認しましょう。耐用年数を超えて使用している場合は、寿命による故障が考えられるためインターホンの交換を検討する必要があります。そのほかの原因としては、インターホン内部の結露による故障、虫の侵入などの異物の混入による配線の断線や誤作動、配線ミスによる誤作動などが考えられます。インターホンが鳴りっぱなしになるトラブルの場合は、室外子機のボタンが押し込まれていたり、異物の混入によって誤作動が起きている可能性が高いでしょう。室外子機の多くは屋外に設置するため、どうしてもトラブルが多くなってしまいます。次にインターホンの音声に関するトラブルです。ハウリングや雑音、音量の変動などによってインターホンから声がうまく聞こえなくなる場合があります。インターホンの音声の問題に関しても、まずは電源に問題がないか確認します。電池残量が少なくなってきた場合に、音量が小さくなって音声が聞き取りづらくなることがあるので、電池を新しいものに交換して様子を見てみましょう。また併せてインターホンの音量設定も確認します。何らかの拍子に音量の設定が変わってしまい、聞き取りにくくなるケースもあります。それらに問題がない場合は、マイクやスピーカーの故障、配線の異常の可能性が考えられます。音がぶつぶつと途切れたり、突然高い音が鳴ったりするなどのトラブルの場合は配線の接触不良や断線が原因となっている場合が多いです。またワイヤレスタイプのインターホンの場合は、テレビなどの電子機器と電波が干渉することによってハウリングが生じる可能性があります。その場合は、インターホンの子機やモニターの設置場所を変更することでトラブルを解決できるでしょう。次にインターホンの映像に関するトラブルです。モニター付きインターホンでは、モニターにうまく映像が映らなくなるトラブルがあります。まずは室外子機のカメラに汚れがないか、表面が白くなっていないか確認しましょう。砂ぼこりや紫外線などの影響によってカメラ自体が汚れたり、傷がつくことでモニターが見えにくくなる場合があります。次にモニターの設定を確認します。インターホンのモニター照度などが適切に設定されているか確認します。そのほか、玄関子機のカメラの故障、モニターの故障などが考えられます。このようにインターホンには解錠の不具合をはじめ、さまざまなトラブルが生じる場合があります。

◎インターホンの解錠トラブルの責任元
インターホンが解錠できないといったトラブルの責任元は、インターホンが個人所有物なのか共有設備なのかによって異なります。分譲マンションではインターホンを共有設備として扱う場合が多いですが、室内親機については個人所有とする場合もあります。建物によってその扱いはさまざまであるので、管理者に確認する必要があります。インターホンを共有設備とする場合には、個人の判断で修理や交換を行うことはできません。必ず管理会社を通して相談をする必要があります。反対にインターホンを専有部分として扱う場合は、個人で修理依頼を行うので修理や交換費用については個人で負担しなければなりません。オートロック機能付きのインターホンの場合は、必ず管理会社を通して修理や交換を行いましょう。オートロック機能付きのインターホンは、個別にインターホンを交換することができません。修理不能な故障が見つかった場合には、全戸一斉に交換しなければならないためです。分譲マンションの場合は、インターホンの寿命や大規模修繕工事の時期に合わせて、解錠できないといったトラブルが発生する前にインターホンのリニューアル工事を検討するのがおすすめです。
◎インターホンを長く使うポイント
解錠トラブルといったインターホンの不具合を防ぐためには、設置場所を工夫することがひとつのポイントになります。インターホンの室外子機は、直射日光や雨風に直接さらされる場所を避け、道路に面して設置しないようにすると良いでしょう。インターホンは直射日光によって紫外線の影響を受けて劣化しやすくなります。また細かい隙間にほこりや砂などが入り込むことも故障の原因になる場合があります。そのため、できる限り道路に面する場所や雨風に直接さらされやすい場所を避けると良いでしょう。そのような環境を避けられない場合は、インターホンにカバーをつけるのもおすすめです。それでもインターホンには寿命があるので、できる限り長く使うためには日々メンテナンスをすることをおすすめします。屋外に設置するインターホンの室外子機は雨風にさらされるため、ほこりや砂などの細かいゴミが隙間に入りやすいです。また特に隙間に小さな虫が侵入する可能性もあります。ボタンなどの人の手が触れる場所は皮脂汚れも付着し、室内親機も同様にほこりや皮脂などによって汚れてしまいます。このようなほこりや汚れをそのままにしておくと故障の原因になりかねません。 清掃方法としては、まず薄めた消毒液を柔らかい布に含ませて、力を入れずに表面を拭いていきます。細かい溝は綿棒などを使うと良いでしょう。1度拭いた後は、硬く絞った柔らかい布で水拭きします。それほど汚れが目立つ場所ではありませんが、最低でも1年に1回程度は清掃することで、インターホンを長持ちさせ、解錠できないといったトラブルを回避することができます。
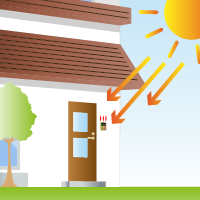
◎まとめ
インターホンは、使用頻度が高く常に通電していること、屋外に設置していることなどからトラブルを生じやすい電子機器のひとつです。トラブルを放置するとさらに症状が重症化してしまう恐れもありますので、できるだけ早めに対処してください。被害を最小限に抑えるためにもトラブルは専門業者に依頼するのが良いでしょう。カギ舎では、インターホンでドアの解錠ができないトラブルなど、インターホンやドアの解錠に関する不具合や修理のご相談を承っております。是非ご気軽にカギ舎までお問合せください。