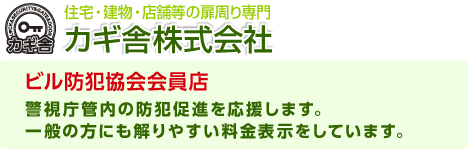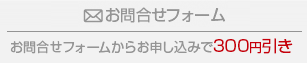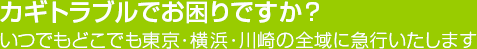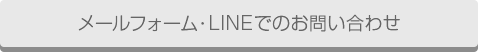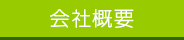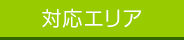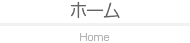ビジネスホンの新規導入
ビジネスホンは内線通話や保留・転送などさまざまな機能があり、オフィスにおいて非常に便利なツールです。複数の電話回線を多くの電話機で共有し、離れた席や違うフロアに内線で電話を取り次いだり、コールセンターなどのように音声自動応答によるアナウンスを流すことができますが、従業員が大勢いる大企業しか必要ないと思っていませんか。しかしビジネスホンには、中小企業や少人数のオフィスにこそ向いている便利な機能が多くあります。この記事では、小規模オフィスでこそ業務効率がアップするビジネスホンの機能やビジネスホンを新規に導入する手順、ビジネスホンを新規導入するときの注意点について解説します。ビジネスホンの新規導入で今よりも確実に業務効率が上がるので、ぜひ参考にしてください。
◎小規模オフィスこそビジネスホンで業務効率がアップ
内線や転送などビジネスホンに備わっている機能は、多くの従業員がいて広いオフィスでは非常に便利です。では従業員の数が少なく室内が狭い小規模オフィスにビジネスホンは必要ないのかというとそうではありません。小規模なオフィスにこそ業務の効率化に役立つビジネスホンの便利な機能があります。
○通信費削減
社員が外出することが多い会社では、外出先から携帯電話で電話をかけるシーンが多くなります。携帯電話のキャリアや通話プランにもよりますが、一般的には携帯電話からの発信は固定電話よりも通話料金が高く設定されています。ビジネスホンの「リモートコールバック機能」は、外出先の携帯電話から会社にワンコールして切ると自動的にコールバックされ、コールバックされた電話に応答して発信したい相手の電話番号を入力すると会社の電話として発信することが可能です。携帯電話の通話料金を軽減し、会社の電話をIP電話などの通話料金が安い回線にすればより通信費の削減に役立ちます。また電話をかけた相手には会社の電話番号が表示されるため、個人の携帯電話の番号を知られることもありません。
○外出先でもオフィスの電話が受けられる外線自動転送
外線自動転送とは、オフィスにかかってきた外線電話を携帯電話などに自動で転送する機能で、外出先でもオフィスにいるかのように電話に出られます。社員数が少ない企業では「オフィスが無人になるから外出できない」という悩みがありがちですが、外線自動転送機能を使うことで電話を気にせずにいつでも外出ができるようになったり、急な休みでオフィスを閉めるけれども電話だけは受けられたりします。転送の際は複数の電話を設定でき、1人が出られない場合には次の人へと転送されるので電話の取りこぼしもありません。
○インターホンと連動して外出先でも来客対応ができる
ビジネスホンはインターホンや電気錠と連動させることができます。オフィス内にいるときはデスクのビジネスホンでインターホンの応答と電気錠の解錠操作ができるので、来客の際にわざわざ席を立つ必要がありません。インターホンからの呼び出しは外出先の携帯電話にも転送できるので、不在時に突然の来客があっても対応が可能です。アポなしの訪問が多ければ来客対応のために外出を控えなければなりませんが、ビジネスホンとインターホンを連動させていれば気にせずに外出が可能です。
○録音機能で24時間用件を受けられる着信代行サービス
夜間や休日にオフィスにかかってきた電話に対して、ビジネスホンが代わりに応答します。お客様から受けた通話内容はそのまま録音されて携帯電話に自動通知されるので、お客様からの急な注文やクレームにも迅速に対応が可能です。録音されたメッセージはビジネスホンに保存され、パソコンや携帯電話で検索ができるので後から内容の確認ができます。

◎ビジネスホンを新規導入する手順
ビジネスホンを新規で導入するには「電話回線」「主装置」「電話機」が必要ですが、これらを用意するために事前に確認しておくべきことがあります。
○オフィスで必要とする電話機の台数を確認する
すべての従業員が頻繁に電話を使うのであればデスクの数だけ電話機が必要です。あまり電話を使わなかったり電話をかける時間がまちまちであったりなど、全員に電話機が必要なければ「2人で1台」や「グループで1台」などと決めて新規導入する電話機の数を決定しましょう。また会議室や応接室などの共有で使用する部屋にも電話機が必要であれば追加ができます。
○チャンネル数を決定する
新規で契約する電話回線の種類と回線数を決めるために、必要となる「チャンネル数」を確認します。チャンネル数とはオフィス内で同時に通話ができる数のことで「回線数」とは異なります。回線数はNTTなどの通信会社と契約する外線数のことですが、チャンネル数(ch)とは同時に通話をする数のことです。たとえば10人の従業員がいて朝や夕方などのピーク時には最大6人が同時に電話をするのであれば6chが必要となります。一般的に必要なチャンネル数は従業員の3分の1だと言われているので、どのくらいのチャンネル数にしてよいか決められないときにはこの3分の1を目安として設定しましょう。
○契約する電話回線の種類と回線数を決める
ビジネスホンで使う電話回線には大きく分けて「アナログ回線」「デジタル(ISDN)回線」「IP電話・光電話」があります。アナログ回線はNTTが提供するアナログ信号を使って通信する回線で、音声を銅(メタル)線にのせて通信するサービスです。基本料金や通話料金はIP電話と比較すると割高で、とくに距離が遠くなればなるほど通話料が上がり音声には雑音が入りやすくなります。また同時に通話できるチャンネル数が1回線につき1chと少ないので、ビジネスホンを新規に導入する際の回線にはあまり向いていません。しかしアナログ回線は通話が安定して電話がつながりやすく停電のときも使えるので、災害時に備えて数回線残している企業もあります。
デジタル(ISDN)回線は、音声を0と1にデジタル化して通信をする回線です。アナログ回線と比較して遠方でもノイズが少なくクリアな音声での通話が可能です。同時に通話ができるチャンネル数は1回線につき2chなので、ビジネスホンで利用するにはアナログ回線よりは適していますが、インターネットを利用するときは速度が64kbpsと遅くなるので注意してください。
IP電話・光電話はどちらもインターネットを利用した回線で、IP電話は音声をパケットというデータに分けて送信し、光電話は光ファイバーという専用のインターネット回線を使って通信を行います。IP電話はインターネットサービスプロバイダが提供する回線ですが、光電話は光ファイバーを持つ回線事業者(NTTやKDDIなど)が提供する回線です。IP電話と光電話の違いは電話番号で、IP電話が「050」からはじまる番号が付与されるのに対し光電話は従来の市外局番からはじまる番号が使えます。基本料金がアナログ回線やデジタル回線と比較すると約3分の1程度と安く、通話料金も距離に関係なく全国一律なのでビジネスホンを新規に導入する際の回線としてはおすすめです。またIP電話は同じプロバイダを利用していると通話料金が無料なので、全国に支店や営業所を持つ大きな企業では通信費の削減に役立ちます。しかしIP電話には110番や119番などの緊急通報やフリーダイヤルが使えないというデメリットもあります。またIP電話・光電話はどちらも電源を必要とする回線で、停電の際には電話が使えないため注意が必要です。チャンネル数については、IP電話・光電話は1回線につき複数チャンネルあり、たとえばNTTのひかり電話オフィスAでは最大300chも設定できるのでコールセンターなど多くのチャンネルが必要な企業でも十分に対応が可能です。
ビジネスホンを新規に導入するときはオフィスの状況や必要なチャンネル数などによって回線の種類と回線数を決定しましょう。どのような回線を選んだらよいかわからない場合は、調査のうえ適切な回線の提案をしてもらえるビジネスホンの専門業者に相談をするのがおすすめです。
○必要な機能を確認して主装置と電話機を選ぶ
ビジネスホンを新規に導入する際には、オフィスで必要とする機能を把握しておくことが重要です。ビジネスホンは主装置と電話機で構成されているシステムですが、主装置によって使える機能や回線数が違ってくるからです。新規導入時にどのビジネスホンを選んでも内線通話や保留・転送などの基本的な機能は備わっていますが、メーカーや機種によっては使える機能はさまざまです。「録音機能や自動応答機能が使いたい」「コードレス電話機がほしい」などのようにオフィスで必要とする機能を整理して、ビジネスホンを新規で導入する際にはそれらが使えるものを選んでください。ビジネスホンの種類が多くありすぎてどれを選んだらよいか迷ってしまう場合は、ビジネスホンの専門業者へ必要な機能を伝えると適切なビジネスホンの主装置と電話機を提案してもらえるのでおすすめです。
○購入とリース契約を検討する
ビジネスホンを新規で導入する際には「購入」と「リース契約」があります。リース契約とは、一定の期間リース会社に毎月のリース料を支払って利用する契約です。新規に購入する場合、ビジネスホンの機種や設置台数にもよりますが機器代金や設置費用などが必要です。新規導入費用は高額になってしまうことがあるのでリース契約も検討されるかもしれませんが、リース契約は新規の導入費用はかからないものの、リース期間中は毎月支払いが発生するので購入するよりもトータルでの支払金額は高くなります。また一般的に5~7年がリース契約の契約期間ですが途中解約はできず、解約をするためには残りのリース料を一括で支払う必要があるため注意が必要です。リース契約の期間が満了すると原則的にはビジネスホンは返却しますが、まだビジネスホンを使いたい場合は2つの方法があります。それは新規のリース契約を結びなおすことと、今まで使っていたビジネスホンを再リースすることです。再リースは機器が古くなっているというデメリットはありますが、リース料は安くなります。リース会社によってはリース料がこれまでの10分の1程度に抑えられることもあるので、ビジネスホンに不具合がなく十分に使えそうなときは再リースもおすすめです。またリース期間が満了した機器を「買い取り」させてくれるリース会社もあるので、契約時にリース満了後についての確認をしておきましょう。リース契約は新規導入の初期費用がかかりませんが、購入と比べてトータルでかかる費用が高額となり、最終的に自社の資産とはならないケースがほとんどです。ビジネスホンをリース契約するときには、自社の資産となりトータル費用も抑えられる購入とよく比較検討してから決定しましょう。

◎ビジネスホン新規導入の注意点
ビジネスホンを新規に導入する際には、オフィスの人数や必要な電話回線・使いたい機能などを考えて機器を選びますが、将来的に人員の増員による電話機の増設の可能性がないかどうかも考慮して決定しましょう。ビジネスホン主装置の機能はユニット(基板)によって決まりますが、主装置の種類によっては増設できるユニット数や機能に制限があるため、あらかじめ余裕をもって主装置を選んでおくと将来の変更にも対応ができます。ビジネスホンを新規に購入する際には、機器の台数にもよりますがまとまった金額が必要となるため、少しでも新規導入コストを抑えたい場合は、中古のビジネスホンを検討する方もいると思います。中古のビジネスホンでも、使用状態がよければ問題なくビジネスホンの機能を使うことができるのでコスト削減を優先する場合にはおすすめですが、以下のような注意点をしっかりと把握したうえで決定しましょう。新品のビジネスホンはメーカーによる保証期間がついていますが、中古の場合はメーカー保証が切れていることがほとんどです。販売店独自の保証期間がついていることもありますが、新規購入前に保証期間の有無を確認しておくことが重要です。また中古のビジネスホンを新規購入する前には、そのビジネスホンの販売開始の時期と生産終了年の確認をしておきましょう。販売時期があまりにも古いとそれだけ使用期間が長いということなので、故障のリスクが高まります。ビジネスホンは生産終了から7年を経過するとメーカーによる修理用部品の供給がされなくなるため、故障をしても修理ができなくなってしまいます。ですからどうしても中古のビジネスホンを新規購入するのであれば、できれば修理用部品の供給がある生産終了から7年以内のものを選ぶことをおすすめします。中古のビジネスホンは機器代金を抑えることができますが、新規導入時にかかる工事費や設置費用、設定費用などは新品と同様にかかり、機器が古いため修理などその後の保守費用はむしろ新品よりも高くつく可能性があります。新品のビジネスホンの新規導入費用は中古よりかかるものの、メーカー保証があり修理可能年数も長く、トータルでかかる保守費用や故障などのストレスもないので結果的にはおすすめといえます。

◎まとめ
ビジネスホンの機能はさまざまで、大企業だけではなく小規模なオフィスにとっても通信費削減やオフィスの無人化が可能など、業務効率アップに役立つ機能が多くあります。ビジネスホンの新規導入に際しては、電話回線の種類や電話回線数など決めなければならないことが多くあり、戸惑ってしまうかもしれません。ビジネスホンの新規導入実績を多く持つカギ舎では、お客様のニーズにあわせて最適なビジネスホンをご提案しています。ご相談や調査・見積もりだけでも無料なので、ビジネスホンの新規導入に興味がある方はぜひお気軽にお問合せください。