カギ舎株式会社
■本社
〒151-0063
東京都渋谷区富ヶ谷1-30-10
TEL:03-6454-1241
〒151-0063
東京都渋谷区富ヶ谷1-30-10
TEL:03-6454-1241
■事業所
杉並区和田1-25-3
杉並区和田1-31-3
中野ブロードウェイ422-2
杉並区和田1-25-3
杉並区和田1-31-3
中野ブロードウェイ422-2
東京商工会議所
杉並警察ビル防犯協会所属
杉並警察ビル防犯協会所属

【東京都】
中野区 新宿区 足立区 荒川区 杉並区 板橋区 江戸川区 大田区 葛飾区 江東区 品川区 渋谷区 世田谷区 台東区 中央区 千代田区 墨田区 豊島区 練馬区 文京区 港区 目黒区 北区 西東京市 三鷹市 調布市 武蔵野市 全域
【埼玉県】
和光市、新座市、朝霞市、戸田市、蕨市、川口市
【神奈川県】
横浜市 川崎市 全域
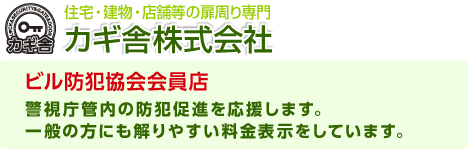
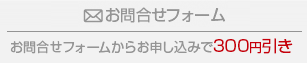

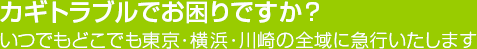

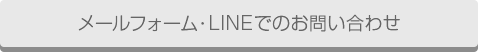
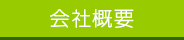
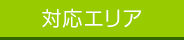
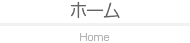




顔や指紋などの身体的特徴や行動的特徴の情報を使って、個人認識をする技術を生体認証といいます。身近な機器だと、スマートフォンやパソコンなどのOSログインなどで活用されています。指紋認証は、誰ひとりとして同じ形がない指の指紋の身体的特徴を使用した認証方法です。唯一無二の個人の情報を用いるため、セキュリティ性の高さからマンションなどの賃貸住宅のほかにも、最近では戸建て住宅にも生体認証を導入するケースが増えており、防犯とセキュリティ対策に欠かせない技術のひとつです。生体認証は新たな鍵として個人認証の技術が急速に発展しています。生体認証の主な種類は顔認証、指紋認証、掌紋認証、虹彩認証、静脈認証、音声認識などがあり、別名「バイオメトリクス認証」と呼ばれています。指紋認証は、生体認証のなかで最も早く国内で導入されました。指紋認証は、指先の指紋を用いて本人であることを認証することによって、ロックや鍵を解錠する技術です。指紋は1人ひとり異なり、ほかの人と全く同じ型がないため、セキュリティ性の高い個人情報といえます。第三者のなりすましによる不正侵入が不可能なことから、パソコンやスマートフォン、玄関ドアなどの指紋認証システムのロック解除方法に利用されています。指紋認証は、インドや中国では古くから指紋照合を行われて歴史がありますが、20世紀初期には日本でも警察が犯罪なども捜索のために、犯人の指紋を照合するために導入されるようになりました。1960年代に、コンピューターを利用した指紋認証の自動照合が行われるようになり、本格的に技術の研究がはじまり、1982年には警察庁の指紋認証システム導入が実用化されています。生体認証のなかで、歴史が長い指紋認証はほかの生体認証方式に比べると、技術の進歩や改善が繰り返されているため、最新の指紋認証の技術では認証精度や認証方法が進化しており、安全性と利便性が向上しています。高度なセキュリティが求められる銀行ATMや研究施設などに導入されていますが、テクノロジーの進歩と共に、私たちの暮らしの身近なスマートフォンやパソコンのロック解除、入室管理システムなどにも導入されており、指紋認証方法は一般的になっています。指紋の形状はさまざまな種類があり、大別すると弓状紋(アーチ型)、蹄状紋(ループ型)、渦状紋(ホール型)の3種類があります。弓状紋は指紋の中心で弓なりになっている形状で、指の横線のように片方から出て反対方向で終わります。中心の三角洲があるタイプや無いタイプ、高いタイプ、馬蹄形が右や左に閉塞されている模様などに区分されます。蹄状紋は、馬のひづめに形が似ており、馬蹄形が右に向かっている模様や、左に向かっている模様、馬蹄形が右や左に閉塞されている模様などに分けられます。渦状紋とは、中央が渦を巻いているような形状で、指紋の全体が左巻や右巻、中心の円が縦に細長いタイプ、中央の線がマルク円を描いている形などがあります。指によって蹄状紋や渦状紋が混ざっている場合や、同種紋様の2個以上の指紋が混合していることもあり、蹄状紋や渦状紋は日本人に多くみられる形状といわれています。手のひらなどに皮膚が盛り上がっている多くの線状の隆起があります。その皮膚が盛り上がっている部分を「隆線」といい、皮膚がへこんでいる凸の部分を「谷線」といいます。指紋認証は、指紋の全ての隆線を取り出して照合をしているわけではなく、隆線の特徴点である端点と分岐点を用いて指紋照合を行う認証方法を導入しています。指紋の隆線が行き止まりになっているポイントを「端点」といい、隆線が枝分かれしているポイントを「分岐点」と呼ばれます。指紋認証では、指紋の隆線の特徴点の位置や方向を利用する照合方式で行われ、指紋の特徴点はおおよそ20~40個ほどあれば照合が可能と言われています。一方で指紋が偶然に一致されていることがあると、セキュリティ面で安全ではありません。それを防止するために、「リレーション」と言った、ひとつの特徴点とほかの特徴点との間に通る隆線の数を照合する技術を導入した、指紋認証システムもあります。一般的な特徴点の位置や方向の照合方式に「リレーション」をプラスすることによって、高度な照合精度を取得し、信頼性の高い指紋認証システムを実現することが可能です。指紋認証システムの認証を行うときの照合時間が早く、平均照合時間は0.3秒です。パスワードを入力する場合と比べると、指紋認証の照合する時間がスピーディーであることがわかります。指紋認証システムを複数人が利用するオフィスや工場などで導入すると、朝の混み合う出勤時間も円滑に通過することができます。