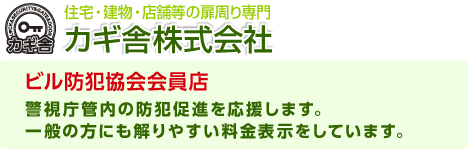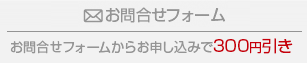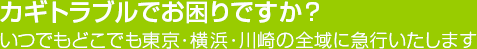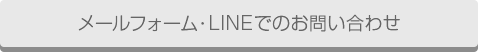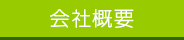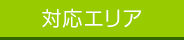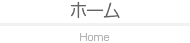KJTECHの暗証番号認証とカード認証リーダー
近年は、セキュリティ性の向上や内部情報の保護管理などの観点から、オフィスへの入退室管理システムの導入が一般的になりつつあります。防犯性の高い電気錠のなかでも、比較的コストを抑え設置できる暗証番号認証やカード認証リーダーは、多くのオフィスで導入されています。この記事では、オフィスにおけるカギ管理の必要性や電気錠の種類、韓国に拠点を置くKJTECHの暗証番号認証リーダーやカード認証リーダー、KJTECHリーダーの導入事例などについてご紹介します。

◎オフィス対するカギ管理の重要性
近年の調査によると、日本のオフィスの数は年々増加傾向にあると言われています。現在の国内の企業法人の数は約178万社、従業員10人以上の規模に絞って見ると約44万社であるとされています。以前行った調査の結果と比較すると、全体としては約7万社の増加、従業員10人以上の規模については約2万社の増加となっています。このことから、日本のオフィスは今後さらに増加することが予想されます。オフィスには、多くの社員や従業員が出入りをしています。事務所には金庫のほかにもノートパソコンやデスクトップパソコンなどの機器もあります。規模の大きいオフィスになると、機密情報や個人情報が保存されている部屋があり、パソコン内部には顧客情報など貴重な情報が多く残されています。オフィスには、社員のほかにも宅配業者や清掃業者など日々多くの人が出入りしています。多くのオフィスは、夜間や休日にはスタッフがいないため、事務所荒らしの被害に見舞われたり外部に情報が流出しないように、出入口にカギをかけることでセキュリティ性を高めることが重要となります。

◎カギ管理のミスがトラブルの引き金に
オフィスにおいて一般的な金属製のカギを使用している場合、セキュリティ面においてあげられるリスクがカギの紛失です。多くのスタッフが在籍しているオフィスの場合、金属製のカギを人数分用意しなければならないことが多々あります。カギはそれぞれ個人で保管しなければならず、外出先でカギを失くしてしまうリスクが常に伴います。ひとりがカギを紛失すると、防犯面からシリンダーごと交換しなければならなくなり、人数分のカギを再び作成するコストや手間がかかります。カギの閉め忘れも、オフィスで起こりがちなトラブルです。オフィスを最後に退社する者が出入口を施錠するようにルールを定めていても、どうしても忘れてしまうケースや自分のほかにもまだ人がいると思い込み、カギをかけない事例が発生してしまいます。管理責任者にとってカギを管理するのは負担が大きく、オフィスのカギを紛失してしまった場合などの対処や、マスターキーの取り扱いなども慎重に行わなければならずストレスにつながります。スタッフが休日出勤する場合などにも、カギの施錠確認を行わなければなりません。このようなオフィスにおけるカギ管理に関するトラブルは、KJTECHの暗証番号認証リーダーやカード認証リーダーなど、電気錠による入退室管理を行うことでリスクを軽減できます。
◎入退室管理システム導入のメリット
入退室管理とは、オフィスにおいていつ誰が出入り口を利用したか、どの部屋に入室したかを管理して記録するシステムです。KJTECHの暗証番号認証やカード認証による入退室管理システムをオフィスに導入することにより、社員の出入りの管理業務を円滑に行えます。入退室管理に加えて勤怠管理も行えるため、残業や休日出勤、有給取得などを正確に把握でき社員の勤務管理に役立ちます。これらの認証システムを活用し入退室管理を行えば、入室を許可されていない人物を含めて2人以上で連れ立って部屋に入る、いわゆる共連れ防止にも効果を発揮します。また、夜間や休日に無人の社内に何者かが侵入しようとした場合でも、カードを持っていなかったり暗証番号を知らない人物はオフィス内に入ることはできません。暗証番号認証やカード認証リーダーと一緒に防犯カメラを設置しておけば、録画記録から不正に侵入しようとした人物の特定につながり、入退室管理システムをセキュリティ面から強化することができます。ほかにも、KJTECHの暗証番号認証やカード認証による入退室管理を採用することで、入館チェックを行う警備員配置にかかる人件費も削減できます。

◎電気錠における解錠の種類
電気錠には、KJTECH製品にもある暗証番号認証キーやカード認証キー、リモコンキー、生体認証のひとつでもある指紋認証など、さまざまな種類があります。暗証番号認証の電気錠は、決められた暗証番号を入力することで解錠できます。カード認証は、カードキーをドア付近に設置されているリーダーに差し込んだりかざすことでカギを解錠するタイプになります。リモコンキーは、リモコンキーのボタンを押したりドアに近づいたりすることでカギを解錠します。電気錠がリモコンキーから送られる電波を受け取ることにより、ドアのカギが解錠する仕組みとなっています。その都度カギをバッグから取り出す必要がなく、ポケットのなかからリモコン操作ができるので手軽に利用できます。生体認証は人間の指紋や顔など身体的特徴を活用してカギの解錠を行う仕組みとなっています。多く普及している指紋認証キーは、あらかじめ登録しておいた指紋をリーダーに読み取らせることにより、本人確認ができドアを解錠します。KJTECHでは、指紋認証のリーダーを開発し市場に流通しています。顔認証は、人の顔の特徴や目や鼻の位置、輪郭などから本人かどうかチェックしてカギを解錠します。KJTECHの顔認証であればマスクを着けていても認証が可能です。静脈認証は、手のひらの血管の形や方向などから本人かどうか確認します。虹彩認証は、目のなかの虹彩のしわの数や形などにより認証を行うもので、両目でも片方の目のみでも認証を行うことが可能です。音声認証は、人間の声の周波数の違いを判断して認証します。電気錠であるKJTECHの暗証番号認証やカード認証リーダーは、使用する上で多くのメリットがあります。
◎暗証番号認証とカード認証のメリット
KJTECHのカード認証リーダーのメリットは、ドアにカギ穴が必要ないため、事務所荒らしがよく使う手口であるピッキングの被害を避けられることがあげられます。カード認証キーは、リーダーにカードをかざしたりするだけで解錠できるため、解錠の際にカギ穴に差し込む手間がないためスムーズに行えます。またカード認証キーは薄くてコンパクトなため、財布やパスケースに入れて持ち運ぶことができることから、カードを紛失するリスクを軽減できます。金属製のカギは簡単に複製できるものが多いですが、KJTECHのカード認証キーは、複製することが難しいとされています。KJTECHのカード認証キーを紛失した場合でも、そのカードをすぐに無効にできるため、拾った人物に悪用される不安がありません。新たにKJTECHのカード認証キーを発行すれば、シリンダー交換などの手間もなく再びドアを解錠することができます。KJTECHの暗証番号認証キーは、オフィスの人数分のカギを用意する必要がなく、利用人数が増えても暗証番号を共有するだけで良いため、コストパフォーマンスに優れています。外出時にカギを持ち歩く必要がなくカギを失くすリスクがないことは、KJTECHの暗証番号認証キーの大きなメリットと言えるでしょう。暗証番号認証リーダーには、数字の入力を一定回数以上間違えると自動的にロックされる機能を備えているものもあり、この機能があれば番号を知らない部外者に不正に解錠される心配がありません。KJTECHの暗証番号認証キーは、後から暗証番号を変更することができるため、高いセキュリティ性を保つことができます。KJTECHの暗証番号認証やカード認証キーは、オートロック式となっています。オートロックとは、ドアを閉めるだけで自動的に施錠される仕組みのことであり、カギのかけ忘れを防ぎセキュリティ性を高められます。暗証番号認証とカード認証リーダーは日本だけでなく海外でも開発されています。その企業のひとつが、韓国に本社を置くKJTECHです。
◎セキュリティに強いKJTECH電気錠リーダー
韓国はアジアの国々のなかでも、特にセキュリティ大国であると言われています。韓国では住民登録証の発行手続きの際に、すべての市民について両手の指の指紋登録制度が義務化されています。韓国では、指紋のほかにも生年月日や性別、出生地などが記載されている住民登録証の保持が義務づけられています。これは、人口統計のほかにも徴兵義務のある韓国において軍事政権下の住民統制や、北朝鮮のスパイを探し出すという目的からであるとされています。韓国では2011年に出入国管理法を改正しており、2012年からは入国審査の際に日本人観光客を含む17歳以上の外国人すべてを対象に、原則として顔写真の撮影と指紋の採取を義務付ける制度を導入しています。そんなセキュリティ意識の非常に高い韓国にあるKJTECHは、韓国国内だけではなくギリシャの政府機関やオマーンの石油工場など、世界各地にKJTECHの製品を流通しています。日本においては、正規代理店がKJTECHの暗証番号認証やカード認証リーダー、生体認証を取り扱っています。2011年に個人事業者として設立されたKJTECHは、2012年には株式会社KJTECHとして法人化し、ベンチャー企業として敷設研究所を設立しています。KJTECHでは、暗証番号認証やカード認証、生体認証システムの構築を行っています。そのほかにも、画像監視システムなどの統合セキュリティシステム構築事業、HID RF Readerサプライ事業、対テロ防止システム構築事業、自動ドア構築事業、侵入検知システム、パトロール管理システム、外郭監視システムなど多くの事業を展開しているのがKJTECHの特徴となっています。KJTECHの暗証番号認証やカード認証などのリーダーは、韓国政府の国防施設や国会議事堂、大統領官邸など重要な施設にも採用され高い評価を受けています。仁川警察庁捜査洞、研修警察署などの各警察署や金浦私病院や請求聖心病院などの医療施設、世宗発電所や仁川発電所など国の重要機関にもKJTECH製品が導入されています。日本の企業である富士ゼロックスは韓国にもありますが、KJTECHは韓国内の富士ゼロックスの複合機指紋およびカードリーダーの開発にも携わっています。そんなKJTECHには、優れた機能を備えた暗証番号認証やカード認証リーダーがあります。

◎KJTECHの暗証番号認証とカード認証リーダー
KJTECHのHID Signoシリーズの暗証番号認証やカード認証リーダーには、「HID Signo20」「HID Signoキーパッドリーダー20k」「HID Signo40」「HID Signoキーパッドリーダ40k」などの製品があります。アクセスコントロール向け認証システムであり、オフィスの入退室管理などに最適なKJTECHのリーダーには、多くの優れた機能が搭載されています。KJTECHであれば、低コストでオフィスに入退室管理システムを構築することができます。KJTECHの暗証番号認証とカード認証リーダーであるHID Signoシリーズは、本体はブラックで固定ケースはシルバーとなっています。どのKJTECH製品もシンプルなデザインでコンパクトなサイズであるため、設置場所を選ばず、高いセキュリティ性と使いやすさ、デザイン性を備えているのがKJTECH製品の特徴となっています。KJTECH「HID Signo20」とKJTECH「HID Signo40」のサイズは4.5cm×12.2cm×2.0cmです。これらのKJTECH製品はICカード認証に対応しています。KJTECHの「HID Signo20k」とKJTECH「HID Signo40k」はサイズが8.0cm×12.2cm×2.0cmです。暗証番号認証やカード認証に対応しているKJTECHのHID Signoシリーズは、ブラックの本体に赤い文字で数字が表示されるため暗い場所でも見やすく暗証番号を入力しやすくなっています。暗証番号認証とカード認証以外にも、KJTECHのHID SignoシリーズはiPhotoやAndroidなどのスマートフォン認証にも対応しています。KJTECHのHID Signoシリーズのカード認証リーダーには、FeliCa(フェリカ)やMifare(マイフェア)などのICカードのほかにも、HID Seos, iCLASSも使用可能です。KJTECHのカード認証に使用されているFeliCaカードは、日本の企業であるソニーが開発したICカードであり、1枚のカードにICチップとアンテナを搭載しています。KJTECHのカード認証対応のリーダーにかざすと、約0.1秒でデータの読み取りができます。FeliCaカードは非接触形式のカードであるため、パスケースに入れたままKJTECHのカード認証に利用できるので衛生面も安心です。そのためFeliCaカードは、日本において駅の改札口でSuiCa、ICOCA、PASMOなどの交通系ICカードや、コンビニエンスストアなどやショッピングセンターなどの電子マネーカードとして幅広く利用されています。一方KJTECH製品でカード認証可能なMifareカードは、海外に拠点を置く企業が開発したICカードです。カード認証に使用するカードとしては比較的安価であるため、オフィスの入退出管理や会員制店舗の会員カードとして広く活用されています。日本ではカード認証リーダーにおいてFeliCaカードが多く普及していますが、ロンドンや北京、ソウル、モスクワなどでは、公共交通システムでも利用されているように、世界的に見るとMifareカードの方が一般的となっています。KJTECHのカード認証で利用できるHID Seos, iCLASSは、テキサス州オースティンに本社を置くHID Globaが開発したICカードです。高いセキュリティ性と素早い認証性を備えた高周波非接触式カードとなっています。KJTECHのHID Signoシリーズは、カード認証の読み取り距離が長く、HID Seos iClass、Mifareは4cm〜10cm、HID Proxは6cm〜10cmとなっています。KJTECHのスマートフォン認証は、15cm〜2m離れた場所からでも可能です。そのためKJTECHの暗証番号認証やカード認証リーダーはオフィスの会議室やサーバー室、機密保管庫や非常口、屋外からの建物通用口の設置にも適しています。さらにオフィスビルやマンションの共用エントランスやエレベータ、エントランスのセキュリティゲート、ホテルや宿泊施設、学校などの教育機関や公共施設、空港や工場駐車場やゲートの入庫や出庫管理などにも、KJTECHの暗証番号認証やカード認証リーダーは導入されています。KJTECHの認証リーダーには、静電容量式タッチキーパッドを採用しています。KJTECH製品に導入されている静電容量方式とは、指とタッチキーパッドの間に発生する微弱な静電容量の変化からタッチ位置を検出する方式となっているため、水滴など水分によるKJTECHの誤作動が少ないことが特徴となっています。KJTECHの暗証番号認証やカード認証リーダーをインテリジェントパワーモードに設定すれば、KJTECHのカード認証リーダーが休止状態のときには、電力消費を削減することが可能となっています。キーパッド入力補助や入力時間延長、誤入力データ送信回避機能を搭載しているなど、KJTECHの暗証番号やカード認証リーダーのHID Signoシリーズは、視覚障がい者などさまざまな方が利用することを想定し開発されています。KJTECHの暗証番号認証とカード認証リーダーは、屋内や屋外を問わずさまざまな場所に導入可能です。保護等級はIP65となっているKJTECHの暗証番号やカード認証リーダーは、-35℃〜66℃という過酷な環境下でも使用できます。保護等級とは、機器の防塵、防水に関する保護を規格化したものを言います。KJTECHの暗証番号認証やカード認証リーダーであるHID SignoシリーズのIP65は、粉塵がKJTECHの機器内部に侵入せず、いかなる方向からの水の直接噴流を受けても有害な影響を受けないことを表しています。機能面に優れ利用しやすいKJTECHの暗証番号認証、カード認証リーダーのHID Signoシリーズは、日本でも多くの場所に採用されています。

◎暗証番号認証とカード認証リーダーの設置事例
○事務所の出入り口にKJTECHの「HID Signoキーパッドリーダー20k」を導入した事例
これまでは会社の全従業員にカギを渡していましたが、たびたび従業員がカギを紛失していました。その際は、シリンダー交換を行い新たなカギを作成して配布しなければならないため、想像していた以上にコストと手間がかかっていました。KJTECHの暗証番号認証リーダーのHID Signoキーパッドリーダー20kであれば、ICカードをかざしたり共有した暗証番号をテンキーに入力するだけで良いので、鍵の紛失や交換の必要がなくなり経費の削減につながりました。
○オフィスの入退室管理システムで暗証番号認証・カード認証リーダー「HID Signo40k」を導入した事例
社員の数が多く派遣スタッフもいて従業員の出入りが多いオフィスでは、事務所の移転に合わせて入退室管理システムの導入を決めました。コストを抑えつつ入退室の履歴管理と許可者以外の入室制限をしたいという要望から、KJTECHのHID Signoシリーズの暗証番号認証とカード認証リーダーを採用して、出入口と会議室などにKJTECHのHID Signo40kを設置しました。社員証を認証カードにして認証することで何枚もカードを持つ必要がなくなり、コスト削減にもなりました。
○カギ管理ボックスを廃止してKJTECHのHID Signoシリーズの「HID Signo40」を導入した事例
以前から使用していたカギ管理ボックスが古くなったため、オフィスのエントランスと機密情報の保存されている部屋に、KJTECH製品のカード認証リーダーを採用しました。経年劣化したカギ管理ボックスは故障がたびたび起こり修理に時間がかかるためコストがかかりましたが、KJTECH製品設置後にはトラブルもなく入退室管理もスムーズに行えるようになりました。認証に使用するカードは、社員証として首から下げる形にしたため、失くすリスクが軽減され社員のセキュリティ意識の向上にもつながりました。
○従業員数500名以上のオフィスにKJTECHのHID Signoシリーズのカード認証リーダー「HID Signo40」を導入した事例
現在オフィスに設置している入退室管理システムは認証が遅く、朝の出勤時間などに混雑が見られるのが課題でした。認証速度を上げるとともにセキュリティ対策を講じたいという理由から、KJTECHの製品を導入しました。KJTECHのICカード認証リーダー採用によりセキュリティ性が向上したことから、1秒以内のカード認証により認証速度をアップさせることができ、スムーズな入退室管理システムの構築が実現しました。
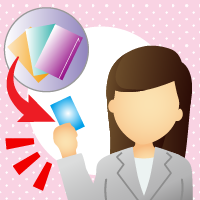
◎KJTECH製品の導入をする際の注意点
オフィスに入退室管理システムを導入する際には、各々の予算に見合った認証方法を選ぶことが重要となります。KJTECHの暗証番号認証リーダーやカード認証リーダーのほかにも、指紋認証や顔認証といった生体認証など、電気錠のリーダーにはさまざまな種類があります。生体認証のリーダーは比較的高額であるため、コストを抑えたいのであればKJTECHの暗証番号リーダーやカード認証リーダーを採用すると良いでしょう。KJTECH製品をはじめ、電気錠リーダーの電気錠の配線工事を行う際には、電気工事士の資格を持つ作業者が在籍している業者に依頼する必要があります。電気錠などカギに関して専門的な知識を持ち、電気工事士などの有資格者が多数在籍しているのがカギの業者です。KJTECHの暗証番号認証リーダーやカード認証リーダーを設置する場合は、電気錠に関する知識はもちろん、多くの実績を持つカギの業者に依頼するのが最適でしょう。候補の業者には、事前に見積り書を提出してもらうようにしてください。見積もりの依頼方法については電話やインターネット、メールなど業者によって異なります。業者にKJTECHの暗証番号認証やカード認証リーダーの見積り書を依頼する際には、見積り書の作成に関して無料であるかを確認しておきましょう。見積り書のみでも料金が発生する業者もあるため注意しましょう。見積り書は、ひとつの業者だけではなく複数の業者に依頼するようにしてください。2〜3社のカギ業者からKJTECHの電気錠リーダーの見積もり書を提出してもらい比較すると、取り付けにかかる費用の相場が明確になってきます。暗証番号認証やカード認証の電気錠リーダーの設置に関して事前に正確な料金を知りたい場合は、業者に連絡して取り付けるオフィスなど現場まで来てもらうと良いでしょう。 そうすることにより、その場でKJTECHの電気錠リーダーの設置について、料金がどの程度なのか知ることができます。作業内容についてわからないことがあれば、見積もり書を作成した業者に直接聞くのが1番安心でしょう。KJTECHの暗証番号認証やカード認証リーダーの取り付けの際にかかる出張費も、カギの業者を選ぶ際の重要なポイントとなります。カギの業者のなかには、あえてサイトに出張費についての情報を掲載していない所があります。優良なカギの業者が多いなか、KJTECHの電気錠リーダーや作業内容について詳しい説明がなく、高額な料金を請求する悪質な業者が存在しています。カギ業者のホームページなどに「出張費無料」「出張費○○円」などの具体的な記載が見当たらない場合は、KJTECHの暗証番号認証やカード認証リーダー設置にかかる出張費の有無について、電話などで直接問い合わせてみるようにしてください。業者を選ぶ際には、急に設置作業がキャンセルになった場合、キャンセル料がかからない業者を選んでおくことで、出費を抑えることができます。入退室管理に加えてセキュリティ強化を重視するために、KJTECHの暗証番号認証やカード認証リーダーにプラスして、監視カメラや防犯カメラの導入も検討すると良いでしょう。それらの防犯機器の設置についてもカギの業者に相談すれば、複数の業者に依頼する手間を省けます。KJTECHの暗証番号認証やカード認証リーダーの寿命についても把握しておくことも大切です。KJTECHなどの電気錠リーダーには耐用年数があります。日本ロック工業会では適切に保守・点検することで、安全上支障なく使用できる標準的な期間を耐用年数として表示しています。KJTECHを含めた一般的な電気錠リーダーの耐用年数は7年となっています。しかしこれはあくまでも目安であり、KJTECHのリーダーの使用頻度や設置場所などによりこれより短くなることがあります。そのため、KJTECHの暗証番号認証やカード認証リーダーの設置工事完了後も、カギ業者が一定の保証期間を設けているか、アフターフォローがあるかどうかも確認することが必要です。 KJTECHの電気錠リーダーの取り付け後、何らかのトラブルが発生してしまった場合、保証期間がないと再び料金が発生することになってしまい費用の負担がかる恐れがあります。万が一の事態に備えてアフターサービスを行っている業者を選ぶと安心です。 自社の技術や経験に自信を持っている優秀なカギ業者は、しっかりした保証を設けている所が多く見られます。業者の技術力や信頼性を見極める際のポイントにもなるため、KJTECHの暗証番号認証やカード認証リーダーを取り付けする際は、よく確認しておきましょう。

◎まとめ
東京に本社を置くカギの専門業者であるカギ舎では、KJTECHの暗証番号認証やカード認証リーダーの設置はもちろん、ほかの種類の電気錠や一般的な金属製のカギの修理交換など、カギに関するあらゆる相談や依頼に対応しています。KJTECHの電気錠リーダーの取り付けについては、年中無休で24時間対応のカギ舎にご相談ください。