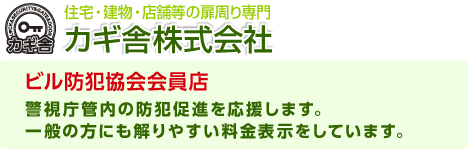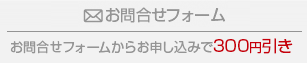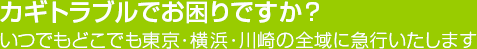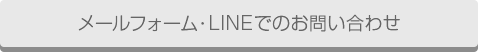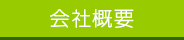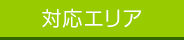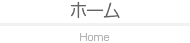自動ドアの鍵に適した防犯性の高い電気錠
今や私たちの便利な生活に欠かせない自動ドアですが、古い鍵ではセキュリティ面に不安があります。自動ドアに電気錠の鍵を導入することで、空き巣など不審者の侵入を防ぎ建物の安全性を高められるだけでなく、遠隔操作で施解錠ができるなど利便性が格段に上がります。電気錠は、既設の自動ドアに後付けで導入することも可能なので、建物の防犯性を高めたいと考えているなら導入を検討すべきです。この記事では、自動ドアの仕組みと電気錠を導入するメリットなどご紹介します。
◎自動ドアのタイプ
自動ドアの歴史は古く、日本では昭和初期からすでに使われていたとされる記録が残っています。もともとは物を持っていて手が使えない場所に設置されることを目的としていた自動ドアでしたが、生活水準が少しずつ上がっていくなかで、「施設の扉をより快適に便利に利用したい」という需要が高まり、今のような形に進化を遂げてきました。一般的に自動ドアとは、人が直接触れることなく開閉する仕組みの扉を指します。自動ドアにはさまざまな種類があり、商業施設やコンビニ、公共施設などでよく見かけるものは「引き戸(両引き戸)タイプ」です。2枚の扉が中央から左右に向けてスライドする仕組みになっており、両方の扉が同時に開くので間口が広がり、扉ですれ違う際にぶつかったりするリスクを軽減します。また、両引きタイプの自動ドアは大型の家具や電化製品などを搬入する際にも便利で、マンションの入り口や病院のエントランスなどで採用されています。中小規模の商業施設や店舗では、「引き戸(片引き戸)タイプ」の自動ドアが使用されている場合もあります。片引き戸タイプは、1枚の扉が横にスライドして開閉する仕組みの自動ドアで、横にスライドする仕組みのため、扉前後に開閉のためのスペースを開ける必要がありません。また突然扉が開くことで前後にいる人とぶつかったり怪我をさせるリスクを軽減します。ただし、引き戸タイプの自動ドアでは、扉の引き込み側で手などを挟まれる危険性がある仕組みのため、防護柵を設けるなど安全面にも配慮が必要になります。通常の自動ドアよりさらに間口が広いものとしては「二重引き戸タイプ」があります。二重引き戸タイプは開口部の扉が二重になっており、一般的な引き戸タイプの自動ドアより間口を約1.3倍に広げることで、開放感があり、かつ通り抜けしやすい出入り口を実現します。「回転ドアタイプ」の自動ドアは、かつて商業施設や公共施設などでよく見かけたのではないでしょうか。防寒を目的にヨーロッパで誕生した回転ドアは、扉が円筒形に回転する仕組みによって室内を常に密閉された状態に保つことができ、風が入りにくい、温度調整がしやすくなるなどのメリットがあります。一方で、回転ドアに挟まれる事故などが多発した影響もあり、現在ではあまり見かけなくなりました。自動ドアのそのほかの種類として、引き戸タイプの扉を通常の2倍に全面開放する仕組みの「ワイドオープンドア」、曲面構成の入口などデザイン性の高い場面で利用される「円形戸」などがあります。自動ドアは、センサーが人や物を感知すると自動的に扉が開閉する仕組みであり、不特定多数の侵入が可能となるためセキュリティ面に不安が残ります。そのため自動ドアには鍵をかけますが、従来の棒鍵よりも防犯性の高い電気錠を導入すれば安心です。電気錠とは電気の力で扉の鍵を施解錠する仕組みで、自動ドアとの相性も非常に良いです。電気錠は、扉の施解錠にカードキーや暗証番号入力、生体認証、スマートフォンなどさまざまな方法を選べるほか、キーを紛失した際の停止や再発行も簡単に行えるというメリットがあります。自動ドアに取り付けられる電気錠には、設置場所や使いやすさに対応して「ラッチタイプ」「デッドボルトタイプ」「歯付電磁ブレーキタイプ」があります。

◎自動ドアの仕組み
自動ドアはさまざまな部品から構成されており、各装置が電気的に連動して作動する仕組みになっています。自動ドアの扉はワイヤーやベルトによって上から吊り上げられており、開閉の制御はドアオペレーターと呼ばれる制御部分が行っています。自動ドアが開くためには、まずセンサーが通行人や物を感知し、ドアオペレーターへ信号が送信され、ドアエンジンと減速機がタイミングベルトと従動プーリーを動かすという流れによって実現しています。
〇センサー
センサーは、人や物を感知して信号を送ったり、自動ドアの開閉をスムーズに行うために周辺を監視する仕組みの装置です。自動ドアに装備されているセンサーは「起動センサー」「補助センサー」と「保護センサー」の3種類があります。「起動センサー」は、文字通り自動ドアが起動しドアを開けるためのセンサーです。起動センサーのうち、天井に取り付けるタイプの「光線反射方式」、無目に取り付ける「電波方式」は、赤外線や電波を反射させることで人や物を検知し、自動ドアを開ける仕組みになっています。一方の「タッチ方式」は、ドアにタッチプレートを設置したり、ドア自体に手を近づけることで自動ドアが作動する仕組みです。そのほかに、テンキースイッチや押しボタンなどの起動装置によって自動ドアが開く仕組みもあります。「補助センサー」は、起動センサーの補助的役割を果たし、扉を通過している人や物、扉付近で立ち止まった人が扉に挟まれないよう制御する仕組みのセンサーです。補助センサーのうち「光電方式」は左右の方立に投光器と受光器が設置されており、その間を通っている間は扉が閉じないようする仕組みとなっています。「光線反射方式」は、無目に取り付けて赤外線の反射が人や物を検知し続けている間は扉を閉じないという仕組みで、同じく無目取り付けの「超音波方式」は超音波を発射することでエリア内の人や物を感知し扉を開けたままにしておけます。いずれの方式も、扉が閉じる動作の途中で人や物を検知すると、自動的に反転動作を行って全開するように制御されています。「保護センサー」は、扉を通過中の人や物などが扉に接触しないように監視するセンサーです。「光電方式」と「光線反射方式」の2種類があるほか、起動センサーの仕組みを兼ね備えた種類のものもあります。保護センサーは扉開閉のたびに自動ドアの自己診断を行い、異常を検知すると扉を全開あるいは全閉、あるいは減速するなどの動作を行って利用者の安全を保護しています。「自動ドアの開閉回数が多く部屋の冷房が効きにくい」などの問題に対応するため、昨今の自動ドアは人や物の動き・方向を検知する機能が充実しており、人が扉に向かう動作をした場合のみ開閉することで省エネルギーを実現しているものも見られます。
〇ドアオペレーター
ドアオペレーターは、コントローラーとドアエンジン、ドアハンガー、ベルト、従動プーリーなどから構成されており、ランマや無目など自動ドアの上部に設置される制御装置です。ドアハンガーが自動ドアを支え、端に設置されているドアエンジンがワイヤーを引き、従動プーリーと呼ばれる滑車がワイヤーをスムーズに動かすことによって自動ドアが開きます。コントローラーは自動ドアの頭脳とも呼ばれる重要な部分で、あらかじめ扉の移動距離を記憶し、モーター速度の「始め」「途中」「終わり」それぞれで微調整を行って開閉時の安全を確保しています。ドアエンジンは自動ドアを開けたり閉じたりする動力部で、重たい扉をスムーズに開閉したり、危険と察知した場合は動きを止めるパワーと反応速度を有しています。
〇扉部分
自動ドア扉部分の一般的な仕組みは、開閉しないFIX(フィックス)と呼ばれる固定された建具と実際に開閉する引き戸があり、床面にはガイドレールが敷かれています。扉の下には「振止め」という部品が付いており、ガイドレールから扉が外れたり軌道外に飛び出さないようになっています。ガイドレールにゴミや石などが挟まったりすると故障の原因になるため、常に掃除して物が詰まらないようにしておくことが大切です。扉の中央下部にある錠前は扉を手動で施解錠できる仕組みですが、自動ドアに電気錠を導入すれば遠隔からの施解錠も行えるようになります。

◎自動ドアの鍵に電気錠を導入するメリット
棒鍵など古いカギを使っている自動ドアは、空き巣などに侵入される危険があるためセキュリティ面が懸念されますが、自動ドアに電気錠を取り付けることで被害に遭うリスクを軽減できます。電気錠は電気の力によって施解錠を行うため、人の手による鍵の管理と比べセキュリティは高いといえます。自動ドアの鍵が物理的な場合、開閉の際は扉の前に必ず人がいる必要がありますが、電気錠によっては遠隔操作ができる製品もあるため、利便性が格段に向上します。また物理的な鍵ではどうしても鍵の閉め忘れが発生する危険性がありますが、電気錠であれば自動的に扉がロックされる仕組みなので防犯面においても安心です。自動ドアに電気錠を導入すれば、カードキーや暗証番号、生体認証、スマートフォン認証などの仕組みによって、キーレスにドアの開閉を行うことができ、自動ドアの存在を大きく意識することなく通行ができるようになります。また電気錠と入退室管理システムを連動させれば、オフィスの出入り口などで勤怠管理なども簡単に行うことができます。マンションのエントランスでは敷地の外から建物内へ入るときのみ電気錠の認証を行い、建物内から外へ出るときは認証なしにするといった仕組みも可能で、設備によって利便性とセキュリティを兼ね備えた運用ができます。また電気錠の認証を非接触で行うことにより、衛生管理にも大きく貢献します。


◎停電時の自動ドアの解錠方法
停電時には、自動ドアの電気錠はすべての機能が利用できなくなるので注意が必要です。自動ドアに付いている停電時の動きは、電気錠の種類によって「停電する前の状態が保持される」「自動的に施錠される」「自動的に解錠される」のいずれかになります。停電時に備えて、あらかじめ電気錠の停電時の動きについて説明書等で確認しておくようにしてください。停電時に自動ドアを通りたい場合、まず扉を手動で開けてみてください。停電時に解錠状態になる仕組みの電気錠であれば、そのまま扉を開けて通ることができます。手動で扉が開かなければ電気錠が自動的に閉まっている状態なので、別の方法で扉を開ける必要があります。自動ドア装置からワイヤーが垂れているなら、ワイヤーを引いている間だけ電気錠が解錠状態になり、手動で扉を動かすことができるようになります。もしワイヤーがなければ、自動ドア装置のボックス内に隠れているかもしれないので探してみましょう。それでも見つからない場合は、自動ドアのメーカーか管理会社に連絡してください。防火自動ドアであれば、電気錠を手動で開けた後ゆっくり扉が閉まります。これは、火災発生時に被害の拡大を防ぐための仕組みとなっています。防火自動ドアのなかにはハンドルが付いているものがあり、その場合は「くぐり戸」と呼ばれる扉が手動で外側に開く仕組みです。自動ドア設置時のタイミングで電気錠を導入している場合、火災報知機や地震感知器と電気錠との連動が行われるため、非常時の避難経路は安全に確保された状態になっています。しかし自動ドアに後付けで電気錠を導入した場合、非常時に火災報知機などと動作が連動していない場合があるため、注意が必要です。電気錠の説明書等で非常時の動きを確認して、必要な対策を行いましょう。停電発生時には、電気錠の「パニックオープン」という仕組みが役に立ちます。パニックオープンは、地震や火災など非常事態が発生した際に、電気錠の扉を自動的に全開放するシステムで、介護施設やマンション、病院などに設置されることが多いです。停電時で非常電源に切り替わった場合でも作動するので、「非常時に電気錠の扉が開かない」という事態を防ぐことができます。商業施設や公共施設など大人数の人が一度に避難行動を取った際、あるいは病院や福祉施設など避難に時間を要する場合でも、安全に確実に電気錠を解錠し避難経路を確保できる仕組みになっています。また、緊急時に消防隊員が迅速に救出活動できるように通路を確保するという意味合いもあります。

◎まとめ
自動ドアに電気錠を導入することで、セキュリティ性が向上するだけでなく、利便性を高めたり衛生管理にも役立ちます。電気錠は電気の力で動いているため、停電時には使用できなくなるので注意が必要です。あらかじめ電気錠の停電時の動きを確認し、緊急時でも安全に利用しましょう。電気錠の取り付けや交換は、お気軽にカギ舎へご相談ください。