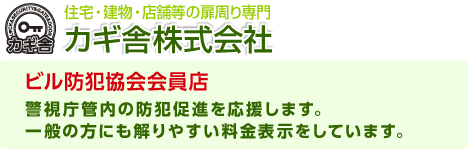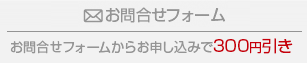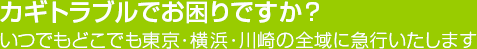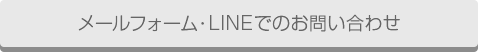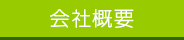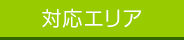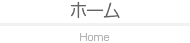扉に後付け可能な電気錠と入退室管理システム
住宅の玄関やオフィスのエントランスには、電気の力で解錠される電気錠が設置されている場合があります。電気錠は、はじめから金属製のカギで施解錠を行うシリンダー錠が付いている状態でも、扉に後付けすることが可能な製品があります。この記事では、扉に後付け可能な電気錠の仕組みや入退室管理システムとの連携、認証の種類や電気錠を後付けする際の注意点についてご紹介します。
◎扉に後付けできる電気錠
電気錠とは、電気の力によりドアのカギの施錠や解錠ができる錠前で、はじめから取り付けられていることもありますが、扉に後付けすることも可能です。電気錠を設置するためには、電気の配線工事を行う必要があります。電気錠は、本体と操作部分、制御部分の3つで構成されています。電気錠の本体は扉に取り付けられているもので、電気錠の操作部分は、暗証番号認証やカード認証など実際に操作を行い扉の解錠を行います。操作部分は、電気錠の本体の近くに取り付けられていることが多いです。たとえば、ICカードを利用するカード認証の場合は、カードのデータを読み込ませるリーダーが操作部分にあたります。電気錠の制御部分は、電気錠本体と操作部分に電気を送るとともに正しく作動するようにコントロールする役割を担っています。電気錠の機能にはいくつか種類があります。MIWAの場合、Aモードと呼ばれている電気錠の閉扉自動施錠機能とは、扉が閉まると自動的に施錠する機能で、1回解錠と連続解錠があります。電気錠の1回解錠は、操作部分の解錠ボタンを押すと電気錠が解錠します。 扉の内側にあるサムターンを回して解錠した場合は、一旦ドアを開け再び閉めると施錠されます。電気錠の連続解錠は、1度操作部分の連続解除ボタンを押すと再びもうボタンを押すまで扉が解錠されたままの状態となります。 連続解錠に設定されている電気錠は、サムターンを回しても施錠されません。施解錠繰り返し機能にはBモードとEモードがあります。Bモードは、電気錠の施錠と解錠を交互に繰り返します。電気錠の解錠ボタンを押すと電気錠が解錠し、施錠ボタンを押した場合は解錠されている電気錠が施錠します。サムターンを回しても施錠と解錠が可能です。電気錠を解錠した際にのみ閉扉自動施錠機能が作動する状態をEモードといいます。Eモードの状態でサムターンで扉を解錠した場合には、ドアを閉めても解錠された状態となります。施錠する場合には、サムターンを回すか操作部のボタンを押します。電気錠はさまざまな種類の扉に後付けできます。前後に開閉する開き戸のほかにも、電気錠の種類によっては左右に引いて開ける引き戸にも設置が可能です。電気錠は門扉にも後付け可能で、雨風を受けても利用できる防水性を持つ屋外用の製品もあります。店舗やオフィスの自動ドアにも、電気錠を後付けできます。自動ドアは、扉の上部に設置されたセンサーが人や物を認識すると、開閉をコントロールしている制御装置へと信号が送られます。扉のエンジンやタイミングベルトが作動することにより、自動ドアが開きます。電気錠を設置すればピッキングされるリスクが軽減されるため、夜間など人がいない時間帯にもセキュリティ性を高められます。電気錠を扉に後付けする大きなメリットは、建物のセキュリティ性が向上することにあります。扉に後付け可能な多くの電気錠には、ドアを閉めると自動的に施錠するオートロック機能が搭載されています。金属製のカギを利用している場合、カギの閉め忘れのリスクがあります。施錠忘れは建物内への不審者や窃盗犯の侵入のリスクが高まりますが、オートロック機能があればカギの閉め忘れの心配がなくなります。物理的なカギは持ち歩く必要があるため、外出先での紛失のリスクも懸念されます。拾ったカギを第三者に悪用され建物内に不正に侵入される可能性があります。カギを紛失してしまうと扉についているシリンダーごと交換しなければならず、費用も手間もかかります。戸建て住宅の場合、子どもにカギを持たせている場合は落として失くしてしまわないか心配が常に伴います。扉に電気錠を後付けしてカギを持ち歩かなくて良い解錠方法にすれば、カギを紛失するリスクがなく安心です。

◎入退室管理システムとの連携
建物やオフィスの出入り口や特定のエリアにおいて、部屋への人の出入りを管理できるのが入退室管理システムです。入退室管理システムを導入すると、いつ、誰が、どこに出入りしたかを正確に記録することができるので、防犯性の向上が実現します。オフィスであれば、個人情報や機密情報の保管室、サーバー室など各部屋ごとに入室の権限を設定することにより、外部からの侵入による重要な情報の持ち出しなどの不正を未然に防げます。電気錠による入退室管理システムの導入は、内部不正を防ぐことにも役立ちます。入退室管理システムにより各エリアの入退室の履歴を把握できれば、特定の時間帯にどの人物がいたのかを迅速に特定でき情報の持ち出しなどを防げます。電気錠による入退室管理システムの採用は内部不正の抑止力にもつながります。防犯カメラやアンチパスバックなど、ほかのシステムとの連携により1度の認証で2人以上が入室する共連れを防止することが可能です。入退室管理システムの電気錠の解錠履歴により不法侵入が発覚した場合には、警報を発したりランプを表示して知らせることができます。電気錠による入退室管理システムと人事管理のシステムを連携させることにより、オフィスにおいて従業員の出勤・退勤時間から勤務時間を正確に把握する勤怠管理が可能となります。時間外労働をリアルタイムで把握することにより、慢性的な長時間労働や不要な残業を管理できるようになります。以前は多くの企業でタイムカードを採用していましたが、押し忘れや不正打刻が大きな問題となっていました。入退室管理システムを導入すれば、不正行為を防ぐこととともに、月々の給与計算のため行っていた月末の事務処理を合理化でき人的な計算ミスも防げます。扉を後付け可能な電気錠の入退室管理システムには、スタンドアローン型とネットワーク型の2つのシステムがあります。スタンドアローンタイプは、電気錠コントローラー本体に入退室のデータを記録して保存できます。パソコンを介してネットワークに接続しなくても利用できることがメリットとなっています。電気錠コントローラー本体に保存されたデータは、USBなどを使いデータを取り出しパソコンで確認が行えます。クラウド型は、ネットワークを活用することにより各々の部屋への入退室履歴を管理することが可能です。オフィスの複数の場所に認証機器が導入されている場合、1台のパソコンから入退室管理システムの認証の履歴をチェックできます。オフィスなどに本社以外にも支店がある場合は、遠隔操作により本社にいながら、電気錠の施錠や解錠ができ入退室記録を一元管理できます。

◎入退室管理システムの認証技術
電気錠と連携可能な入退室管理システムは、さまざまな認証方法があります。カード認証は、扉付近に後付けした認証機器にICカードをかざす、差し込む、スライドして解錠します。万が一、カードを紛失した場合でも、カードを無効化して新たに再発行することができるため、失くしたカードを悪用される心配がありません。リモコンタイプの電気錠は、リモコンのボタンを押すことにより操作部分が電波を受信して扉のカギを解錠します。バッグなどからその都度取り出す必要がなく、ポケットのなかからでもリモコンを操作できます。暗証番号認証は、0から9の数字を組み合わせて暗証番号を設定し、扉付近に設置した認証機器に打ち込み解錠します。カギなどを持ち歩かなくて良いため失くす不安がありません。人間の体の一部を使用した電気錠の生体認証には、指紋認証や顔認証があります。パソコンやスマートフォンのロック解除にも顔認証や指紋認証は活用されています。 扉に後付け可能な電気錠の指紋認証タイプは、事前に登録した指紋を認証機器にかざして解錠する方法です。指紋認証はセンサーに指を載せるのみで認証ができるため、スピーディーに利用できます。登録した指紋でしか認証することができず、複製が困難であるため非常にセキュリティレベルが高いといえます。指紋は年齢を重ねても形がほとんど変化しないため、経年変化の影響を受けにくいのも特徴です。そのため、1度認証機器に指紋を登録すれば登録したデータを長期間に渡り使い続けることができます。顔認証は、顔認証機器に顔を向けることにより本人確認を行い扉を解錠します。カメラの前に立つと認証でき、直接認証機器に触れる必要がないため、気軽に利用でき衛生的です。 荷物などで両手が塞がっている場合でも、問題なくスムーズに利用できます。マスクをしていても認証可能な顔認証機器であれば、その都度外す必要がありません。扉に後付けできる電気錠の認証方法は、1種類のみではなく複数の方法を組み合わせることが可能です。扉に後付けできる電気錠のカード認証と指紋認証を組み合わせて使用すれば、セキュリティ性の向上につながります。


◎電気錠を後付けする際の注意点
現状の扉に後付けで電気錠を設置する場合には、配線工事が必要となります。電気錠の配線工事を行う場合、電気工事士の国家資格が必要です。カギの業者など、電気工事士が在籍している所に扉への電気工事の取り付けを依頼するようにしましょう。電気錠は電気の力で動作を行う機器です。落雷などの影響により停電すると、扉に後付けした電気錠が使用できなくなることが考えられます。停電時の電気錠の動作については、電気錠の種類ごとに異なります。扉に後付けした電気錠が停電した際にどのような状態になるのかを事前に知っておくことで、非常時に対応しやすいでしょう。電気錠のなかには、停電時に自動的に扉が解錠される通電時解錠型の製品があります。非常解錠用のシリンダーが付いている電気錠であれば、物理的なカギを使用して扉を解錠できます。 非常時に備えて普段からバッグなどにカギを入れて持ち歩くことで、建物からの閉め出しや閉じ込めを防げるでしょう。扉に後付け可能な電気錠の耐用年数は、一般的に7年程度とされています。入退室管理システムや防犯カメラなどセキュリティに関わるシステムについては、法定耐用年数が6〜8年と定められています。ただし耐用年数はあくまでも目安であり、扉に後付けした電気錠の使用頻度や設置環境によっては、それよりも早めに劣化したり交換が必要になるケースがあります。扉に後付けした電気錠を長く使い続けるためには、カギの専門業者などにより定期点検やメンテナンスを行うことが重要です。

◎扉に後付け可能な電気錠の導入事例
カギを持ち歩く必要がないため、セキュリティに優れた電気錠は多くの場所で採用されています。入退室管理システムとの連携で、人の出入りが管理できるようになります。
○オフィスの出入り口の扉に電気錠を後付けした事例
セキュリティ性向上のため、あるオフィスビルの出入り口に電気錠を導入しました。解錠方法はカードを使用するカード認証を使用しました。入退室管理システムを導入して、電気錠のカードは社員証として使用できるようにしたため、入室がスムーズになり入退室の記録や管理も容易になりました。
○マンションのエントランスに電気錠を後付けした事例
マンションの大幅改修工事をきっかけとして、エントランスに電気錠を後付けで設置しました。これまでは金属製のカギを差し入れて解錠するシリンダー錠を採用していましたが、扉付近にある認証機器にカードをかざして解錠する方法を導入しました。カードは複製が難しく、万が一失くしてもすぐに無効化できるため、防犯性の向上につながりました。
◎まとめ
扉に電気錠を後付けする場合には、電気工事士による配線工事が必須となります。東京に本社を置くカギの専門業者であるカギ舎には、電気錠に関して豊富な知識と扉への後付けの経験を持つ作業者が在籍しています。「扉に後付けで電気錠を設置したい」「入退室管理システムを導入したい」場合は、24時間365日ご相談やご依頼に応じているカギ舎にご一報ください。