カギ舎株式会社
■本社
〒151-0063
東京都渋谷区富ヶ谷1-30-10
TEL:03-6454-1241
〒151-0063
東京都渋谷区富ヶ谷1-30-10
TEL:03-6454-1241
■事業所
杉並区和田1-25-3
杉並区和田1-31-3
中野ブロードウェイ422-2
杉並区和田1-25-3
杉並区和田1-31-3
中野ブロードウェイ422-2
東京商工会議所
杉並警察ビル防犯協会所属
杉並警察ビル防犯協会所属

【東京都】
中野区 新宿区 足立区 荒川区 杉並区 板橋区 江戸川区 大田区 葛飾区 江東区 品川区 渋谷区 世田谷区 台東区 中央区 千代田区 墨田区 豊島区 練馬区 文京区 港区 目黒区 北区 西東京市 三鷹市 調布市 武蔵野市 全域
【埼玉県】
和光市、新座市、朝霞市、戸田市、蕨市、川口市
【神奈川県】
横浜市 川崎市 全域
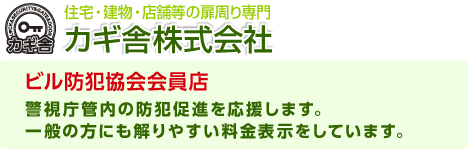
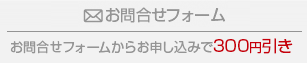

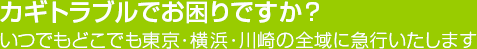

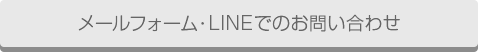
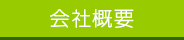
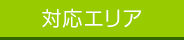
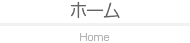




◎鍵を電気錠にしてセキュリティ強化