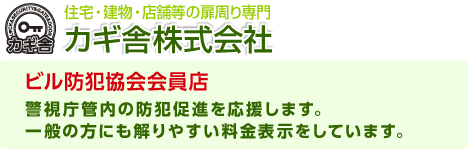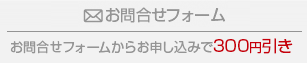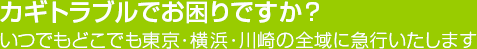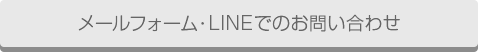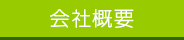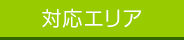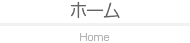既存のドアに電気錠は後付け可能
電気錠は物理的な鍵を持ち歩くことなく自動解錠ができるため、オフィスなどでよく見かけますが、最近では防犯対策として住宅にも電気錠を後付けするケースが増えています。電気錠にはICカード、スマートフォンなど、身近に使用しているものも鍵として利用することができ、電気錠を後付けすることで、セキュリティ面の強化と利便性の向上が見込めます。この記事では、電気錠の構造や後付けのメリットについて、また電気錠の後付けの事例や電気錠の選び方をご紹介します。
◎電気錠の構造
電気錠とは、電気の力を使ってドアを開閉する錠前のことです。電気錠の構造は電気錠本体・操作部・制御部の3つに分かれています。電気錠本体とは、扉の開閉やロックする役割がある錠前を指します。一般的な錠前と同じようにシリンダーがついているタイプや、鍵穴がついていないタイプなどさまざまな種類があります。操作部とは、鍵を開けるための操作をする部分で、電気錠を開閉する方法はさまざまな種類があります。ひとつの電気錠に対して、複数の操作部分を組み合わせて使うことも可能です。電気錠の操作部の種類にはICカード、ICタグ、リモコン式、タッチ式、スマートフォン、暗証番号、生体認証などがあります。ICカードキーは、交通機関で使用されるカードや、電子カード暗号化技術を玄関ドアや入り口に応用し、かざすことで施解錠できるタイプです。ICタグキーはドアに近づけるだけで施解錠でき、昨今では、ICタグに対応可能なキーホルダーやシールも増えています。ICカードやICタグは、万が一紛失したときでも、無効化して新たに再発行することができます。リモコン式はリモコンのボタンを押すと、電波を利用して扉を開閉します。タッチ式は、リモコンをバッグやポケットに入れていると、ドアをタッチするだけで施解錠することができます。スマートフォンは専用アプリをダウンロードすることで鍵として施解錠ができ、スマートフォンひとつで家族と鍵を共有することが可能です。暗証番号は、指定した数字の組み合わせを入力することで、施錠・解錠を行います。覗き見防止や一時的に発行できるワンタッチ暗証番号など、優れた機能を備えている電気錠もあります。生体認証には、顔を鍵として解錠する顔認証や、指紋の形状で本人と認識する指紋認証、黒目の内側にある虹彩という部分をスキャンする虹彩認証、静脈を認証して解錠する静脈認証、本人の声を鍵にする音声認識など、生誕認証は本人が鍵となるので鍵紛失のリスクがなく、セキュリティ面おいても優れています。制御部とは、操作部から送らせて来た信号を、電気錠本体に伝達する役割があり、電源の供給などもコントロールしています。操作部と制御部が一体型になっているタイプもありますが、基本的に電気錠の後付けする際には、電気錠本体・操作部・制御部の3つを取り付ける必要があります。

◎電気錠はさまざまな扉に後付けが可能
電気錠は古い扉、新しい扉に関係なく後付けが可能です。後付けできる扉の材質もさまざまで、スチール製やアルミ製、木製の扉にも対応しています。蝶番などを使用して扉を開閉するタイプの開き戸や、レールや溝の上を往復させて開閉する引き戸など、それぞれの扉に適した電気錠が販売されています。引き戸には、ドアの枠とぶつかる部分である「戸先」に取り付けるタイプと、引き戸と引き戸が重なる部分である「召し合わせ」に取り付けるタイプの2種類があります。また、門扉においては屋内・屋外関係なく後付けできる電気錠があるので天候を気にする心配もありません。電気錠は、不特定多数が出入りする宿泊施設や商業施設の自動ドアなどにも後付け可能なため、セキュリティ強化のために導入する施設が増加しています。しかし、電気錠を後付けするのに十分なスペースがないと、電気配線工事に加えて別途追加作業が発生したり、シリンダーと扉のハンドル位置が近いと後付けが難しい場合があります。電気錠を後付けする前に、設置する扉に電気錠が設置できるスペースがあるかが重要になります。ドアの厚みや錠ケースの先端から鍵穴の中心までの距離(バックセット)を確認しますが、電気錠の種類や製品によって対応できる厚みが異なるため、厚すぎても薄すぎても取り付けられないことがあります。扉の厚さは、おおよそ30〜60㎜の厚みがあれば対応できることが多いとされていますが、後付けする電気錠を選ぶ際は、製品カタログで対応扉厚などの記載を確認すると良いでしょう。バックセットと呼ばれる錠ケースの先端から鍵穴の中心までの距離は、38・51・64・76mmが好ましいとされています。また、電気錠を後付けする扉の錠ケース側面に印字されている型番を確認して、専門業者へ伝えると電気錠の選定がスムーズです。

◎電気錠を後付けするメリット
玄関ドアなどに電気錠を後付けするのは多くのメリットがあります。まずひとつめは、一般的な金属の鍵を外出するときに常に持ち歩かなくて済むことです。鍵を持ち歩くということは、紛失してしまうリスクが必ずついてきます。とくに、お子さんやご高齢の方であれば紛失する可能性が高く、1度どこかへ落としてしまうと探すのに時間がかかり、そのまま見つからない場合もあります。また、外出はしたものの、途中で鍵を閉めたか不安になり1度家に戻るも、しっかり施錠されていた…といった経験をしたことがある人は多いのではないでしょうか。鍵の閉め忘れの心配もオートロックで施錠する電気錠を後付けすることによって解消されます。電気錠を後付けすることは、空き巣や侵入窃盗などのピッキング対策としても非常に有効です。令和2年の侵入窃盗の被害が全国で21,030件発生したというデータがあり、これは1日あたり約58件の空き巣が発生しているということになります。侵入窃盗の被害にあった主な場所は、商店が43.1%、一戸建て住宅が23.9%となっており、鍵の閉め忘れ以外では、ガラスを破って侵入するケースや、ピッキングやサムターン回しで解錠し侵入しています。電気錠は耐久性が非常に高く、万が一壊されてもサムターンが回らなくなるなどの機能を備えているタイプもあります。空き巣は、侵入に5分以上かかる場合は諦めるというデータもあるので、電気錠を後付けすることで、空き巣被害に合うリスクが大幅に下がります。空き巣や侵入窃盗などの被害は例年減少傾向にありますが、オフィスや施設、戸建て住宅に電気錠を導入するなど、セキュリティ面が向上していることが背景にあると考えられます。
◎電気錠を後付けした事例
従来の鍵に比べて防犯性の高さや利便性を考慮して、既存の扉に電気錠を後付けする施設や住宅が増えています。ここでは、電気錠の後付け事例をご紹介します。
○マンションの室内扉
マンションの玄関だけでなく室内扉に電気錠を後付けする事例も増えています。リモートワークや在宅ワークなど、自宅で働くというライフスタイルが増加傾向にある現代では、自宅内で大切な書類を保管しなければならない場面も多くあります。すでに一般的な鍵が付いている場合であっても、毎日鍵の開け閉めをするのが手間だったり、子どもが何度も入ってきたりと、不便さを感じることも少なくありません。電気錠を後付けすることによって、開け閉めをする手間も省け、なおかつセキュリティ面でも安心です。
○シェアハウス
近年需要が高まっているシェアハウスにも電気錠を導入する事例が増えています。シェアハウスといえば、住人全員が共有するエリアとプライベートエリアの2つが存在しますが、プライベートエリアには必ず施錠できるドアが必要です。少人数のシェアハウスであれば、電子錠のほうが手軽に使えることが多いのですが、よりセキュリティを強化したいと、顔認証や指紋認証など生体認証の電気錠を導入するケースが増加しています。セキュリティ強化はもちろん、複数人で暮らす家なので、感染予防としての目的で、非接触で解錠を行える顔認証やQRコードの電気錠が注目を集めています。
○レンタルスペース
レンタルスペースは、遠隔操作によって施錠・解錠を行える電気錠の後付け事例が多くあります。日時を事前に予約して使用するレンタルスペースですが、電気錠を導入する以前は、予約日時に管理者がレンタルスペースへ出向き、ドアの解錠・施錠を行う作業が発生していました。しかし遠隔操作が可能な電気錠を後付けすることによって、無人での運用が可能となりました。電気錠を後付けしたレンタルスペースの扉と操作盤がオンラインでつながっているため、離れた場所からでも施錠・解錠ができる仕組みとなっています。レンタルスペースに暗証番号式のリーダーを導入した場合は、予約したと同時に暗証番号が自動発行されるシステムも増えてきています。レンタルスペースへの電気錠の後付けによって、管理者の鍵の受け渡しの手間を軽減することができました。
○オフィス
「部外者の侵入を防ぎたい」「セキュリティを強化したい」というオフィスには、入退室管理と連動した電気錠を後付けすることが可能です。時間帯や曜日によって出入りの権限を設定できるものや、部屋ごとの鍵を一元で管理できるもの、また来客者への鍵の共有をWeb上で行えるなど、管理やセキュリティに優れている電気錠はオフィスで多く導入されています。社員の勤怠管理をはじめ、誰が、いつ、どの扉を利用したのかなどの履歴も残るので、オフィス内の状況把握に役立ちます。ICカードや生体認証などの機器と組み合わせることで、本人確認をより明確に行えるので「なりすまし」や部外者の侵入を防げます。オフィスで働く従業員は、導入したリーダーに情報を登録することで、施解錠の対象となります。
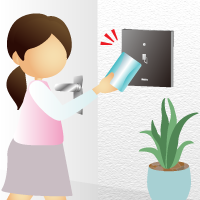
◎後付けする電気錠の選び方
電気錠の後付けには、設置する場所によって適した操作部を選ぶことでより使いやすくなります。例えば、玄関先で小さい子どもを抱っこしていて両手がふさがっているときや傘を持っているとき、一般的な鍵で開けるにはひと手間かかります。そんなとき電気錠を後付けしてスマートキーを導入すれば、バッグにいれているだけ、ドアノブのボタンを押すだけ解錠できるため、小さいお子さんやご高齢の方がいる家庭に適しています。不特定多数の人が出入りするオフィスにおいては、電気錠と入退室管理システムを連動させる方法もあります。電気錠を後付けすることで物理的な鍵が不要となり、従業員が保有するスマートフォンや社員証、PASMOやSuicaといったICカードを鍵として登録することができ、退職した際の削除も簡単です。入退室管理システムを導入するとタイムカードの打刻をせずに社員の勤怠管理が行えます。病院では感染症予防対策として、建物の出入口や各部屋のドアなどに手が触れる必要のない顔認証や非接触カードが適しています。近年、訪日外国人の宿泊として「民泊」が増えています。シリンダー錠の鍵の受け渡しに負担や紛失のリスクがありますが、電気錠を後付けすることによって、鍵の受け渡しから解放され、合鍵を不正に作られる心配もありません。リーダーによっては宿泊客に対して一時的に暗証番号を発行することができたり、日によって暗証番号を変更したり、利用者が任意で暗証番号を設定したりできるタイプもあります。
◎電気錠を後付けする業者の選び方
専門業者を選ぶときに押さえておきたいポイントはいくつかあります。まず見積書の内訳に出張費や作業費、追加料金などの料金設定が、明確化されているかをチェックしましょう。やむなくキャンセルをしたときのために、キャンセル料がしっかり提示されているかも大切な確認事項です。業者が電気錠の後付けを行った際に、ドアや壁や鍵が壊れたり、傷ができたりした場合のために保証が設けられている業者を選びましょう。また、電話対応はお店の顔とも言えるので、電話のやり取りがしっかりしているか、質問をした際に丁寧な対応が返ってきたかなどもチェックしましょう。最後に電気錠の後付けをしたら完了ではなく、アフターフォローがしっかりしているかもポイントです。電気錠を後付けする専門業者を選ぶ際には価格が安いのはもちろん、ホームページを隅々まで見て信頼できる業者か見極めることが大切です。定期的にコラムやブログを更新していると、業者の雰囲気を気軽に感じられます。
◎まとめ
電気錠はオフィスや病院、住宅などさまざまな場所で導入されています。自宅で設置する場合は、家族の年代によって解錠方法に選択できるタイプが便利です。従業員が多いオフィスや病院などでは、個人で使用しているICカードやスマートフォンを鍵とすることで、コスト削減にもつながります。安心で快適な暮らしを求めるために、電気錠の後付けをご検討されている方は、年中無休24時間受付をしているカギ舎へご相談ください。