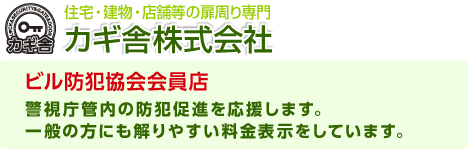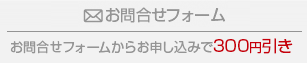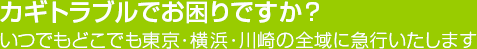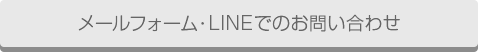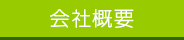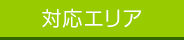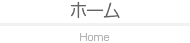自動ドアの扉の仕組みと鍵交換
日本の自動ドア普及率は世界でも有数です。今ではスーパーや病院・ビルなどさまざまな施設で使われているため、自動ドアを見ない日はありません。日常的に使われている自動ドアだからこそ、鍵交換による防犯対策が必要です。この記事では、自動ドアの構造や鍵交換をする必要性、鍵の種類などご紹介します。
◎自動ドアの扉の仕組み
自動ドアは、自動ドア上部にある「ドアエンジン」「コントローラー」「タイミングベルト」「従動プーリー」の4つの機器から構成されており、無目と言われるアルミサッシでできたケースのなかに機器が入っています。ドアエンジンとは自動ドアの動力源とされる部分です。ドアエンジンが動くことによって自動ドアの開閉がされることにより、自動ドア間を自由に行き来することができます。コントローラーとは自動ドアの司令塔の部分にあたり、制御装置とも言われています。コントローラーは、人と物などを感知するためのセンサーから信号が送られ、その信号をもとにドアエンジンを動かす従動プーリーという滑車部分とタイミングベルトが連動することで、扉が開閉される仕組みとなっています。コントローラーが信号を受け取るのに重要になるのが、センサーと言われる部分です。センサーは自動ドアの上部に設置されているものが多く「起動センサー」「補助センサー」「保護センサー」にわけられます。起動センサーとは、自動ドアを開閉するためのセンサーのことを指しており、光線反応方式・電波方式・タッチ方式に分類されます。光線反応方式は、センサーから地面に向けて近赤外線が出されており、近赤外線の反射率の変化により人や物などを感知するセンサーです。電波方式は光線反応方式と同様の仕組みとなっており、マイクロ波のような電波をもとに人や物を感知することで自動ドアが開閉されます。タッチ方式は、センサーに人や物が反応するだけでは自動ドアは開閉されず、自動ドアに付けられている押しボタンを軽く押すことで自動ドアが開閉されます。自動ドアに付いているパネルに手で触れずに手を近づけるだけで、自動ドアが開くタイプが主流となっており、感染症予防のためコンビニエンスストアや病院、商業施設など人の出入りが多い場所で導入されています。補助センサーとは、自動ドアの間に人が転んでしまったり止まっている場合でも、扉に挟まれないように、センサーに触れている間は開き続けます。自動ドアの両端に付けられている光電方式センサーというセンサーに触れている間は、自動ドアが開いている状態になります。そのほかにも、光線反射方式・超音波方式といったセンサーは自動ドアに近づくだけで感知されるため、安全性はより高い種類となっています。保護センサーとは自動ドアに人が通過したり、立ち止まった際に閉まる自動ドアにぶつからないようにするセンサーのことです。起動センサーや補助センサーの機能を兼ね備えているため、より安全に自動ドアを利用することが可能となっています。

◎自動ドアの扉の種類
自動ドアの扉の種類は「引き戸」「二重引き戸」「回転ドア」と大きく3種類にわけられます。引き戸はコンビニエンスストアやビルなどさまざまな場所に設置されています。左右どちらかに開閉される扉や両扉が開くタイプになっており、自動ドア前後のスペースの確保が必要ないことから導入しやすく、多くの場所で普及されています。二重引き戸は引き戸に比べ1.3倍ほど開口幅があり、病院で車椅子を利用する人でも安心して通ることもできるため、より人の出入りが予想される場所に適した種類となっています。回転ドアは半時計回りに扉がゆっくりと流れているため、荷物カートを利用している人はもちろん、駆け込みによって人との衝突が避けられることが特徴となっています。外観のデザイン性も高いため、ショッピングモールやホテルなどに使われていますが、2000年代に回転ドアの巻き込み事故があったことがきっかけに、回転ドアを導入している施設は減少傾向にあると言われています。多くの企業や施設が自動ドアを導入する1番のメリットは利便性の高さでしょう。例えば、ドアは押したり引いたりすることで開きますが、そういった手間を省くことができるので、力のない小さな子どもやご高齢の方が扉で指を挟んだりする事故が減少します。さらにバリアフリーが施されているため、車椅子の方も安心して出入りすることが可能です。自動ドアを設置することにより開閉の心理的負担が解消されるので、幅広い年齢層が出入りする病院や商業施設などに適しています。そのほかにも施設内の温度を一定に保たないといけない場所でも自動ドアにすることで、開きっぱなしを防ぐことができます。室内エアコンなどの電気消費も抑えられ、省エネにもつながるでしょう。自動ドアは手を触れて開閉することがないので、衛生管理や感染症対策が必要な病院や食品を扱う工場などで導入されています。一方で自動ドアにもデメリットがあります。初期費用が数十万から数百万と高額になることが多く、定期的なメンテナンスも必要となってきます。メンテナンスを怠ってしまうとセンサーが正常に感知できず、挟まれ事故や巻き込み事故の要因となってしまいます。特に9歳以下の子どもや年配の方が自動ドア関連による事故が、2015年から2019年の間で400件以上発生していることから、日頃の事故防止のためにもメンテナンスが必要になってきます。メンテナンスを依頼する際は、自動ドアのメーカーや扉業者に依頼をしましょう。なかには悪徳業者が存在しており、メンテナンスを口実に、勝手に故障時連絡先シールを貼り替える業者や不要な部品交換を要求する業者がいるため、信頼ができる扉業者をピックアップしておくと安心です。

◎自動ドアの鍵の種類
自動ドアのメンテナンスは大切ですが、日頃の防犯対策として鍵交換も重要となってきます。強盗犯による侵入被害は一般住宅などに意識が向きますが、実は自動ドアの鍵が壊され侵入されてしまうケースも多くあります。防犯性の高い鍵に鍵交換をすることで、空き巣による侵入被害に備えましょう。自動ドアの鍵交換をする際に使われている物理的な鍵は「ピンシリンダー錠」「ディンプルシリンダー錠」「ディスクシリンダー錠」「レバータンブラー錠」などがあげられます。ピンシリンダー錠の見た目は、鍵の片方のみにギザギザが刻まれており、鍵穴の中にある複数のピンを押し上げて開ける構造になっています。シンプルなつくりになっているため、ピッキングがされやすく防犯性が比較的低い鍵とされています。ディンプルシリンダー錠は、ピンシリンダーの構造が複雑になった、防犯性に優れたシリンダーです。上下に限らず斜めにもピンがあることで複雑性が増しています。そのためピッキングが難しい鍵であると言えます。ディスクシリンダー錠の鍵は、両側がギザギザに刻まれているのが特徴的です。古い住宅に使われていた鍵で、ピッキングのターゲットにされやすいです。そこで、後継型としてピッキングにも強く防犯性が高いとされているのが、ロータリーディスクシリンダー錠です。タンブラーという鍵穴に鍵が入っていないときにロックされる防護さくが、鍵に入れることによりタンブラー部分が回転する構造になっているため、ピッキングが難しく防犯性の高い鍵とされています。レバータンブラー錠は別名棒鍵とも言われており、アンティーク調の鍵穴の形になっていることが特徴的です。古い自動ドアに使われていることが多く、自動ドアの内側につまみがついているため、サムターン回しの被害が多いです。レバータンブラー錠の製造数が減少しており、防犯性も低いことからレバータンブラー錠からシリンダー錠に鍵交換をする傾向にあります。
◎自動ドアの鍵交換をする必要性
自動ドアも玄関扉などと同様に、鍵をなくしたり折れてしまった場合は、鍵交換を行います。最新の鍵に交換することで防犯対策にもつながります。鍵交換をせずレバータンブラー錠のような防犯性の低い鍵を使い続けてしまうと、侵入被害を受けてしまうリスクがあります。1度強盗犯に侵入を許してしまうと、侵入しやすい建物と認識されてしまうため、鍵交換による防犯対策が必要になってきます。そのほかに鍵交換が必要になるケースとしては、鍵の劣化により鍵が入れづらくなったり、鍵が鍵穴のなかで折れてしまうなどのトラブルがあげられます。どんな鍵には寿命があり、鍵の使い方や使う頻度によって異なりますが約10年とされています。特に自動ドアは足元に鍵穴があることが多く、雨風によって鍵穴にほこりやゴミがつまったり、鍵穴自体の錆びにより鍵がかかりにくくなる原因にもなります。そのため、定期的に掃除機やエアダスターなどで鍵穴のごみを取り除き、鍵専用の潤滑油を使うことで鍵穴の回りが良くするなど、日頃からのメンテナンスを心掛けましょう。自動ドアの鍵交換は、各鍵メーカーから選べますが、今回は物理的な鍵としてMIWA製のシリンダーをご紹介します。シリンダー錠のなかでもU9シリンダーは、ロータリータンブラーを使用されています。ロッキングバーというピックと呼ばれる特殊工具でピンキングが行われた場合でも、シリンダー内にあるタンブラーがロックされるバーが取り付けられているので、安易にピンキングができない仕組みとなっています。そのほかにもタンブラー内が9枚で構造されており、鍵の切り込み深さが4段階になっています。理論鍵違い数が1億5,000万通りあるので、ピッキング対策にも防犯性にも高い鍵と言えます。U9シリンダーには自動ドアの種類によって対応している鍵があります。DGという鍵は1番普及されているもので、シリンダーの突出がなく、サムターン回しの防犯性が高いです。鍵交換をするときに自動ドアを外さなければ鍵交換ができないため、脱着作業費用がかかる場合があります。DG2という鍵はDGの改良版として、シリンダーや鍵のつまみの部分の突出が小さく、サムターン回しやバールによる自動ドアの持ち上げに対しても高い防犯性を誇ります。雨風によるシリンダー錠の耐食性能もされているため、鍵穴のつまりや劣化にも強くなっています。TRFは主に強化ガラス扉用錠と使用されており、内側がサムターンやシリンダーとさまざまなタイプがあります。サムターン回し対策としてはシリンダータイプに鍵交換をするとよいでしょう。

◎鍵交換は鍵の専門業者に依頼を
自動ドアの鍵交換をするときは、ホームページなどで情報を収集して、信頼のおける鍵業者に依頼すると安心です。鍵交換が必要なときは、大半が急な場面での鍵交換ではないでしょうか。例えば、鍵を紛失してしまったことに気づき、建物内に入れなくなってしまった場合は、急いで鍵業者に連絡をする必要があります。夜間や休日に関しては当日の鍵交換に対応できない業者もあるので注意してください。鍵交換を依頼する際は、受付窓口が年中無休で24時間対応をしている鍵業者を探しておくとよいでしょう。鍵交換も即日対応が可能であり、事前に作業の内訳が書いてある見積書を出している業者は安心です。自動ドアの鍵交換は複雑な作業になる場合があるので、鍵業者を探す際は自動ドアの鍵交換の実績があることを確認することも重要です。実績の少ない鍵業者に依頼をすると、鍵交換にかかる時間や費用が予想以上にかかってしまうことがあります。鍵交換で鍵業者を探されるときは、十分な実績があることを確認しましょう。また、費用を抑えるために自分で鍵交換をしようと、インターネット通販で鍵を購入する人がいますが、ご自身で鍵交換をすることは避けましょう。自動ドアの鍵交換は複雑になっており、鍵交換の知識があったとしても取り付けを間違えてしまうと自動ドアが開かなくなってしまいます。設置方法を誤ってしまうと防犯対策にならず、外部から侵入されるリスクが生じます。鍵交換の費用を抑えようとした結果、かえって余分に鍵交換の費用がかかってしまうので、鍵交換の際は鍵業者に依頼するようにしましょう。
◎まとめ
自動ドアに使用されている鍵は、古い鍵や防犯性の低い鍵が使われている場合があります。思わぬ鍵のトラブルが起こる前に鍵交換を行いましょう。カギ舎では、年中無休で自動ドアの鍵交換はもちろん、自動ドアの修理やメンテナンスなど熟練のスタッフが対応しています。防犯性の高い鍵に鍵交換をご検討されている方は、お気軽にカギ舎までご相談ください。