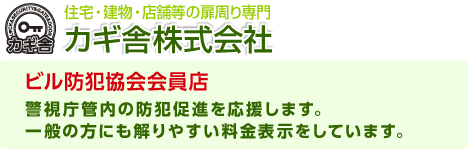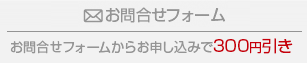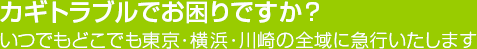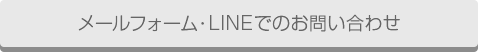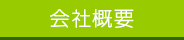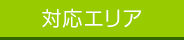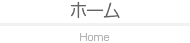入退室管理システムで二重認証を導入するメリット
近年、大きいオフィスや工場、公共施設などには、出入りする人の流れを厳重に管理するのと、セキュリティ性を向上させる目的で入退室管理システムの導入が進んでいます。入退室管理システムの認証方法はさまざまな種類があります。ひとつの認証方法を導入すれば防犯性アップにつながりますが、二重認証を採用することで、さらにセキュリティ性を高められます。この記事では、入退室管理システムにおける二重認証とは具体的にどのようなものなのか、二重認証の組み合わせや導入事例、二重認証を導入する際の注意点についてご紹介します。
◎二重認証の導入が広まっている背景
大企業ほど、社員や契約社員、派遣社員のほかにも、取引先や建物の出入口の管理を行う警備員や清掃員、エレベーターや警報設備の点検を行う作業員、配達員など、企業の入っているビルには実に多くの人が出入りしています。受付への人員配置や警備員だけでは、これらの人々の動きを全て正確に把握することは非常に労力が必要です。入退室管理システムが一般的に普及する以前は、企業の出入り口に警備員を常駐させるセキュリティ対策が行われていました。24時間稼働の工場や夜間無人になるオフィスには、夜勤専用の警備員を配置する必要がありました。出入口の監視に加えて定期的に施設内の見回りを行うためにはある程度人数が必要で、毎月多くの人件費がかかっていました。企業の規模が大きくなればなるほど、日中にもより多くの警備員を各エリアに配置しなければならず、さらにコストがかさんでいたのです。企業には、金庫やパソコンなどだけではなく、取引先などとの契約に関わる機密情報なども多く存在しています。万が一、取引先との契約内容や業務に関わる情報が外部に漏洩すれば、企業の信頼性が失われます。最悪の場合、契約破棄にもつながり多大な損害を被るのみではなく損害賠償案件につながることも考えられるでしょう。不審者や部外者の企業への不正侵入を防ぎ、社員や企業の財産、取引先や自社の業務に関わる機密情報を守るために急速に導入が進んでいるのが、入退室管理システムです。入退室管理システムとは、さまざまな認証方法を使い本人確認を行い、人の出入りを正確に管理し記録するセキュリティシステムのことをいいます。認証方法はひとつの方法を利用しますが、ときには2つの認証方法を導入する二重認証が採用されていることがあります。企業の出入り口に二重認証の入退室管理システムを設置することにより、 外部からの侵入者だけでなく、内部からの金品や資産、機密情報の持ち出しなど不正行為の防止にも効果を発揮します。内部で不正を行った人物の特定はもちろん、二重認証を用いた入退室管理システムにより使用したルートを把握することで行動履歴を確認ができます。問題の早期発見や解決につながるだけではなく、内部不正の抑制にも役立ちます。勤怠管理システムと二重認証による入退室管理システムとの連携により、従業員の勤怠管理を行うことが可能になります。勤怠管理とは、従業員の出勤または退勤時間、欠勤や遅刻、休日取得の有無などの記録について管理することをいいます。企業側は国が定めた労働基準法により、法定労働時間が適正であるか判断してそれに見合う賃金の支払いを行う義務を負っています。時間外労働や休日出勤は賃金の割り増しの対象になるため、企業側は勤務時間を正確に把握しておかなければなりません。二重認証による入退室管理システムの導入により、正確な労働時間を把握するだけではなく、不要な残業を防ぐことにも役立ちます。企業は大地震や火災など万が一の災害に備えて、従業員の誰がどこにいるのかを正しく把握しておく必要があります。二重認証による入退室管理システムを導入すれば、どの人物がどこのエリアや部屋にいるのかを把握することができ、迅速な避難や救出にもつながります。

◎二重認証を導入するメリット
入退室管理システムにおける二重認証のメリットとしてまずあげられるのが、セキュリティ性の向上です。2種類の認証方法を組み合わせた二重認証を導入することにより、セキュリティを格段にアップさせることが可能になります。入退室管理システムを導入すれば、エリア部屋ごとに二重認証に使用する認証方式を選択することができます。特定の部屋には限られた部署やある役職以上の者が入室できないようにすれば、機密情報の持ち出しなどのトラブルが発生するリスクを軽減できます。二重認証に人間の生体情報を導入した生体認証を採用すれば、なりすましによる不正な入室を防ぐことが可能です。二重認証による入退室管理システムを導入すれば、企業に拠点が複数あってもデータを本社で一元管理ができます。二重認証に利用できる生体認証には屋外でも使用できる機器があるため、企業や工場の駐車場のセキュリティ管理にも導入できます。車両内にいたまま二重認証が行える入退室管理システムを導入すれば、出勤や退勤時の混雑緩和につながります。入退室管理システムにおける二重認証を導入すれば、リアルタイムで正確な勤務状況の把握ができるとともに給与計算の効率化にもつながります。最近は働き方の変化に伴い、一般的なオフィスだけではなくコワーキングスペースやシェアオフィスを利用する人も増えています。コワーキングスペースとは、ほかの人間が場所を共有して業務を行うために提供されるスペースのことをいいます。個人専用の席ではないため、自由に席を選んだり途中で移動することが可能です。ネット環境はもちろん、コピー機など一般的なオフィスとほとんど変わらない環境が整っていることが多く、リラックスしてスムーズに業務を行うことができます。個人事業主やフリーランス以外にも、一般企業の従業員が在宅勤務の際に利用することがあります。シェアオフィスとは、ひとつのオフィスを複数の企業や個人がシェアして使うシステムを導入しています。シェアオフィスのメリットとしては、オフィス開設にかかる初期費用を抑えられることがあげられます。それぞれのシステムに関して明確な定義はありませんが、作業スペースが広いひとつの空間となっているのがコワーキングスペース、個室の形態を導入しているのがシェアオフィスとなっています。コワーキングやシェアオフィスを利用する際には、利用するたびに受付で手続きを行わなければなりません。短時間コワーキングスペースを利用する場合でも、利用時間や席の種類などを毎回受付に伝える必要があり、その都度利用料の支払いが必要となります。シェアオフィスに二重認証による入退室管理システムを導入すれば、ネットから事前に予約することが可能です。認証機器に事前に本人確認の情報を登録しておくことにより、面倒な手続きを行わずにコワーキングスペースを利用できます。レンタルオフィスの利用者側だけではなく、管理者側にもメリットが多いのも二重認証の入退室管理システムへの導入の特徴です。人の出入りの状況はもちろん、管理用のパソコンの画面に現在誰がどの場所を利用しているか表示されます。状況がひと目でわかるため、次に来た利用者にどの部屋や席を貸し出せるのか迅速に判断できます。コワーキングスペースは、普段から不特定多数が出入りする場所です。一般的な企業より金品やパソコン機器などの盗難や不審な人物が侵入するリスクが高いといえます。利用者が安心して利用するためには、二重認証による入退室管理システムの導入が適しています。ICカードや生体認証を組み合わせて認証する二重認証の導入により、部外者の入室を防げます。シェアオフィスにおいて、パソコンや資料などの手荷物などを保管できるスマートロッカーは、二重認証を導入した入退室管理システムでの管理が可能です。スマートロッカーとは、スマートフォンがカギの代わりとなるロッカーのことをいいます。コワーキングスペースは、新たな資格取得を目指す社会人、大学生や専門学校生などの学生が利用することもあります。資格取得の勉強や受験勉強などをする際には、多くの問題集や参考書などの勉強道具を持ち歩かなければならないため、移動する際に荷物が多くなり負担がかかります。スマートロッカーに参考書を預けておけば、その都度持ち歩く必要がありません。シェアオフィスのなかには、利用者向けにスマートロックにより郵便物の受け取り、保管サービスを導入している所があります。事前に予約ができたり、キャッシュレス決済が可能なものがあり利便性が高いものとなっています。スマートフォンを利用するロッカーのほかにも、暗証番号を入力して利用できるロッカーを導入しているレンタルオフィスもあります。

◎二重認証の組み合わせ
入退室管理システムの認証方法は、暗証番号認証やICカード認証、指紋認証や静脈認証、虹彩認証、顔認証といった生体認証など、複数の認証方法があります。2つの認証方法を組み合わせて利用可能な二重認証システムを導入している機器もあります。二重認証にも利用される暗証番号認証とは、機器のテンキーやタッチパネルの画面に表示された数字を使い、暗証番号を入力して認証を行い部屋に入室します。暗証番号については、0〜9までの数字を組み合わせて決めます。二重認証が可能な暗証番号キーには、配線工事を行い電気で施解錠する電気錠、電池を使って施解錠する電子錠、電気の力を使わず物理的に施解錠するキーレックスがあります。ほとんどの機器は、暗証番号を何度も変更することが可能となっています。タッチパネルタイプの暗証番号錠には、番号を入力するたびに数字の並びが変わるランダムキータイプがあります。これはタッチパネルに残っているわずかな指紋の跡から、他人に暗証番号を知られることがないようにするためのシステムです。ほかにも、適当な数字を入力してその後正確な暗証番号を打ち込む、ごまかし機能を導入している機器もあり、そばに暗証番号を知られたくない人がいる場合には、この機能が役立ちます。暗証番号認証には、定められた回数の暗証番号の入力を間違えると一定時間は操作が行えなくなるセキュリティ性の高い機器もあります。二重認証に対応した暗証番号認証錠を導入すれば、外出する際に金属製のカギを持ち歩く必要がなくなります。それにより、カギの紛失や盗難、不正に複製され利用されるリスクを回避できます。企業においても、従業員の人数分のカギを用意する必要がなく、カギの作成費用の削減につながります。金属製のカギは誰かひとりでもカギを紛失すると、ドアについているシリンダーと呼ばれるカギ穴部分も交換しなければなりません。交換を行うためには、カギの専門業者に依頼しなければならず、作業代だけではなく出張費もかかることがあります。二重認証に対応している暗証番号認証を導入すれば、これらにかかる手間や費用を省けます。暗証番号認証錠は、万が一暗証番号を見られたとしても番号を変更するだけで良いため、余分なコストはかかりません。セキュリティ性の向上のために、定期的に暗証番号を変更してオフィス内で共有するのも有効です。二重認証にも利用できるICカード認証は、企業の出入口や各エリア、部屋のドア付近に導入された認証機器に、カードを通したりかざすことにより本人確認を行います。二重認証に利用できるカードには、磁気やICチップが内蔵されています。磁気タイプは黒いストライプ状の模様があり、この部分に情報が記載されています。磁気タイプのカードは、スマートフォンや車のロックキーなど磁力を発生させるものと一緒に持ち歩いていると、磁気不良を起こし突然カードが使えなくなることがあるため注意が必要です。財布などにキャッシュカードや店舗のポイントカードなどと一緒にまとめて保存している場合も、同じような症状が起こることがあります。ICチップタイプは、認証時にカードに埋め込まれたチップに情報を保存します。ICカードは磁気カードと比較して、非常に多くの情報を暗号化して保存できるのが特徴となっています。ICチップは磁気の影響を受けないため、磁気不良が起こる心配がありません。日本国内において認証可能な入退室管理システムに利用されているICカードの規格には、FeliCaカードとMIFAREカードが導入されています。日本を代表する企業のソニーが開発したFeliCaは、価格が安価であり、日本だけではなく世界でも多く普及しているカードとなっています。電車やバスなどで利用できるSuicaなど交通系カードのほかにも、スマートフォンの便利な機能であるおサイフケータイにも導入されています。二重認証にも利用できるICカードのMIFAREは、企業において社員証として導入されているケースが多く見られます。部外者の侵入や個人情報の持ち出し防止のために、オフィスのエレベーターやプリンターを使用する際にも認証を行うケースもあります。二重認証にも利用できるカード認証錠は、一般的なカギのようにホームセンターなどで簡単にコピーを作成できないこともメリットといえるでしょう。二重認証に活用可能なカードは、薄くて軽いためパスケースなどに入れて持ち運びやすい反面、雑に扱うと割れたり折れ曲がったりすることがあるため注意が必要です。二重認証に利用できる生体認証は、人の身体の特徴を活用して本人確認を行う仕組みを導入しています。認証精度が高くなりすましや偽造がほぼ不可能であるとされており、セキュリティ性が非常に高いといえます。二重認証に利用できる生体認証には、指紋認証や顔認証、静脈認証や虹彩認証などがあげられます。二重認証に利用可能な指紋認証は、認証機器にあらかじめ登録した指を置くことにより本人確認を行います。指紋は双子でも模様が違っているため、なりすましは困難となっています。二重認証に利用できる静脈認証には、指静脈認証と手のひら静脈認証の2種類があります。静脈内のヘモグロビンのパターンを読み取り、認証を行います。静脈のパターンは人ごとに異なり一生変わらないことから、非常に精度が高くなおかつ偽装される可能性が低い認証方法といえるでしょう。二重認証に導入可能な指静脈認証は、指を認証機器にかざして認証します。二重認証にも使える手のひら静脈認証は、手のひらを広げて読み取り機器にかざし本人確認を行うシステムが導入されています。二重認証に採用できる虹彩認証は、瞳の中にある虹彩により認証を行います。虹彩は瞳のなかにありドーナツ状の形をしています。虹彩は同じ人物の左右でも異なるため、なりすましによる不正な認証はほぼ不可能となっています。二重認証に適している顔認証は、顔の目や鼻、口の位置や比率などのデータを元に認証を行う仕組みを導入しています。二重認証に利用できる顔認証には、ビジュアル方式の2D認証とIR方式の3D認証があります。2D認証は、顔の目や口などの位置をデータベースと比較して本人かどうか識別します。ヘアスタイルやメイク、サングラスの着用により認証しにくかったり、周囲の光量が認証精度へ影響を及ぼすことがあります。二重認証に導入可能な顔認証の3D認証は、赤外線センサーにより顔を立体的に認識してデータとして照合します。認証精度が高く、光の量やメイク、メガネなどに左右されることはほとんどありません。サーモカメラ導入の顔認証機器では、カメラが認識した人物の体温を測定できます。マスクを着用したままでも認証可能な、マスクモード付きの顔認証機器もあります。二重認証の組み合わせにはいくつか種類があります。カード認証と暗証番号認証の二重認証可能な機器は、認証機器にカードを軽くタッチした後に正しい暗証番号を入力し、本人確認を行うとともに履歴を管理します。二重認証の本体機器のみで、カード認証や暗証番号認証のログ管理や電気錠のコントロールが可能なものもあります。本体内に保存された入室や退室の履歴は、パソコンに専用の管理ソフトをインストールすればいつでも確認することができます。ICカードと顔認証の二重認証は、入退室管理システムに導入できるフラッパーゲートを採用すればさらなるセキュリティアップにつながります。フラッパーゲートとは、とくセキュリティ面を強化したいエリアの出入り口に設置するゲートのことをいいます。カード認証と顔認証による二重認証を行うと、フラッパーと呼ばれる扉が開き、通過すると扉が閉じる仕組みとなっています。顔認証付きのカード機器は、顔認証とカード認証の二重認証の仕組みが導入されています。医療機関や調剤薬局を利用する際には、受付の際に健康保険証と連携したマイナンバーカードを使うことがあります。マイナンバーカードにはICチップがついており、署名用電子証明書と利用者証明用電子証明書という2種類の電子証明書類が搭載されます。二重認証機器を利用する際には、専用に機器にマイナンバーカードを置き、カードのICチップにより認証します。同時に顔認証装置に顔を向けることにより本人確認を行います。二重認証可能な機器には、カードの置き忘れを音で知らせる置き忘れ通知機能を導入しているものもあり、カードを忘れる心配がありません。従来の健康保険証のように月ごとに窓口で提示する必要がなく、窓口の事務員の確認作業の負担も軽減され人件費の削減につながります。人の目で確認することにより起こるミスを防げることも、二重認証導入のメリットといえるでしょう。二重認証を行う顔認証付きカード機器には広角カメラレンズが導入されているため、小さなお子さんや車椅子を利用している方でもスムーズに認証することが可能です。非接触で受付ができ、感染症対策としての効果も期待できます。静脈認証と指紋認証による二重認証は、非接触型指ハイブリッド認証と呼ばれています。指紋のデータと指の静脈データの2種類の生体情報を利用して、二重認証を行います。2種類の情報を組み合わせて二重認証するため、指が乾燥したり濡れている場合や血管の細い指など指の状態に左右されることがなく、正確な認証が可能となっています。二重認証の端末に指をかざすだけで使用でき、指が直接センサー面に触れない非接触の仕組みを導入しています。そのため衛生的で指紋残留の心配もありません。外部から見えない指の内部にある静脈を二重認証に利用するため、偽造や改ざんが極めて困難で、非常にセキュリティ性に優れています。二重認証機器のなかには、なりすましがほぼ不可能な顔認証と虹彩認証を組み合わせた認証方式を導入しているものもあります。顔認証と虹彩認証の二重認証機器には、日本の大手企業が開発した技術を採用しています。顔の情報とともに、左右の目で異なる虹彩の情報の3つの要素を合わせて二重認証を行うことにより、高い認証精度を実現しています。二重認証機器には、カメラが人に合わせて位置調整を行う機能が導入されているため、スピーディーな認証が可能となっています。顔認証と虹彩認証の二重認証機器には、写真によるなりすましをブロックする機能が搭載されています。マスクやゴーグル、帽子などで顔の大部分が覆われている場合でも、外したりずらすことなく認証が可能です。企業における二重認証を導入した入退室管理システムは、さまざまなシステムと連携することにより幅広い利用が可能となります。二重認証機器と警備システムを連動させれば、特定の区画内への部外者や不審者の侵入などをより早く検知できます。不審者を発見した場合には、警報を鳴らしたりランプを点滅させて威嚇できます。警備システムからの信号を二重認証機器が受信することにより、器械の利用停止も可能になります。警備会社や警察署に通報を行うこともできます。二重認証機器と火災報知器を連動させれば、万が一火災が起きた際には、全てのエリアの出入り口が開放され認証を行わなくても開くため、逃げ遅れを防げます。二重認証による入退室管理システム入退室の記録から、いつ誰がその部屋にいたのか履歴を残すことができ災害時の従業員の在籍確認にも役立ちます。

◎二重認証を導入する際のポイント
入退室管理システムの二重認証機器をオフィスに導入する際、気をつけなければならない点はいくつかあります。オフィスなどへ導入する入退室管理システムを選ぶ際には、どの認証方法を導入するか、二重認証機器を採用する場合は認証方法の組み合わせを考えることが重要です。機密保管エリアなど特定の場所の防犯性を高め不正侵入を防ぎたい場合は、顔認証などといったセキュリティに優れた認証方法とICカード認証を組み合わせて二重認証にするといいでしょう。二重認証による入退室管理システムを導入する際には、初期費用やランニングコストを検討することも重要です。初期費用としては、二重認証の装置の購入費用、設置工事や入退室管理システムのサーバー構築などに関わる費用が必要となります。導入するオフィスの設置数や認証装置の種類により、二重認証機器の設置費用は異なります。二重認証機器のランニングコストとしては、利用料金やサーバー保守費用、定期的なメンテナンス費用などがかかります。二重認証による入退室管理システムは、導入を決めてからは運用開始まである程度時間がかかります。オフィスの新設や移転に伴い二重認証に対応した機器を導入する場合には、電気工事の業者や通信工事業者との調整も必要になります。運用開始時には、業者の立ち合いの元に二重認証機器の使用方法の確認が必要です。二重認証機器の運用開始前には、企業内での運用方法のルールを明確にしておきましょう。二重認証機器に故障にトラブルが発生した際には、修理や二重認証機器の交換が必要となることがあります。二重認証機器の設置が完了した後も、業者によっては一定期間無料で修理を行う保証期間を設けているケースがあります。二重認証機器の定期的なメンテナンスなど、導入後のサポート体制がどのようになっているかをチェックすることも大切です。

◎入退室管理システムにおける二重認証の導入事例
入退室管理システムにおける二重認証は、規模の大きい企業をはじめ、多くの場所で採用されています。
○オフィスの出入り口に二重認証を導入した事例
関東にあるオフィスでは、移転に伴い顔認証と虹彩認証を組み合わせた二重認証による入館管理システムを導入しました。オフィスには関係者以外立ち入り禁止のエリアがあり、不正な入場を防ぐ高度なセキュリティ対策と、従業員の本人確認の効率化が大きな課題となっていました。顔認証と虹彩認証による二重認証を導入することにより、特定のエリアの出入り口の厳格な本人確認を行うとともに履歴管理を行えるようになりました。2種類の生体認証による二重認証の導入は、なりすましによる不正侵入を防止するとともに厳格な本人確認と高い利便性の両立が実現できました。


○24時間営業の温浴施設に二重認証を導入した事例
サウナ施設などを導入している24時間営業の施設で、以前は入り口にICカードによる認証方法が導入されていました。しかしひとりの認証でほかの人を意図的に招き入れる不正行為がたびたび起こっているのが問題視されていました。そのため、ICカード認証と顔認証が可能な二重認証に対応した機器を導入しました。温浴施設の利用時にはICカードと顔認証の二重認証が必須であるため、不正な行為が行われるリスクを軽減できます。温浴施設内にあるロッカーにも認証が必要なシステムを導入したため、貴重品の盗難の心配もなくなりました。

○総合病院で顔認証付きカード機器を導入した事例
都内のある大きな病院では、受付業務の効率化とセキュリティ性を高める目的で、はじめに総合受付に顔認証も含まれたカード認証機器を設置しました。その後、それぞれの診療科の各外来の受付にも二重認証機器を導入しました。二重認証の導入により健康保険証の確認ミスがなくなり、よりスムーズに受付が行えるようになりました。


◎まとめ
入退室管理システムにおける二重認証は、違うタイプの認証方法を組み合わせることでより安全性を高めることが可能です。二重認証の認証方法の組み合わせは複数存在しています。企業に導入する際には、各々の認証方法の特徴を把握してそれぞれのニーズに応じて選択し導入することが重要です。カギ舎では、金属製のカギや電気錠・電子錠をはじめ、二重認証機器についての設置工事のご依頼やご相談にも随時対応しています。当社は年中無休24時間営業で、二重認証機器の導入に関わる相談に応じていますので、お気軽にお問い合わせください。