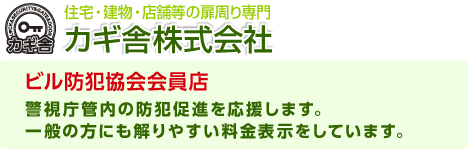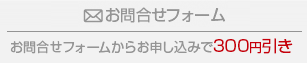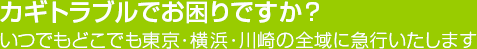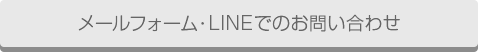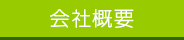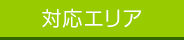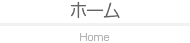自動ドアに後付けカードリーダーで安心な入退室管理を実現
利便性が高い自動ドアは、オフィスや商業施設、病院、事務所、マンションなどあらゆる場所に導入されています。しかし、特定の人が利用する建物や部屋などの自動ドアにおいては、不審者や部外者を防止するセキュリティ対策が重要です。既存の自動ドアに許可された人のみ入室できるカードリーダーを設置すると、不正侵入を防止や建物内の安全性が守れます。この記事では、自動ドアに後付け可能なカードリーダーの導入メリットや、カードリーダーKJ-150の仕組みをご紹介します。
◎自動ドアの仕組み
自動ドアとは、扉の開閉を人力で動かすのではなく、電気などの動力を用いて自動で扉の開閉を行うことをいいます。自動ドアは、公共施設やコンビニエンスストアなどの出入口の扉に導入されており、センサーが人を検知すると扉が開き、人や物が通り過ぎると扉が自動で閉まる仕組みです。両手に荷物を持っていても扉の開閉を行うため、入退室がスムーズです。自動ドアの基本機能は、センサー、コントローラー、モーター、ガイドプーリ、ベルト、レール、戸車、ガイドレールなどの装置で稼働しています。センサーとは、通行人を検知してコントローラー部に信号を送る起動センサーや、起動センサーが気づきにくい部分に検知する補助センサー、ほかにも、扉が閉じようとした扉に人が挟まれないようにする保護センサーなどが使用されています。また、ボタンを押して開くタッチパネル式センサーなども存在します。自動ドアの動作の流れは、センサーが通行人を検知すると、制御装置のコントローラーに信号が送られ、それを受けて駆動装置のモーターが、ベルトやガイドプーリなどを動かしドアが開く仕組みです。自動ドアの種類には、片引き戸、両引き戸、二重引き戸、開き戸、回転ドアなどのタイプが存在します。片引き戸は、1枚の扉が横にスライドして開閉するタイプで、玄関前が狭い場所などにも有効活用でき、扉が戸袋に収納されるため空間を広く見せます。両引き戸は 2枚の扉が中央から左右に開閉するタイプで、広いスペースを確保できることから、商業施設や公共施設などに最適な自動ドアです。二重引き戸は、2枚の扉が重なって収納される自動ドアで、一般的開き戸タイプのドアの広さより、1.3倍程の広さを確保します。開き戸は、扉の開く側にスペースが必要ですが、既存の開き戸に後付けすることができ、省スペースで導入ができます。回転ドアは、円筒形の形状の中に放射線の扉が複数あり、それを回転させて出入りする自動ドアですが、近年はあまり見かけないタイプです。利便性が高い自動ドアは、多様な場所で導入されていますが、オフィスや公共施設などでは、不正侵入を防止することから電気錠を活用した自動ドアも増えています。
◎既存の自動ドアをオートロック化する方法
自動ドアのセンサーの近くを通行すると、自動で扉が開く自動ドアですが、オフィスやマンションなどにおいては、誰でも自由に出入りできる環境の自動ドアでは、部外者や関係者以外の侵入を防止することができません。自動ドアは通常の戸締まりをする金属の鍵だけでなく、電気錠や電子錠など利用して施解錠することが可能です。自動ドアに電気錠を活用すると、カード認証や生体認証などの認証方法で入室権限を付与した人のみ入室でき、オートロック機能で利便性とセキュリティ性を高めます。既存の自動ドアがオートロック化されていない場合、電気錠を取り付けて配線するだけでは、オートロック機能を利用することができません。オートロックで扉を施錠する自動ドアには、集合玄関機やカード認証などを操作する電気錠の電気錠ユニットが、自動ドアの上部にセットされています。オートロックされていない自動ドアをオートロック化するには、その電気錠ユニットを組み込む必要があります。自動ドアの電気錠ユニットを組み込むには、主に自動ドアのメーカーが作業することが多く、そのため、そのメーカーに電気錠ユニットの組み込み工程を依頼するのが良いでしょう。自動ドアの電気錠ユニットに電気錠を設置し、カード認証、生体認証などの認証リーダーを導入すれば、認証リーダーで自動ドアの扉を解錠し通過した後も自動で施錠します。自動ドアの電気錠を操作する認証リーダーには、カード認証や暗証番号認証のほか、顔認証や指紋認証、静脈認証、虹彩認証などの生体認証が採用されています。既存の自動ドアに特定の認証方法の認証リーダーを運用することで、自動ドアの扉をオートロック化することができ、利用者の利便性と安全性を保てます。


◎自動ドアに後付けができるカードリーダーの機能
自動ドアに後付けでカードリーダーを設置すると、自動ドアから許可された人のみが入室できることから、関係者以外の不正侵入を防ぎ、セキュリティ性の強化が図れます。カードリーダーとは、ICカードなどをカードリーダーにかざすと、自動ドアが解錠される仕組みです。ICカードには、ICチップが搭載されており、データを記録するメモリとデータの処理を行うCPU(中央演算処理装置)が内蔵されています。ICカードをカードリーダーに近づけると、カードリーダー内にあるアンテナの電波を利用して、ICカードのアンテナと送受信を行い情報交換します。また、カードリーダーとICカードのやりとりは、無線通信を行うことから情報漏洩や改ざんを防止するため、暗号化通信で行い高いセキュリティ性を保つことができ安全です。カードリーダーに用いるICカードの特徴は、鍵を持ち歩くことがなく紛失により複製される恐れがないため、防犯面においても高い効果が見込めます。また、ICカードの大きさは、使いやすいサイズで、財布やカードケースなどに入れて持ち運びやすいことや、一枚のカードで色々なサービスを受けられる点が特徴です。自動ドアに後付けできるカードリーダーの非接触性タイプのICカードは、電子マネーや交通系カード、社員証、学生証などさまざま場面で活用されています。カードリーダーに活用するICカードの種類は、Felica規格と、MIFARE規格の2種類が使用されています。Felicaカードは主に日本で普及されているICカードで、高速で認証が行えるため、電子マネーや交通系カードなどに有効なICカードです。一方MIFAREカードは、国際的にもっとも普及率が高いICカードで、運用の容易性が高くFelicaより安価な価格で導入することが可能で、日本では、社員証や学生証などに利用されています。カードリーダーと入退室管理と連携すると、企業などの自動ドアでは勤怠管理にも役立ちます。
◎自動ドアに適したカードリーダー導入メリット
自動ドアにICカードを活用してカードリーダーを導入すると、通行する際に入退室を厳重に管理するなどのさまざまなメリットが見込めます。カードリーダーを搭載した自動ドアは、不審者などの不正侵入リスクをおさえる点が最大のメリットです。自動ドアに、従来の金属の鍵を使用している場合、紛失や忘れなどにより、複製や改ざんされる恐れがあります。一方で、カードリーダーに活用するICカードは、情報を抜き出すことやコピーが非常に困難なことから、紛失した場合でも悪用されるリスクを低減する認証システムです。また、カードリーダーに登録したICカードを紛失した場合、カードリーダーにて、そのカードを直ちに無効化することも可能です。カードリーダーを用いた自動ドアは、利便性の向上が期待できます。カードリーダーのカード認証は、カードをかざすだけで、誰でも簡単に自動ドアの解錠が行える点が特徴です。また、カードリーダーは非接触性の認証方法のため、直接指などで認証リーダーに触れずに認証が行えることから、衛生的な環境作りにも貢献します。自動ドアに後付けしたカードリーダーを搭載することで、ICカード認証により扉を解錠することができ、通行した後もオートロック機能により自動で施錠し締め忘れなどのリスクがありません。また、企業などでICカードの社員証を利用している場合は、そのカードを利用して自動ドアの解錠を行えます。そのため、管理者にとってはコスト削減や、利用者にとってはカード2枚を所持する必要がなく利便性も優れています。自動ドアにカードリーダーを採用すると、入退室管理に役立ちます。エントランスや室内のドアなどの自動ドアにおいて、カードリーダーを導入すると、いつ、だれが、どこから、入室したのかを記録することが可能です。そのため、万が一トラブルが発生した場合、履歴から入室者を確認することで原因が特定しやすいことや、外部からだけでなく、内部不正を抑止する効果もあります。


◎自動ドアに後付け可能のカード認証リーダーKJ-150
KJ TECH japanの日本国内専用規格のカード認証リーダーKJ-150は、自動ドアに後付け専用に特化した専用機器です。日本国内専用規格で、日本国内のニーズに特化した様式のため、使いやすく安心性が高い認証リーダーといえます。KJ-150のカード認証には、MIFARE UIDに対応しており、さまざまなICカードを使用でき登録は999枚まで行えます。MIFAREカードとは、暗号機能をシンプルに標準搭載しており、入退室管理カードや交通系カードなどさまざまなシーンで活用されているICカードです。ICカードをカードリーダーで利用するには、利用者のICカードを事前に登録します。認証する際は、ICカードをカードリーダーにかざすことで認証し、ICカードが登録されていると解錠される仕組みです。カード認証のほかには、数字の組み合わせで認証を行う暗証番号認証で解錠することができ、万が一カードを忘れた場合に有効な機能です。本体のカードリーダーは、シンプルで洗練されたデザインで、あらゆる空間に馴染みやすく、坊雨型IPX3も備えているため、建物の軒下などの屋外設置にも適しています。KJ-150の配線部分の電源線は12V〜24Vの入力のため、既存の自動ドアの感知センサーの線を延長してそのまま接続することができる点がメリットです。また、カードリーダーは、インターホンと連動することが可能で、インターホンから呼び出しがあった場合、室内用の親機から自動ドアの電気錠の解錠が行えます。ほかにも、モータ錠自動扉シャッターでは、シャッター制御盤への接続を行うと連動することが可能です。駐車場ゲートはゲートの制御盤とカード認証リーダーKJ-150を接続すると、カードをかざすだけでゲートを解錠します。操作もパソコンを使わずに本体のカードリーダーで、カード認証や暗証番号認証などの新規登録や削減などの操作が簡単に行える点がメリットです。
◎自動ドアにカード認証リーダーKJ-150を導入した事例
オートロック機能がついていない自動ドアに、カード認証リーダーKJ-150を活用すると、飛躍的なセキュリティ対策の構築や利便性の向上が実現します。
⚪︎オフィスのエントランスの自動ドアにKJ-150を導入
企業では、個人情報や顧客情報、資産などを保有していることから、エントランスの出入口においての不正侵入を防止する物理的なセキュリティ対策は重要です。誰でも簡単に入室できるエントランスの自動ドアに、後付けでカードリーダーを導入すると、関係者以外の入室や不審者などの不正侵入を防ぎます。KJ-150を導入する際、オフィスで社員証などのICカードを利用しているのであれば、新しくICカードを用意する必要がなくコスト削減にもつながります。カードリーダーに活用するICカードは、入退室管理だけでなく、勤怠管理システムと紐付けすると、従業員の勤怠管理にも貢献します。
⚪︎集合住宅マンションのエントランスの自動ドアにKJ-150を導入
近年、オートロックマンションが増えていますが、オートロック機能が付いていない自動ドアのマンションも少なくありません。既存の自動ドアに後付けでカードリーダーを設置すると、エントランスの自動ドアをオートロック化することができ、ICカードで解除後には自動で施錠され、防犯性を高めます。また、自動ドアをオートロック化することで、訪問セールスや勧誘などを避けるほか、空き巣などの抑止効果にもなります。マンションの居住者は、ICカードでエントランスの扉を解錠して入室しますが、インターホンと連動すると、来訪者があった場合、室内機で扉の操作が行えます。


◎まとめ
建物や室内用などの自動ドアにオートロック機能がついていない場合、後付けでカードリーダーを導入することが可能です。カードリーダーを用いた自動ドアは不審者や部外者などの不正侵入を防止することから、セキュリティ性が格段にアップします。カギ舎では、自動ドアの後付け専用の、KJ TECH japanのカード認証リーダーKJ-150をお取り扱いしております。オフィスや公共施設などの自動ドアにおいて、カード認証リーダーをお考えの方は、ぜひ、カギ舎までお気軽にお問い合わせください。