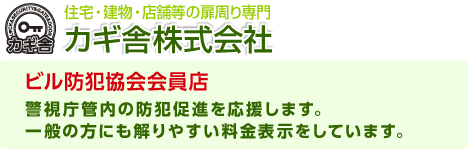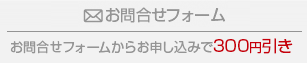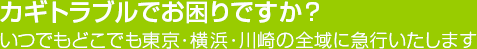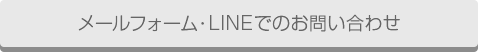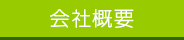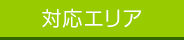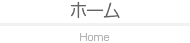ビジネスホンにおける故障の症状と原因
「今日は電話がかかってこない」「発信しようと思ったら反応しない」など、ビジネスホンが急に使えなくなることがあります。この記事では、ビジネスホンの耐用年数や故障の症状とその原因、ビジネスホンの故障を防ぐための日頃のメンテナンスなどについて解説します。「ビジネスホンが故障したかもしれない…」と思ったらぜひ参考にしてください。
◎ビジネスホンとは
ビジネスホンとは、複数の電話機で少ない電話回線を共有できるシステムです。家庭用の一般的な電話機では、1つの電話番号に対して1台の電話機だけですが、ビジネスホンでは1つの電話番号を何台もの電話機で同時に使用できます。たとえば、電話番号が1つでオフィスには5台の電話機があるとします。1つの電話番号に電話がかかると5台すべての電話機がコール音を鳴らして着信を知らせるうえに、どの電話機の受話器を上げてもかかってきた電話を受けられるのがビジネスホンです。電話回線を共有できるビジネスホンには「転送」という便利な機能があります。一般的な家庭用電話機では着信を受けた電話機でしか通話ができないため、自分以外の人への電話を受けたときにはその電話機まで来てもらい代わらなければなりません。しかし、ビジネスホンでは受けた電話を一旦保留にし「内線」機能を使って他のデスクへ転送できます。内線機能では、オフィス内の席が離れた同僚や違うフロアにいる上司などへ連絡をすることが可能です。通信費の削減に役立ち外線着信が転送できる内線通話は、広いオフィスでは特に便利な機能です。このように複数の電話機で少ない電話回線を利用できるビジネスホンですが、どのような構成となっているのでしょうか。まずNTTなどの電話回線がオフィス内に設置された「主装置」という機器に接続され、主装置を介してオフィス内のそれぞれの電話機につながっています。主装置には交換機の役目があり、主装置内のユニット(基板)がオフィス内の電話機に内線電話や外線電話をつないでいます。主装置のユニットは外線ユニットや内線ユニット、電源ユニットなどさまざまな種類があり、通話以外にも拡張ユニットを使うことでインターホンや電気錠、構内放送などいろいろな設備とビジネスホンを連動できる便利な機能です。

◎ビジネスホンの耐用年数
ビジネスホン主装置の耐用年数は6年と定められています。これは税務上の「法定耐用年数」で、企業が減価償却をするための期間です。減価償却とは、簡単に言うと資産を購入したときの費用を使用が可能な期間に分けて費用計上をする処理のことです。つまりビジネスホンは6年かけて原価償却をすることになりますが、必ずしもこの6年という期間を過ぎると故障につながるというわけではありません。もちろん機械なので6年を待たずして故障したり10~20年と使い続けたりする場合もあります。ただあまりにも長期にわたってビジネスホンを使い続けると部品の供給がされなくなったりサポート期間が終わったりして突然の故障に対応できなくなる恐れもあるため、この6年をひとまずの目安として故障に備えた修理や将来的な取替の計画を立てておくと良いでしょう。
◎ビジネスホンの故障の症状と原因
次にビジネスホンの故障が疑われる際の症状とその原因や対処法について解説します。
○使えない電話機が1台だけの場合
1台の電話機だけに不具合が発生している場合は、その電話機本体の故障やそこにつながる配線異常の可能性があります。ビジネスホンの電話機は電話線が抜けていると使えないので、まずは電話機に電話線がきちんと差し込まれているかを確認し、1度電話線を抜き差しして正常に動作するかどうかを試してみましょう。また電話機と受話器をつないでいるカールコード(クルクル状のコード)が抜けていないかもよく確認しましょう。電話機に接続されている線に異常がない場合は、故障している電話機を別の電話機と取り替えてみてください。取り替えた電話機が正常に通話できるのであれば、電話機本体の故障だと考えられます。電話機本体が故障した場合、同じ電話機を買ってきて取り替えてもビジネスホンでは使えない場合もあるので注意が必要です。ビジネスホンでIP電話機を使っている場合は、それぞれの電話機に設定されているIPアドレスというネットワーク上の住所に内線番号が割り振られているため、新しく電話機を用意したときは再設定が必要になるので、電話機を新しくする際は電話回線なのかIP回線なのかの確認をしておきましょう。電話機を取り替えてみても症状が改善されない場合は、配線にトラブルが起こっているかもしれません。電話機へ接続しているケーブルがデスクなどの重いものの下敷きになると断線してしまったり、床面で濡れるとショートの原因になったりすることがあるので注意が必要です。断線やショートは電気工事の知識がない素人が触ると感電などの恐れがあり危険なので、かならず電気工事の専門業者へ調査や修理を依頼しましょう。
○使えない電話機が複数台の場合
複数台の電話機に不具合が見られる場合は、1度ビジネスホン主装置の電源を切り再起動させてみましょう。主装置の再起動だけで症状が改善するケースもあります。再起動をしても症状が改善しない場合は、ビジネスホンの電話機でグループを形成するための主装置内線ユニットの故障や機器を接続しているハブの故障も考えられます。またLANケーブルを使用したビジネスホンの場合は、スイッチングハブの確認もしてください。スイッチングハブとは、LANケーブルをたくさんの電話機で使えるように分岐させる電源タップのような役割を持つ機器です。スイッチングハブの電源が落ちていると、そこに接続されている電話機がすべて使えなくなるので、電源が落ちていないかを確認したり、一度電源を切って再起動したりしてみましょう。また1本のLANケーブルの両端がどちらもスイッチングハブに接続されていると、「ループ」という現象が起こります。ループとは2本のLANケーブルが2台のスイッチングハブをつないでいたり、1台のスイッチングハブにLANケーブルの両端がつながっていたりすることで、ループ(輪っか)を作りデータが延々と回り続ける現象です。ループが続くとシステムダウンの恐れもあるので、レイアウト変更などでLANケーブルを抜き差しするときはケーブルとハブのポートに、番号を記入したビニールテープなどを貼ってケーブルが迷子にならないように注意してください。
○すべての電話機が使えない場合
ビジネスホンのすべての電話機が使えない場合は、それぞれの端末が故障しているのではなく、NTTなど電話回線に障害が出ていたりビジネスホンの主装置が故障したりしている可能性があります。グループ内での不具合と同様に、1度ビジネスホンの主装置の電源を切って再起動させてみましょう。主装置を再起動しても改善されない場合は電話回線の不具合の可能性があります。光回線を利用したIP電話の場合は、光信号と電気信号を変換するためのONU(回線終端装置)という機器も接続されています。このONUも主装置と同じように電源を切って再起動すると症状が改善するケースがあるので試してみてください。同時にNTTなど回線事業者のホームページなどで障害が出ていないかの確認もしましょう。

○通話中の音声に問題があるとき
相手に自分の声が聞こえなかったり、声が小さくて相手に聞こえにくかったりするケースです。これは受話器の送話口(口の部分)にあるマイクが故障している、電話機と受話器をつなぐカールコードに不具合がある、受話音ボリュームが小さくなっているなどが考えられます。
○電話機のボタン操作に不具合があるとき
電話器のボタンを押しても操作ができない、反応がよくないなどの不具合があるときは、ボタン部分にホコリなどの異物が入り込んで接触不良を起こしていたり飲み物などの水分をこぼしたりしたことで内部の部品が故障したことが考えられます。また経年劣化によってボタン接触部分の部品が摩耗を起こして正常に接続できない場合もあります。
○電話機のディスプレイに問題があるとき
電話機のディスプレイ表示が消えてしまった場合は、電話機本体に電話線が正常に差し込まれているかを確認してください。もしも電話線が差しこまれていなければ電話機は使えないのでしっかりと差しなおしてください。ディスプレイの文字がところどころ抜けている、のように部分的に表示がされているのであれば電話機本体の経年劣化による故障が考えられます。
○着信音が鳴らないとき
電話機の着信音が鳴らない場合は、電話機の設定を確認してみましょう。誤操作によって着信音量設定が小さくなっていたりオフになっていたりすることがあります。着信音量設定に問題がなければ電話機本体のスピーカー故障の可能性があります。
○内線が別の電話にかかってしまうとき
オフィス内のレイアウト変更や座席移動が原因で起こります。たとえば内線01の電話機をオフィスの違う部屋へ移動させても「内線01」としては使えません。電話線を使ったビジネスホンは、電話機ではなく電話線自体に内線番号が設定されているので、元の席の電話線に接続された電話機が内線01となるからです。(インターネット回線を使ったIP電話では電話機に内線番号が設定されます)またビジネスホンには、あらかじめほかの電話機へ内線を転送させる「不在転送」という機能が備わっています。以前に不在転送を設定してそのままになっている可能性もあるので、設定の確認もしてみましょう。
○子機が動作しないとき
ビジネスホンの子機が動作しない場合の原因のひとつはバッテリー切れです。常に子機をあちらこちらに持ち歩いて使用しているオフィスでは特に注意して、使わないときは充電器に収める習慣をつけましょう。ビジネスホンの子機はオフィスに設置してある無線アンテナを介して通話をしています。したがって無線アンテナの近くに障害物があると無線が届きにくくなり子機が動作しないことがあります。無線アンテナを移動する際はできるだけ障害物がなく高いところに置くようにしましょう。またビジネスホンの子機は携帯電話と同じようにどこへでも持ち歩くことができるため、落としたり濡らしたりしやすくなります。落下や水没は電話機の故障につながるので、持ち歩く際は注意が必要です。
ビジネスホンの不具合は故障ではないこともありますが、多くの場合は電話機本体や配線、主装置に問題が起こっています。ビジネスホンに故障が起こったときは素人では原因究明や修理が難しく、ビジネスホンの設置工事や配線工事は電気工事の有資格者でなければおこなえません。ビジネスホンに故障が疑われる症状が起こったときは早めに専門業者へ調査や修理の依頼をしましょう。

◎ビジネスホンの故障を防ぐためのメンテナンス
ビジネスホンの故障には、経年劣化以外にもさまざまな原因が考えられますが、ビジネスホンの故障を予防するための日頃のメンテナンスをご紹介します。1つは、ビジネスホンの電話機をこまめに清掃することです。電話機の押しボタンの隙間や受話器の送話口(しゃべる部分)などは、ホコリやゴミが侵入しやすく故障の原因につながります。定期的にエアダスターなどで電話機本体の清掃をしましょう。またデスクに電話機を置いていると、何かのはずみで飲み物や食べ物をこぼしてしまうことも考えられます。電話機専用のスタンドを使ってデスクから少し上にあげておくことをおすすめします。また電話機に接続されているケーブルは、断線やショートの原因となるのでデスクやキャビネットその他オフィス家具などの下敷きにならないよう注意しましょう。安心してビジネスホンを使い続けるためには専門の業者による保守点検もおすすめです。有償ですが各機器の動作状況の確認や清掃、バッテリーの残量確認、電源の電圧など自分ではできないメンテナンスが受けられるので安心です。
◎まとめ
突然ビジネスホンが故障してしまうと、業務に支障をきたすだけではなく、取引先やお客様にも迷惑をかけてしまいます。特にコールセンターなど数多くのビジネスホンを有する業種の企業ではビジネスホンの故障は命取りです。日頃からメンテナンスを行うことも重要ですが、突然のビジネスホン故障に備えてビジネスホンの故障が疑われたときに確認するべき点をしっかりと押さえておきましょう。またビジネスホンが故障したときにコストを惜しんで自分たちで修理しようとすると症状が悪化して余計にトラブルが大きくなる恐れがあるため、ビジネスホンに不具合が起こったときには専門業者への調査や修理をおすすめします。カギ舎は、ビジネスホンの設置実績を数多く持つ電気工事士の有資格者が在籍する専門の業者です。調査や見積もりだけでも無料なので「ビジネスホンが故障したかもしれない」と思ったときはぜひカギ舎までご依頼ください。