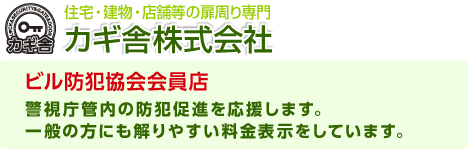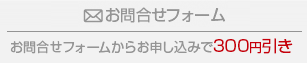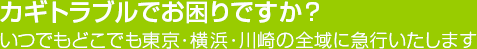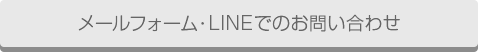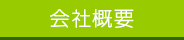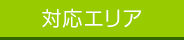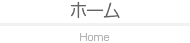セキュリティ重視なら電気錠に交換を!
「古い鍵だから壊れたりしないだろうか」「空き巣に入られたりしないか心配」など、今使っている玄関の鍵の防犯レベルに不安を感じている人もいると思います。不安を改善するためには電気錠に交換することをおすすめします。従来の鍵と違い、電気錠は電気の力で動く鍵で、鍵を持ち歩く必要がありません。オートロックや入退室管理システムといった高度なセキュリティ機能が搭載されており、オフィスやマンションのエントランスなど幅広く活用されています。今回の記事では、普通の鍵を電気錠に交換するメリット、電気錠の種類や交換の活用事例、交換するときの注意点についてご紹介します。
◎電気錠とは
電気錠は電気の力を利用した鍵のことを言います。電気錠は電気錠本体、操作部、制御部の三構造で成り立っています。電気錠本体は、普通の鍵でいう錠前にあたり鍵の解錠や施錠をする部分になります。普通の鍵と同じく鍵穴が付いているものもあれば、例えばカードキーを読み取る部分やテンキーだけで鍵穴のないものもあります。操作部はリーダーとも呼ばれ電気錠本体の近くに設置されており、暗証番号を入力するテンキーやカードキーなどを読み取る部分になります。制御部は電気錠本体と操作部に電気を送る部分になります。電気錠がきちんと動くように電力のコントロールをしており、いわば司令塔のような役割をしています。電気錠はこのように三構造で成り立っており、これらを正しくつなぐためには専門の電気工事士による配線工事が必須となります。そのため、電気錠へ交換するにはコストがかかり、建物の構造によっては導入が複雑になる場合があります。電気錠は電気の力を利用して施解錠しているため、停電が起きたときは操作ができなくなる恐れがありますが、予備電力で予防することが可能です。電気錠の種類にもよりますが、万が一操作ができなくなっても、内鍵を使ったりそのまま開けたりすることで対応が可能です。電気錠の耐久年数は規定によりおおよそ7年とされていますが、実際の使用頻度によって異なるため、定期的なチェックをしておく必要があります。このようにさまざまな解錠方法がある電気錠ですが、普通の鍵のままではどのようなリスクがあるのでしょうか。
◎普通の鍵のリスク
みなさんのなかには「ピッキング」という犯罪を聞いたことがある人もいるかと思います。ピッキングは空き巣がよく使う手口で、鍵穴に特殊な工具を入れて鍵を開け侵入します。最近ではインターネットの普及により、ピッキングに必要な道具やピッキングの方法を簡単に知ることができます。ピッキング技術が手に入りやすい世の中になったことから、ピッキング犯には鍵開けの素人が多くいると言われています。そのため、普通の鍵のままだと簡単に犯人の侵入を許してしまい、深刻な被害にあうことがあります。また、鍵をきちんと閉めたか不安になり、閉まっているかどうかを戻って確認したことがある人もいるかと思います。とくに高齢者の方に多いとされていますが、都度確認を繰り返していくと鍵を持ち歩くことにストレスを感じてしまいます。ほかにも、万が一鍵を失くしてしまったときは、鍵屋さんを呼んで、鍵を開けてもらわなければなりません。そのとき、失くした鍵は誰かに拾われてしまう可能性があります。また、鍵を失くしたのではなく、第三者に盗まれている可能性も考えられます。鍵を失くしたり盗まれたりすると、鍵を複製されたり、第三者がそれを使って侵入してくる恐れがあります。そのため、普通の鍵だとセキュリティという面から、シリンダー錠の交換をしなければならず、交換の費用がかかってきます。普通の鍵を使用していると、こういったリスクが考えられますが電気錠に交換することで、このようなリスクのほとんどを回避することができます。


◎普通の鍵から電気錠へ交換
電気錠は普通の鍵と違い、鍵を持ち歩く必要がなくなります。そのため、鍵を失くしたり、盗まれたりという心配はなくなります。カードキーやリモコンキーのように鍵の代わりに使うものはありますが、簡単に複製できるものではありません。万が一、カードキーやリモコンキーを失くしたり盗まれたりしても、電気錠本体の設定を変えてしまえば使えなくなるので、悪用される恐れはなくなります。また、電気錠は基本的に鍵穴がないため、ピッキングの心配はなくなります。電気錠の製品のほとんどがオートロックであるため、鍵をかけ忘れていないか心配…といったことがなくなります。このように電気錠はセキュリティ機能が優れており、普通の鍵のままだとセキュリティ対策が不安な場合、電気錠に交換することをおすすめします。電気錠のリーダーの種類にはさまざまなので、使用人数や用途に応じて選ぶと良いでしょう。
○カードキー
通常の金属鍵に代わって、ICカードや磁気カードを鍵として使います。カードを読み取り部分にかざしたり、挿入することで解錠します。かざすだけなら財布やパスケースに入れたままでも鍵の開け閉めができます。そのため、カバンなどから取り出す必要がなく、例えば忙しい朝のオフィスの出入りにとても便利です。カードは常に持ち歩く必要がありますが、万が一カードを失くしても、すぐにそのカードを使えないように設定することができます。カードは経年劣化の傷や汚れによって動作不良を起こしたり、磁気カードの場合磁気不良を起こしたりすることがまれにあります。しかし、カードは失くしたり壊したりしても、基本的にはすぐに再発行することができます。
○リモコンキー
普通の鍵に代わって、専用のリモコンを鍵として使い、リモコンを操作することで解錠します。カードキーと同じでリモコンを持ち歩かなければなりません。まれにですが、何らかの電波障害で、動作不良を起こすことがあります。その場合、リモコンキーを電気錠本体に近づけて操作すると、正常に動作することがあります。
○タッチキー
リモコンキーをバッグやポケットに入れたまま、ドアやドアノブについているボタンなどを押すとワンタッチで解錠ができます。やはり取り出す手間が省けるのでとても便利です。その都度鍵を取り出す、回すというストレスから解放されます。
○暗証番号式
あらかじめ暗証番号を機械に登録しておき、テンキーでその番号を打ち込むことで解錠します。鍵を持ち歩く必要がなくなるので、鍵を失くす心配は無くなりますが、番号を忘れないようにしたり第三者に知られないようにしなければなりません。定期的に暗証番号を変更することは可能です。
○生体認証式
身体の一部を本体に登録しておき、センサーで読み取って解錠を行います。具体的には指紋認証、顔認証、虹彩認証、静脈認証、音声認証などがあげられます。とくに指紋認証と顔認証についてはさまざまな場所で使われています。身体の一部を使うので、暗証番号式と同じく鍵を持ち歩く必要がなくなります。複製がほぼ不可能であることからセキュリティ面も万全で、大勢の人が出入りする会社や施設などで活躍しています。
○スマートロック
スマートフォンにアプリをあらかじめダウンロードしておき、読み取り部分にかざすことで解錠します。設定方法によっては遠隔操作も可能です。鍵を紛失したり暗証番号が知られたりする心配はありませんが、スマートフォンの電池が切れた場合、鍵の操作ができなくなる恐れがあります。充電が切れたときはモバイルバッテリーを使えばすぐにスマートフォンの充電ができ、正常に鍵の操作が行えます。


◎電気錠へ交換した活用事例
電気錠の種類はいくつかありますが、いずれも高度なセキュリティ機能を持っています。ほかにも入退室管理システムや鍵の遠隔操作など優れた機能があり、さまざまな現場で活用されています。
○オフィス
オフィスには、多くの機密情報や重要な備品を取り扱っているので、重要物の保守・管理をすることが重要です。普通の鍵から電気錠に交換することで、これらを適切に管理することが可能になります。例えば部屋の電気錠をあらかじめ特定の人物しか開けられないようにしたり、決められた時間にしか電気錠の操作ができないように設定することができます。この利点を生かしてオフィス内に侵入されたり、機密情報を知られたりするリスクを激減させることができます。また、電気錠には入退室管理システムと連動できるものがあります。入退室管理システムとは、オフィスの出入り口や重要物のあるドアなどに認証機能を設置して、いつ誰が出入りをしたかを管理する機能です。オフィスには多くの人が出入りするため、電気錠に交換し、入退室管理機能を活用することで、よりセキュリティを強化することができます。また、電気錠の入退室管理システムは社員の勤怠管理に活用することができます。例えば、社員証をカード認証できるものにすれば、比較的簡単に出欠や遅刻のチェックが可能になります。オフィスでは電気錠が多く導入されており、わずらわしい業務の短縮に活用されています。
○病院
病院もオフィスと同じく、電気錠に交換することで、高度なセキュリティ機能や入退室管理システムが活用されています。病院では、カードキーや指紋認証式の電気錠がよく活用されています。しかし、昨今の感染症拡大の面から、両方ともカードや読み取り部分に接触しなければならなかったため、最近では接触する必要のない顔認証式の電気錠に交換することで、感染症拡大の防止に取り組んでいる病院もあります。
○マンション
マンションでは、エントランスでオートロックや鍵の遠隔操作など、電気錠のセキュリティ機能が活用されています。インターホンで来訪者の確認をした後、遠隔操作でオートロックを解除することができます。また、マンションの住民は帰宅時に部屋に誰もいなくても、オートロックの鍵を使えばいつでも解除することができます。
○高齢者介護施設・障がい者施設
電気錠は、高齢者介護施設や障がい者施設でも活用されています。例えば認知症の高齢者の方や障がいのある方の場合、施設から勝手に出て行ってしまうことがあり、安全対策が重要となります。そこで電気錠に交換して、職員だけが鍵の操作をできるようにしたり、夜間など一定の時間は職員以外入退室できないように設定するなどして、安全対策が行われています。
◎電気錠へ交換するときの注意点
電気錠は規定により耐用年数はおおよそ7年とされています。しかし、使用頻度や経年劣化により、早めの交換が必要になる場合があります。経年劣化により機器本体や部品が故障・破損したりしていると、例えばカードキーが読み取れなかったり、暗証番号を入力しても反応しないことがあります。また、建物そのものや扉のゆがみによって、正常に施解錠がされないことがあります。このようなトラブルで電気錠が作動しない状況にならないためにも、気になるところがあったら早めに交換するほうが良いでしょう。また、電気錠の交換には必ず配線工事が必要になるため、鍵専門の電気工事士に相談したうえで交換をしてもらう必要があります。電気錠の交換は、電気錠の種類や取り付け業者によってかかる費用が変わってきます。鍵交換の業者のなかには悪徳業者も存在し、提示金額があいまいだったり、あとから高額請求される事例が発生しているため注意が必要です。電気錠の交換を行うときは信頼できる業者をあらかじめ見つけておき、作業内容や見積もり金額についての説明をきちんと受けてから、正式に依頼することが大切です。


◎まとめ
電気錠は普通の鍵に比べて非常に高いセキュリティ性能を持っています。普通の鍵を電気錠へ交換することで、オートロック、ピッキング対策、鍵の遠隔操作、入退室管理など高度なセキュリティ対策ができるほか、用途に応じてさまざまな機能が活用できます。電気錠には多くの種類があるため、活用する場面や使用人数によってどの電気錠に交換したら良いか決める必要があります。現在使っている普通の鍵を、電気錠に交換したいとお考えの方はぜひ1度カギ舎へご相談ください。